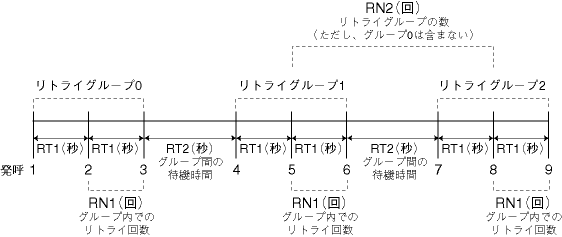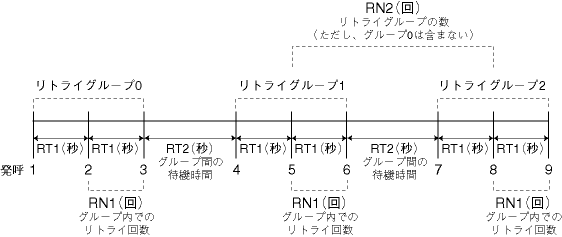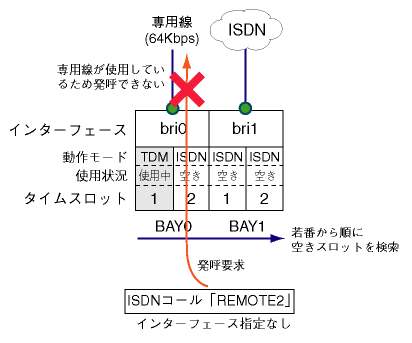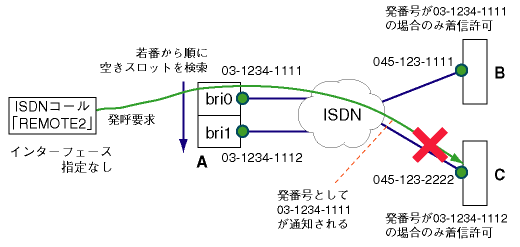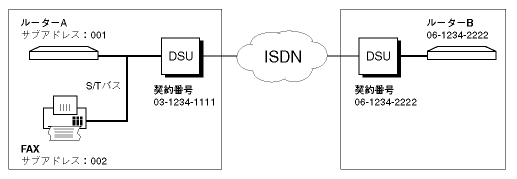[index]
CentreCOM AR410 V2 コマンドリファレンス 2.6
ISDN/概要・基本設定
- 基本設定
- 物理インターフェース
- ISDNコール(接続先情報)の作成
- データリンク層とのインターフェース
- 詳細設定
- 同時発呼時の調停
- 自動リトライ
- ISDNと専用線を併用する場合の注意
- ISDN回線を2本使用する場合の注意
- コールプライオリティーとコールバンピング機能
- ISDNコールログ
- ISDNコールバック
- ISDN S/Tバスに複数の機器を接続している場合
- Dチャンネル共有機能
- スロット型インターフェース番号
- 着信設定(着信呼の識別と認証)
- 着呼までの流れ
- 呼の識別・認証に使う情報の設定
- 発呼時に送信する情報(OUT...パラメーター)
- 着信呼の識別に使う情報(SEARCH...パラメーター)
- 着信呼の認証に使う情報(CHECK...パラメーター:オプション)
ここでは、BRI、PRIの各インターフェースを使って、ISDN回線に接続するための方法について解説します。
ISDN網との接続には、BRIインターフェースかPRIインターフェースを使います。これらのインターフェースはデフォルトでISDNモードに設定されているため、特に設定を行うことなく使用できます。
本製品では、接続先の情報をISDNコールとして定義することにより、上位のデータリンク層モジュールからISDNコールを物理回線として使用できるようになります。
「ISDNコール」は、ISDNにおける接続先登録情報です。この情報は、ISDN網経由で相手先に発信接続するとき、および、ISDN網経由で接続を受け入れるときに使用されます。ISDN経由で発信・着信を行うためには、必ずISDNコールを定義する必要があります。
ISDNコールは、ADD ISDN CALLコマンドで定義します。作成したISDNコールは、指定した相手との間に張られる呼(コール)を示すもので、専用線接続におけるTDMグループやSYNインターフェース、LAN接続におけるETHインターフェースと同様、物理インターフェースとして扱われます。したがって、PPPインターフェースを作成するときに、下位回線としてISDNコール名を指定することができます。
■ ISDNコールを定義するには、ADD ISDN CALLコマンドを使います。CALLパラメーターには任意の名前を、NUMBERパラメーターには相手の電話番号を、PRECEDENCEパラメーターには両側から同時に通信が開始された場合に発呼(OUT)、着呼(IN)のどちらを優先するかを指定します。以上3つのパラメーターは必須で省略できません。
ADD ISDN CALL=office NUMBER=0312342345 PRECEDENCE=OUT SEARCHCLI=ON ↓
「SEARCHCLI=ON」は着信時の動作設定で、NUMBERで指定した相手から着信したときのみ応答することを示します。ISPにダイヤルアップするときのように、着信の必要がない場合はこの設定は必要ありません。次のように指定できます
ADD ISDN CALL=isp NUMBER=0312345678 PRECEDENCE=OUT ↓
着信条件を指定するパラメーターはほかにもあります。詳しくは「着信設定(着信呼の識別と認証)」をご覧ください。
■ 発呼時に使用するインターフェースは、INTREQパラメーターかINTPREFパラメーターで指定します。INTREQを指定した場合は、発呼時に必ず指定されたインターフェースを使おうとします。該当インターフェースに空きチャンネルがなかった場合は、発呼に失敗します。一方、INTPREFパラメーターは優先的に使用するインターフェースを指定するものです。発呼時には、最初にINTPREFで指定したインターフェースで空きチャンネルを探し、空きがないときは他のインターフェースを探します。
ADD ISDN CALL=office NUMBER=0312342345 PRECEDENCE=OUT INTREQ=bri0 SEARCHCLI=ON ↓
Note
- ISDNコールを定義するときは、特に理由がない限り、INTREQパラメーターで発呼用インターフェースを明示的に指定してください。詳しくは、「ISDNと専用線を併用する場合の注意」、「ISDN回線を2本使用する場合の注意」をご覧ください。
ISDNコールは、上位モジュール(データリンク層)からは指定した接続相手との間に張られた物理回線(インターフェース)として扱われます。
ISDN回線(ISDNコール)上で使用できるデータリンク層プロトコルはPPP(Point-to-Point Protocol)の1種類のみです。
■ ISDNコール「office」上にPPPインターフェース「0」を作成するには次のようにします。CREATE PPPコマンドのOVERパラメーターに「ISDN-callname」の形式でコール名を指定してください。「ISDN-」はISDNコールであることを示す固定文字列、「callname」はコール名です。
CREATE PPP=0 OVER=ISDN-office IDLE=ON ↓
通信相手と同時に発呼しようとした場合は、ISDNコールのPRECEDENCEパラメーターの設定によって、着信・発信のどちらを優先するかが決まります。ISDNコールを定義するときは、次に示すように、必ず一方をINにもう一方をOUTに設定してください。
ルーターA
ADD ISDN CALL=CallToA NUMBER=0612342222 PRECEDENCE=OUT INTREQ=bri0 SEARCHCLI=ON ↓
ルーターB
ADD ISDN CALL=CallToB NUMBER=0312341111 PRECEDENCE=IN INTREQ=bri0 SEARCHCLI=ON ↓
発信接続に失敗した場合、あらかじめ指定した回数再接続を試みるよう設定することもできます。これはISDNコールのRN1(グループ内でのリトライ回数)、RN2(初回をのぞく追加のリトライグループ数)、RT1(グループ内でのリトライ間隔)、RT2(リトライグループ間の間隔)パラメーターで設定します。デフォルトはリトライなしです。
リトライは、次の順序で行われます。
- 初回の接続を試みる。
- 接続できなかった場合、RT1(秒)間隔でRN1回までリトライする。
- RN1回リトライしても接続できなかった場合は、RT2(秒)待機した後、再び手順1〜2をRN2回まで繰り返す。
- それでも接続できない場合、ALTNUMBERパラメーターが指定されていれば、1回だけALTNUMBERに発呼し、それでも失敗した場合はリトライをあきらめる。ただし、KEEPUPパラメーターにYESが設定されている場合は、接続できるまで手順1〜4を繰り返し実行する。
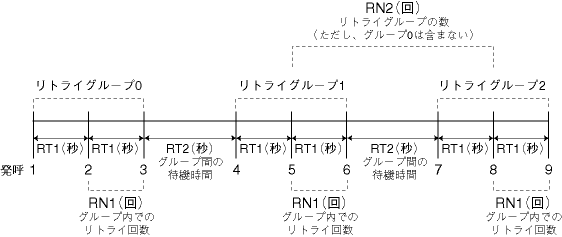
一方のWANインターフェースでISDN回線を使用し、もう一方で専用線(またはフレームリレー)を使用する場合、次の点に注意してください。
■ ISDNの接続先を登録する際に、発呼に使用するインターフェースを明示的に指定してください(ADD ISDN CALLコマンドのINTREQパラメーター)。次の例では、ISDNコール「TOOS」の発呼時にbri1を使用するよう指定しています。
ADD ISDN CALL=TOOS NUM=0312341111 PREC=OUT INTREQ=bri1 ↓
■ BRI、PRIインターフェースで専用線に接続するときは、回線速度にかかわらず、使用するインターフェースの全スロットをTDMモードに変更してください(SET BRIコマンド/SET PRIコマンドのTDMSLOTSパラメーター)。次の例では、bri0の全スロット(1と2)をTDMモードに変更しています(BRI/PRIインターフェースの各スロットはデフォルトでISDNモードに設定されています)。
SET BRI=0 MODE=TDM ACTIVATION=ALWAYS TDMSLOTS=1-2 ↓
PRIの場合は、次のようにします。
SET PRI=0 MODE=TDM TDMSLOTS=1-24 ↓
■ 次に、具体的な例を挙げて説明します。
- BRIインターフェースカードを2つ装着(BAY 1=bri0、BAY 2=bri1)
- bri0は専用線64Kbpsに使用、bri1はISDN接続に使用する
この場合、次のような設定を行うとISDNでの接続ができなくなる可能性があります。
SET BRI=0 MODE=TDM ACTIVATION=ALWAYS TDMSLOTS=1
CREATE TDM GROUP=REMOTE1 INT=bri0 SLOTS=1
ADD ISDN CALL=REMOTE2 NUM=0312341111 PREC=OUT SEARCHCLI=ON
CREATE PPP=1 OVER=TDM-REMOTE1
CREATE PPP=2 IDLE=60 OVER=ISDN-REMOTE2
|
ISDN接続先登録コマンド(ADD ISDN CALLコマンド)は、デフォルトでは発呼に使用するインターフェースを特定しません。発呼時には、若い番号を持つインターフェースベイから順にISDNモードの空きスロットを探してゆき、最初に見つかったスロットを使用して発呼を試みます。
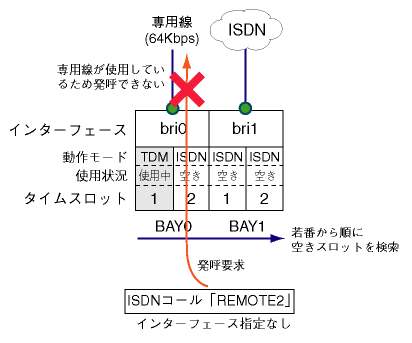
また,専用線接続時に使うインターフェース動作設定コマンド(SET BRIコマンド/SET PRIコマンド)は、インターフェース全体の動作種別(ISDN/専用線)を設定するのではなく、スロット単位で動作種別を設定します。
インターフェースの各スロットは、デフォルトでISDNモードに設定されているため、さきほどの設定例(TDMSLOTS=1)では、bri0のスロット2はISDNモードのままとなります。そのため、ISDNの発呼時にはこのスロットが使用されますが、bri0はすでに専用線接続に使用されているため、接続に失敗してしまいます。
このような問題を避けるため、専用線を使用するときは、回線速度にかかわらず、SET BRI/SET PRIコマンドのTDMSLOTSオプションで、使用するインターフェースのすべてのスロットをTDM(専用線)モードに設定してください。
具体的には、BRIインターフェース使用時はTDMSLOTS=1-2を、PRIインターフェース使用時にはTDMSLOTS=1-24を指定してください。
また、ISDN接続先を登録する場合も、ADD ISDN CALLコマンドのINTREQオプションで、使用するインターフェースを明示的に指定してください。
次に先ほどの設定例を正しく書き換えたものを示します。
SET BRI=0 MODE=TDM ACT=ALWAYS TDMSLOTS=1-2
CREATE TDM GROUP=REMOTE1 INT=bri0 SLOTS=1
ADD ISDN CALL=REMOTE2 NUM=0312341111 PREC=OUT SEARCHCLI=ON INTREQ=bri1
CREATE PPP=1 OVER=TDM-REMOTE1
CREATE PPP=2 IDLE=60 OVER=ISDN-REMOTE2
|
ISDN回線を2回線使用する場合は、ISDNレベルの着信呼識別情報に食い違いが生じないよう留意してください。次に、具体的な例を挙げて説明します。
- 発信側(A)はBRIインターフェースカードを2つ装着(BAY 1=bri0、BAY 2=bri1)
- 着信側(B、C)は発信者番号により応答する着信呼を選択する。
この場合、次のような設定を行うとISDNでの接続ができなくなる可能性があります。
発信側(A)
ADD ISDN CALL=REMOTE1 NUM=0451231111 PREC=OUT SEARCHCLI=ON
ADD ISDN CALL=REMOTE2 NUM=0451232222 PREC=OUT SEARCHCLI=ON
CREATE PPP=1 OVER=ISDN-REMOTE1
CREATE PPP=2 OVER=ISDN-REMOTE2
|
着信側(B)
ADD ISDN CALL=REMOTE1 NUM=0312341111 PREC=IN SEARCHCLI=ON
CREATE PPP=0 OVER=ISDN-REMOTE1
|
着信側(C)
ADD ISDN CALL=REMOTE2 NUM=0312341112 PREC=IN SEARCHCLI=ON
CREATE PPP=0 OVER=ISDN-REMOTE2
|
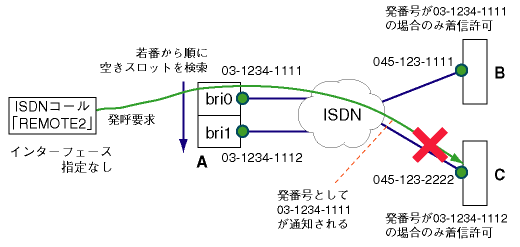
ISDNの発呼時には、番号の若いインターフェースから順に空きスロットを探して発呼するため、2回線とも未使用の状態でREMOTE2の発呼要求が発生すると、BRI0(ベイ0)を使用して発呼します。すると、着信側(C)には、ISDN網から発番号「0312341111」が通知されるため、認証失敗で着呼が許可されず接続できません。
このような問題を避けるため、相手側で発信者番号(SEARCHCLI=ON)やサブアドレス(SEARCHSUB=ON)による着信呼識別を利用している場合は、ADD ISDN CALLコマンドにINTREQパラメーターを指定し、発呼時に使用するインターフェースを明示的に指定してください。次に先ほどの例を正しく書き換えたものを示します(発信側のみ)。
ADD ISDN CALL=REMOTE1 NUM=0451231111 PREC=OUT SEARCHCLI=ON INTREQ=bri0
ADD ISDN CALL=REMOTE2 NUM=0451232222 PREC=OUT SEARCHCLI=ON INTREQ=bri1
CREATE PPP=1 OVER=ISDN-REMOTE1
CREATE PPP=2 OVER=ISDN-REMOTE2
|
コールプライオリティ機能とコールバンピング機能は、ISDNインターフェース上のBチャンネルがすべて使用されているときに、外部からの着呼要求または外部への発呼要求が発生した場合、コール(呼)ごとに設定された優先度(PRIORITY)に基づいて、すでに確立されている通信を切断し、後から発生した着呼/発呼要求を優先させる機能です。
Note
- 着信についてこの機能をご利用になるためには、ご契約のISDN回線で「通信中着信通知」の申し込みが必要です。
データ通信(data call)の優先度は、ADD ISDN CALLコマンド、SET ISDN CALLコマンドのPRIORITYパラメーターで設定します。PRIORITYの範囲は0〜99で、値が大きいほど優先度が高くなります。データ通信のデフォルトの優先度は50です。
空きチャンネルがないときに、すでに確立しているデータ通信よりも優先度の高いデータ通信の発呼/着呼の要求が発生した場合は、優先度の低い呼が切断されます。
コールログ機能を使用すると、ISDN経由の通信記録を専用のログに残すことができます。コールログは、ルーターのシステムログとは別に管理されます。
■ ISDNコールログを有効にするには、ENABLE ISDN LOGコマンドを実行します。デフォルトは有効です。無効にするには、DISABLE ISDN LOGコマンドを実行します。
ENABLE ISDN LOG ↓
DISABLE ISDN LOG ↓
■ 保存するログエントリーの最大数は、SET ISDN LOGコマンドのLENGTHパラメーターで指定します。デフォルトは25です。ログエントリー数が最大数を超えた場合、状態がCLEAREDのエントリーのうち最も古いものが削除されます。ただし、該当するエントリーがない場合、ログエントリー数が最大値を超えることもありえます。
■ コールログをコンソール(非同期)ポートにも出力させたい場合は、SET ISDN LOGコマンドのPORTパラメーターで非同期ポートの番号を指定します。デフォルトはNONE(出力しない)です。メッセージは、ログエントリーがCLEARED状態になったときに出力されます。
■ コールログを見るにはSHOW ISDN LOGコマンドを実行します。
■ ISDNコールに関する情報は、ルーターのシステムログにも送られます。記録される情報は次のとおりです。
- ISDNコールの起動(発呼、着呼)
- ISDNコールの切断(正常終了)
- ISDNコールの切断(異常終了)
コールバックとは、かかってきた電話をかけなおす機能です。コールバック機能をうまく使用すれば、地域によって料金体系が異なるところで常に安い側がコールバックを行ったり、料金の請求先をまとめたり、より強力なセキュリティー体制を築いたりすることができます。
本製品は、「ISDNコールバック」と「PPPコールバック」の2通りのコールバック方式をサポートしています。
- ISDNコールバックでは、ISDNのDチャンネルレベルで相手を識別しコールバックします。Bチャンネルまでは接続されないため、最初に発呼した側には課金されません。
- PPPコールバックは、PPPでCHAPまたはPAP認証を行うため(設定により、ISDNのDチャンネルレベルでの認証も併用可)、最初に発呼した側にも通信料金がかかります。
ここでは、ISDNコールバックの使用方法について解説します。PPPコールバックについては、「PPP」の章をご覧ください。
■ コールバック(かけなおす)する側は、ISDNコールの定義でCALLBACK=ONを指定します。
ADD ISDN CALL=TOOS NUMBER=0612342222 PREC=IN INTREQ=bri0 SEARCHCLI=ON ↓
SET ISDN CALL=TOOS CALLBACK=ON ↓
■ コールバック時に最初の呼を切断してからコールバックするまでの待機時間は、CBDELAYパラメーターで調整できます。時間は0.1秒単位で指定します。デフォルトは41(4.1秒)です。
SET ISDN CALL=TOOS CBDELAY=50 ↓
■ ISDNコールバックを無効にするには、CALLBACKパラメーターにOFFを指定します。
SET ISDN CALL=TOOS CALLBACK=OFF ↓
■ ISDNコールバックを要求する側には、特別な設定は必要ありません。
| ISDN S/Tバスに複数の機器を接続している場合 |
ISDN S/Tバス上に複数の機器を接続している場合は、個々のISDN機器にサブアドレスを設定し、着信呼がどの機器に宛てられたものかを識別できるようにする必要があります。本製品のサブアドレスは、SET Q931コマンドのSUB1パラメーターで設定します。
■ たとえば次の図では、ルーターAにサブアドレス「001」を、FAXに「002」を割り振っています。この場合、ルーターAの設定は次のようにして行います。
SET Q931=0 SUB1=001 NOSUB=REJECT ↓
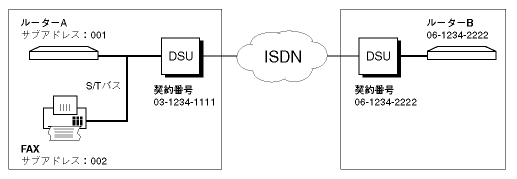
これにより、本製品は着サブアドレスが「001」の呼に対してのみ何らかの処理(識別、認証など)を開始するようになります。「NOSUB=REJECT」ではなく「NOSUB=ACCEPT」(デフォルト)を指定すると、サブアドレスのない着信呼に対しては無条件で処理を開始します。
S/Tバス上のISDN機器が本製品だけの場合は、SET Q931コマンドを実行する必要はありません。
Dチャンネル共有機能は、23B+D構成のPRIインターフェースにおいて、64KbpsのDチャンネルをBチャンネルとして扱い、24Bの構成で使用するための機能です。この場合、制御用のDチャンネルがなくなるため、もう一本BRIかPRIの回線を用意してDチャンネルを共有するよう設定します。
以下、Dチャンネル共有の設定方法を示します。ここでは、BRIとPRIを1つずつ持っているものと仮定します。スロット型インターフェース番号(後述)は、bri0が0、pri0が1とします。
- 共有DチャンネルをBRIインターフェース上に設定する場合は、BRIをTEI非自動割り当てモードに変更し、TEI値を0に設定する必要があります。これには、SET LAPDコマンドのMODEパラメーターとADD LAPD TEIコマンドを使います。
SET LAPD=0 MODE=NONAUTOMATIC ↓
ADD LAPD=0 TEI=0 ↓
Note
- この手順は、共有DチャンネルをPRIインターフェース上に設定するときは必要ありません。
- 共有Dチャンネルを置くインターフェースをSET LAPDコマンドのNASMODEパラメーターでマスター(MASTER)に設定します。また、もう一方のインターフェース(ここではpri0)をスレーブ(SLAVE)に設定し、NASMASTERパラメーターでマスター側のインターフェースを指定します。
SET LAPD=0 NASMODE=MASTER ↓
SET LAPD=1 NASMODE=SLAVE NASMASTER=bri0 ↓
- 最後にSET Q931コマンドを使って、Q.931レベルのインターフェース識別子を設定します。指定する値は通信事業者にご確認ください。
SET Q931=bri0 INTID=00 ↓
SET Q931=pri0 INTID=01 ↓
■ Dチャンネル共有機能の設定を確認するには、SHOW LAPDコマンドを使います。
Note
- Dチャンネル共有機能を使用するときは、INTREQ、INTPREFパラメーターを使わないでください。
スロット型インターフェース番号
BRIインターフェースとPRIインターフェースは、64Kbps相当のタイムスロットでチャンネルを構成しているため、スロット型インターフェースと呼ばれます。
ISDNモード(デフォルト)で動作しているBRI、PRIインターフェースには、それぞれ1つずつLAPDモジュールとQ931モジュールのインターフェースが用意されます。これらのインターフェースは、スロット型インターフェース番号と呼ばれるインデックス値によって識別されます。
たとえば、本体内蔵のBRIインターフェースとPICベイ装着のPRIインターフェースがある場合、BRIインターフェース「0」がLAPD/Q931インターフェース「0」になり、PRIインターフェース「0」がLAPD/Q931インターフェース「1」となります。
TDM(専用線)モードではLAPDモジュールやQ931モジュールを使用しないため、BRI、PRIインターフェースをTDMモードに変更すると、LAPD、Q931の各インターフェースは削除されます。
このとき、他のLAPD、Q931インターフェースの番号は変更されません。たとえば、先ほどの例で挙げたBRI0がTDMモードに変更された場合であっても、PRI0のスロット型インターフェース番号は1のままとなります。
ISDNでは、発呼時に「呼設定メッセージ」が接続先へ送られます。呼設定メッセージにはさまざまな情報を入れるフィールド(Q.931では情報要素またはIE = Information Elementと呼びます)があり、本製品はそのうち以下のフィールドを使って情報を送ることができます。接続先では、これらの情報をもとに着信呼を識別し、呼に応答するかどうかを決定できます。
- 着サブアドレス
- ユーザー間情報
- 発番号(発信者番号)
どの着信呼を受け付け、どの着信呼を拒否するかといった条件は、基本的にADD ISDN CALLコマンド/SET ISDN CALLコマンドの各種パラメーターを使って設定します。
本製品が着信呼に応答するまでの流れを示します。
- 着サブアドレスとルーター自身のサブアドレスの比較
ISDN S/Tバスに複数の機器が接続されている場合など、SET Q931コマンドでルーター自身にサブアドレスが設定されている場合は、着信呼の着サブアドレスがSET Q931コマンドのSUB1パラメーターで設定されたサブアドレスと一致する場合にのみ手順2に進み、それ以外の場合は他の機器に宛てた呼とみなして応答しません。SET Q931コマンドでサブアドレスが設定されていない場合は無条件で手順2に進みます。
- SEARCH...パラメーターによる着信用ISDNコールの選択(SEARCHフェーズ)
着サブアドレスまたはユーザー間情報が送られてくるか、発信者番号が通知されてきた場合は、送られてきた情報とADD ISDN CALLコマンド/SET ISDN CALLコマンドのSEARCHSUB、SEARCHUSER、SEARCHCLIパラメーターで指定された情報を比較し、一致するISDNコール定義が見つかればそれを選択して手順3に進みます。
条件にマッチするISDNコールが見つからなかった場合は、ADD ISDN CALLコマンド/SET ISDN CALLコマンドで「INANY=ON」が指定されているコール名を探し、見つかった場合はそれを選択します。見つからなかった場合は、着信呼を拒否して切断します。
- CHECK...パラメーターによる呼認証(CHECKフェーズ)
手順2で選択したISDNコール定義にCHECKSUB、CHECKUSER、CHECKCLIのいずれかのパラメーターが指定されていた場合は、さらに呼の認証(チェック)を行います。すべての認証にパスして初めて着信呼に応答します。CHECK...パラメーターが指定されていなかった場合は無条件で応答します。いずれかの認証に失敗した場合は、着信呼を拒否して切断します。
発呼時に送信する情報(OUT...パラメーター)
発呼時に接続先へ送信する情報は、ADD ISDN CALLコマンド/SET ISDN CALLコマンドのOUTSUB、OUTUSER、OUTCLI、SUBADDRESSパラメーターで指定します。これらの情報は、接続先で着信判断を行うときに使用されます。
■ サブアドレスを送るにはOUTSUBパラメーターを使います。「OUTSUB=LOCAL」を指定すると、自コール名(CALLパラメーター)が相手に送られます。発呼時に着サブアドレスとして自コール名「TOOS」を送るには、次のようにします。
SET ISDN CALL=TOOS OUTSUB=LOCAL ↓
また、「OUTSUB=REMOTE」を指定すると、REMOTECALLパラメーターで指定した文字列が相手先に送られます。サブアドレスとしてコール名以外の文字列を送る場合はこちらを使用してください。着サブアドレスとして「001」を送るには、次のようにします。
SET ISDN CALL=TOOS OUTSUB=REMOTE REMOTECALL=001 ↓
■ また、数字のみのサブアドレスを送信したいときは、SUBADDRESSパラメーターを使うこともできます。SUBADDRESSパラメーターを指定した場合、OUTSUBパラメーターは無効となります。
SET ISDN CALL=TOOS SUBADDRESS=001 ↓
着信呼の識別に使う情報(SEARCH...パラメーター)
本製品は、外部から着信があった場合、ADD ISDN CALLコマンド/SET ISDN CALLコマンドで指定したSEARCHSUB、SEARCHUSER、SEARCHCLI、INANYの各パラメーターの値をもとに、どのISDNコールを使って応答すればよいかを判断します。
■ ADD ISDN CALLコマンド/SET ISDN CALLコマンドで「SEARCHSUB=LOCAL」を指定すると、コール名と同じサブアドレスの着信呼にのみ応答します。「SEARCHSUB=REMOTE」を指定した場合は、リモートコール名と同じサブアドレスの着信呼にのみ応答します。
次の例では、着信呼のサブアドレスが「TOOS」と一致する場合にのみ応答します。
SET ISDN CALL=TOOS SEARCHSUB=LOCAL ↓
■ 「SEARCHUSER=LOCAL」を指定すると、ユーザー間情報が自分のコール名と一致する呼にのみ応答します。「SEARCHUSER=REMOTE」を指定すると、ユーザー間情報が自分のリモートコール名と一致する着信呼にのみ応答します。
次の例では、ユーザー間情報として「TOOS」が送られてきた場合(発呼側のコール名が「TOOS」で「OUTUSER=LOCAL」が指定されていたような場合)にのみ応答します。
SET ISDN CALL=TOOS SEARCHUSER=LOCAL ↓
■ 「SEARCHCLI=ON」を指定すると、発信者番号が接続先番号(NUMBERパラメーターで指定)と一致する場合にのみ応答させることもできます。
次の例では、発信者番号が「06-1234-2222」の着信呼にのみ応答します。
ADD ISDN CALL=TOOS NUMBER=0612342222 PREC=OUT SEARCHCLI=ON ↓
■ また、発番号リストを使うと、あらかじめリストに登録しておいた番号からの着信呼にのみ応答させることができます。リストは100個まで作成できます。
発番号リストの作成はADD ISDN CLILISTコマンドで行います。CLILISTパラメーターには任意のリスト番号(0〜99)、NUMBERには登録する番号を指定します。
ADD ISDN CLILIST=0 NUMBER=0312341111 ↓
ADD ISDN CLILIST=0 NUMBER=0323452222 ↓
この例では、03-1234-1111と03-2345-2222の2つの番号を発番号リスト「0」番に登録しています。
リスト「0」番に登録されている番号からの着信呼にのみ応答するようISDNコール「TOOS」を設定するには、次のようにします。発番号リストを使うときは、SEARCHCLIパラメーターに発番号リストの番号を指定します。
SET ISDN CALL=TOOS SEARCHCLI=0 ↓
■ ダイヤルアップサーバーのように不特定多数からの着信を受け付ける場合は「INANY=ON」を指定します。
SET ISDN CALL=TOOS INANY=ON ↓
Note
- 複数のISDNコールに「INANY=ON」を指定することはできません(デフォルトは「INANY=OFF」)。また、SEARCH...パラメーターによる着信識別を行う場合は「INANY=ON」を指定しないでください。
■ ここまでの条件に一致しなかった着信呼は拒否(切断)されます。ISDNの着信を許可する場合は、少なくともSEARCHSUB、SEARCHUSER、SEARCHCLI=ON、INANY=ONのいずれか1つを指定してください。これらを指定しなかった場合、そのISDNコールは発呼専用になります。一方、発信専用でかまわない場合は、これらのパラメーターを指定しないでください。たとえば、ISP接続用のISDNコールは次のようになります。
ADD ISDN CALL=isp NUMBER=0312345678 PREC=OUT INTREQ=bri0 ↓
着信呼の認証に使う情報(CHECK...パラメーター:オプション)
CHECKSUB、CHECKUSER、CHECKCLIの各パラメーターを指定することにより、SEARCHフェーズで条件に一致したISDNコールに対して、さらに追加のチェック(認証)を行うこともできます。CHECK...パラメーターが指定されていない場合は、この時点で着信呼に応答します。
■ CHECKSUB、CHECKUSERパラメーターの働きは、基本的にSEARCHSUB、SEARCHUSERパラメーターと同じです。LOCALが指定されていればコール名(CALL)と、REMOTEが指定されていればリモートコール名(REMOTECALL)と、送られてきた情報(サブアドレスやユーザー間情報)を突き合わせます。
■ CHECKCLIパラメーターを使用すると、あらかじめ発番号リストに登録しておいた番号からの着信呼にのみ応答させることができます。リストは100個まで作成できます。
発番号リストの作成はADD ISDN CLILISTコマンドで行います。CLILISTパラメーターには任意のリスト番号(0〜99)、NUMBERには登録する番号を指定します。
ADD ISDN CLILIST=0 NUMBER=0312341111 ↓
ADD ISDN CLILIST=0 NUMBER=0323452222 ↓
この例では、03-1234-1111と03-2345-2222の2つの番号を発番号リスト「0」番に登録しています。
リスト「0」番に登録されている番号からの着信呼にのみ応答するようISDNコール「TOOS」を設定するには、次のようにします。
SET ISDN CALL=TOOS INANY=ON CHECKCLI=REQUIRED CLILIST=0 ↓
(C) 2002 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社
PN: J613-M3048-01 Rev.M