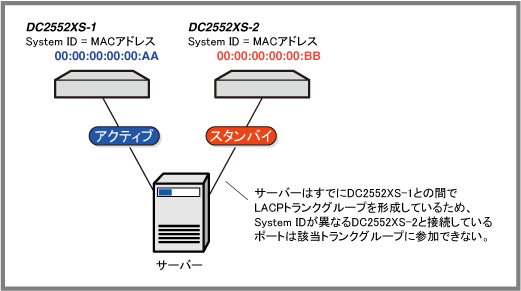
[index] AT-DC2552XS コマンドリファレンス 5.4.4
Note - IEEE 802.3adでは、論理的に1ポートと見なされるポートの束を「リンクアグリゲーショングループ(LAG)」と呼びますが、本マニュアルでは、一般的な意味での「リンクアグリゲーショングループ」を「トランクグループ」と表記することにします。
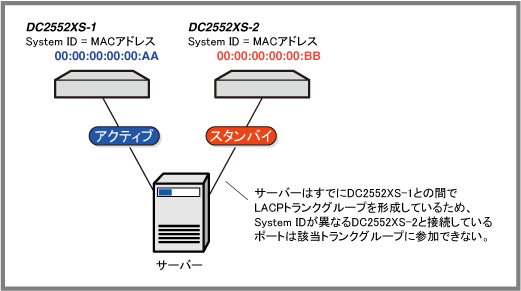
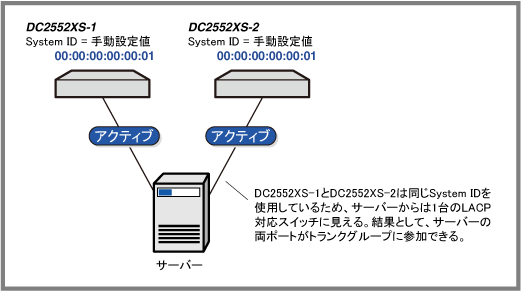
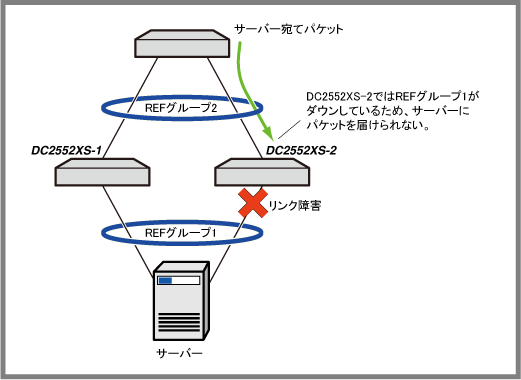
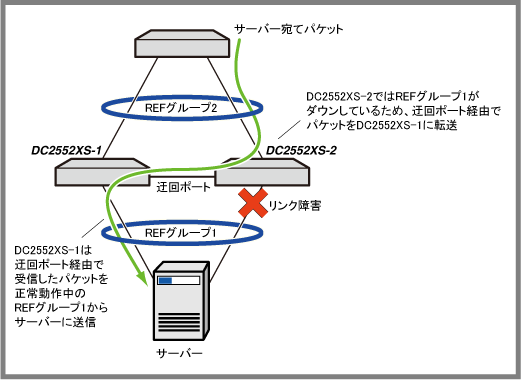
| DC2552XS-1、DC2552XS-2とも、受信したサーバー宛てのパケットを自身のREFグループ1へ転送する。迂回経路は使用しない | ||
| DC2552XS-1は受信したサーバー宛てのパケットを迂回経路に転送する。DC2552XS-2は迂回経路から受信したパケットを自身のREFグループ1に転送する | ||
| DC2552XS-2は受信したサーバー宛てのパケットを迂回経路に転送する。DC2552XS-1は迂回経路から受信したパケットを自身のREFグループ1に転送する | ||
| DC2552XS-1、DC2552XS-2ともREFグループ1がダウンしており、サーバーへの経路が存在しないため、迂回経路は使用しない | ||
Note - システムIDは、別のREF対応装置ペアや他のLACP対応装置と重複しないよう設定する必要があります。他の装置または装置ペアと同じシステムIDを設定すると、REFグループを正常に構成できません。
Note - 共用迂回ポートであっても、REFグループと同じ数だけ迂回ポートを設定しておけば基本的に迂回ポートが足りなくなることはありません。
Note - 複数のREFグループで専用迂回ポートを「共用」することもできますが、その場合は「対象REFグループを限定した共有迂回ポート」になります。
Note - 複数のREFグループで専用迂回ポートを「共用」することもできますが、その場合これらのREFグループは同じVLANに所属している必要があります。専用迂回ポートを共用するREFグループ間で所属VLANに差異があると、一部のVLANは専用迂回ポート経由での通信ができなくなるため注意してください。特に理由がないかぎり、専用迂回ポートは文字通り1つのREFグループ専用に設定してください。
Note - REFグループがダウンしたときに使われる迂回ポートは、1つのREFグループにつき1ポートだけです。
Note - 迂回ポートとして設定されたポートではMACアドレスを学習しません。
Note - REFグループがダウンしたときに使われる迂回ポートは、1つのREFグループにつき1ポートだけです。
| IN | 本来なら自装置のREFグループに転送すべきパケットを、迂回経路に転送するための設定を行う |
| OUT | 迂回経路から受信したパケットを、自装置のREFグループに転送するための設定を行う |
| Down → Up | Down | 「OUT」実行 | 「IN」実行 |
| Up → Down | Down | 「OUT」解除 | 「IN」解除 |
| Down → Up | Up | 「IN」解除 | 「OUT」解除 |
| Up → Down | Up | 「IN」実行 | 「OUT」実行 |
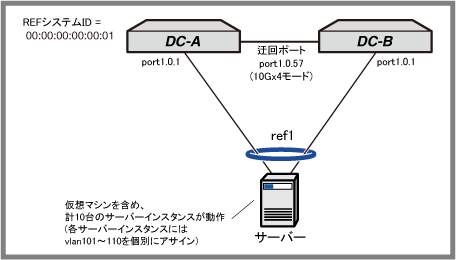
awplus# erase startup-config ↓ awplus# reload ↓ |
awplus> enable ↓ awplus# configure terminal ↓ Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. awplus(config)# no stack 1 enable ↓ Warning: this will disable the stacking hardware on member-1. Are you sure you want to continue? (y/n): y ↓ |
awplus(config)# end ↓ awplus# copy running-config startup-config ↓ awplus# reload ↓ |
awplus> enable ↓ awplus# configure terminal ↓ Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. awplus(config)# no spanning-tree rstp enable ↓ awplus(config)# no ip igmp snooping ↓ awplus(config)# no ipv6 mld snooping ↓ |
awplus(config)# hostname DC-A ↓ |
awplus(config)# hostname DC-B ↓ |
DC-A(config)# ref system-id 0000.0000.0001 ↓ |
DC-B(config)# ref system-id 0000.0000.0001 ↓ |
DC-A(config)# ref port-number-offset ↓ |
DC-A(config)# vlan database ↓ DC-A(config-vlan)# vlan 101-110 ↓ DC-A(config-vlan)# exit ↓ DC-A(config)# interface port1.0.1 ↓ DC-A(config-if)# switchport mode trunk ↓ DC-A(config-if)# switchport trunk native vlan none ↓ DC-A(config-if)# switchport trunk allowed vlan add 101-110 ↓ DC-A(config-if)# thrash-limiting action none ↓ DC-A(config-if)# exit ↓ |
DC-B(config)# vlan database ↓ DC-B(config-vlan)# vlan 101-110 ↓ DC-B(config-vlan)# exit ↓ DC-B(config)# interface port1.0.1 ↓ DC-B(config-if)# switchport mode trunk ↓ DC-B(config-if)# switchport trunk native vlan none ↓ DC-B(config-if)# switchport trunk allowed vlan add 101-110 ↓ DC-B(config-if)# thrash-limiting action none ↓ DC-B(config-if)# exit ↓ |
DC-A(config)# interface port1.0.1 ↓ DC-A(config-if)# ref-group 1 mode active ↓ |
DC-B(config)# interface port1.0.1 ↓ DC-B(config-if)# ref-group 1 mode active ↓ |
Note - この例では所属ポート(port1.0.1)にVLANの設定をしてからREFグループを作成していますが、手順9と手順10を入れ替え、REFグループを作成してから、REFグループ(ref1)に対してVLANの設定をしてもかまいません。どちらの順序で設定しても、ランニングコンフィグ上、VLAN設定コマンドはREFグループではなく所属ポートに対する設定として表現されます。
DC-A(config)# interface port1.0.57 ↓ DC-A(config-if)# ref bypass-port ↓ |
DC-B(config)# interface port1.0.57 ↓ DC-B(config-if)# ref bypass-port ↓ |
DC-A(config-if)# end ↓ DC-A# copy running-config startup-config ↓ |
DC-B(config-if)# end ↓ DC-B# copy running-config startup-config ↓ |
Note - 迂回ポートの接続には、40GのQSFP+ダイレクトアタッチケーブル(AT-QSFP1CU/3CU)を使用するのが便利です。また、迂回ポート間はQSFP+モジュール(AT-QSFPSR)で接続することもできます。
Note - 迂回ポートは必ず同じポート番号どうしで接続してください。番号の異なるポートどうしを接続すると迂回ポートが正しく作成されず、REFグループがダウンしたときにパケットの迂回転送ができなくなるため注意が必要です。
Note - ファームウェアバージョンアップの手順については、「運用・管理」の「システム」をご覧ください。
(C) 2011 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社
PN: 613-001633 Rev.E