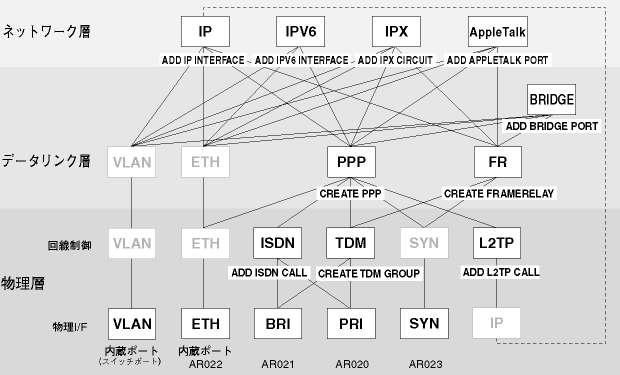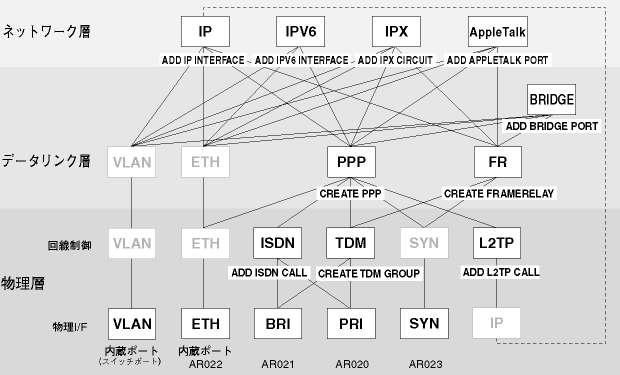[index]
CentreCOM AR410 V2 コマンドリファレンス 2.6
インターフェース/概要・基本設定
- インターフェースの階層構造
- インターフェース名
- 短い名前
- 長い名前
- 物理インターフェース
- VLANインターフェース
- Ethernetインターフェース
- BRIインターフェース
- PRIインターフェース
- 同期シリアルインターフェース
- 回線制御モジュール
- ISDNモジュール
- TDMモジュール
- データリンク層インターフェース
- VLANインターフェース
- Ethernetインターフェース
- PPPインターフェース
- フレームリレーインターフェース
- ネットワーク層インターフェース
- IPインターフェース
- IPv6インターフェース
- IPXインターフェース
- AppleTalkインターフェース
ここでは、本製品が装備する物理インターフェースとその上に作成するデータリンク層インターフェース、ネットワーク層インターフェースの基本的な設定方法について解説します。物理インターフェースとデータリンク層インターフェースの間をとりもつ回線制御モジュールや、インターフェースの階層構造についても解説します。
ルーターの設定は、最下位に位置する物理インターフェースの上にさまざまな論理インターフェースを重ねていく形で行います。次に本製品のインターフェース階層図を示します。
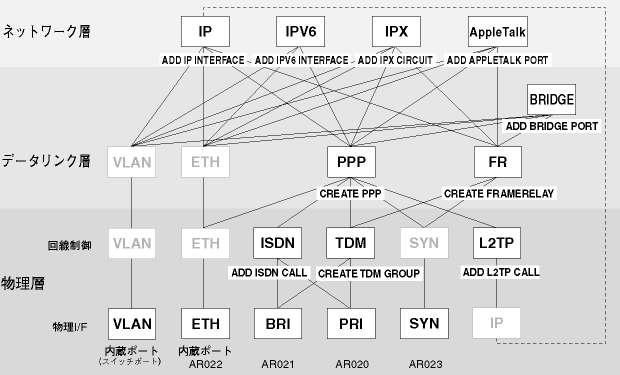
最下層にあるインターフェースが、本体内蔵あるいはPIC(Port Interface Card)モジュールの形で提供される物理インターフェース(ポート)です。本製品では、VLAN(LAN側ポート)、Ethernet(ETH)、BRI、PRI、同期シリアル(SYN)の5種類があります。
その上にあるのが、物理インターフェースに接続されている回線を制御するソフトウェアモジュールです。VLAN、Ethernetの場合は特に設定の必要がないため、明確な形では存在しません。BRI、PRIインターフェースでISDN網に接続するときは発信接続等を担当するISDNモジュールを、専用線やフレームリレー網に接続するときはタイムスロットの処理を行うTDMモジュールを使います。同期シリアルインターフェースの場合は、回線制御が外付けのTA等によって行われるため、この層を担当するモジュールはありません。ここまでがOSIモデルでの物理層に相当すると考えられます。
Note
- 図中の「L2TP」は、IPネットワーク上に仮想的な回線を構築するVPN(Virtual Private Network)用のトンネリングプロトコルです。詳細は「L2TP」の章をご覧ください。
回線制御モジュールの上位にくるのが、OSI参照モデルの第2層にあたるデータリンク層インターフェースモジュールです。本製品ではVLAN、Ethernet、PPP、フレームリレー(FR)の4種類をサポートしています。この層では、単なるビット列をフレームと呼ばれる単位に組み立て、同一回線(データリンク)上での通信を制御します。VLAN、Ethernetインターフェースは物理層とデータリンク層が一体となっているため、特に設定の必要はありません。PPP、フレームリレーの場合は、CREATE PPPコマンド、CREATE FRAMERELAYコマンドで明示的にインターフェースを作成します。このとき、下位インターフェースとして、回線制御モジュールか物理インターフェースを指定します。
データリンク層の上には、第3層にあたるネットワーク層プロトコルのインターフェースモジュールが位置します。本製品ではIP、IPv6、IPX、AppleTalkをサポートしています。ネットワーク層インターフェースは、ADD IP INTERFACEコマンド、ADD IPV6 INTERFACEコマンド、ADD IPX CIRCUITコマンド、ADD APPLETALK PORTコマンドを使って、データリンク層インターフェース上に追加(ADD)する形となります。
Note
- フレームリレー上でのIPv6はサポートしていません。また、同期シリアル(SYN)上のPPPにおけるIPv6もサポートしておりません。
Note
- 図には示していませんが、IP(IPv4)上の仮想的なIPv6インターフェースとして、IPv6 over IPv4トンネルインターフェース(VIRTn)があります。詳細は「IPv6」の章をご覧ください。
ここでは、インターフェースの名前付け規則について解説します。インターフェース名には、「短い名前」と「長い名前」(フルパス名)があります。
短いインターフェース名は、インターフェースの種類を示す略称(ETH、BRIなど)に、インターフェース番号(0、1、2)をつなげた形式で表します。種類を示す略称は次のとおりです。
表 1:短いインターフェース名
| 種別略称 |
例 |
説明 |
| 物理インターフェース |
| VLAN |
vlan1 |
VLANインターフェース(データリンク層と一体) |
| ETH |
eth0 |
Ethernetインターフェース(データリンク層と一体) |
| BRI |
bri0 |
BRIインターフェース |
| PRI |
pri0 |
PRIインターフェース |
| SYN |
syn0 |
同期シリアルインターフェース |
| データリンク層(論理)インターフェース |
| FR |
fr0 |
フレームリレーインターフェース |
| PPP |
ppp1 |
PPPインターフェース |
物理インターフェースの番号は、同じ種類のインターフェース間で重ならないようにシステムが0から順番に割り当てます。割り当て順序は、本体内蔵の固定ポート、拡張ベイ(PICベイ)の順です。PICを使用している場合は、PICの着脱によってインターフェース番号が変更される可能性があります。これが問題になる場合は、後述する「長い名前」を使うことにより、インターフェース名を絶対指定できます。
Note
- VLANインターフェース(VLAN)のインターフェース名は「vlan1」で固定です。
VLANインターフェースとEthernetインターフェースは物理層とデータリンク層が一体になっているため、物理インターフェース名とデータリンク層インターフェース名が同じになります。
Note
- LAN側スイッチポートのグループ構成を変更することはできません。常に全ポートがvlan1所属になります。IPアドレスなど上位層の設定は、個々のスイッチポートではなく、vlan1インターフェースに対して行います。
これに対し、論理的なデータリンク層インターフェース(PPP、FR)のインターフェース番号は、CREATE FRAMERELAYコマンドやCREATE PPPコマンドで作成するときにユーザーが指定した番号になります。番号は有効範囲内で任意に選べますが、通例として0番から順に割り当てます。なお、論理的なデータリンク層インターフェースに長い名前はありません。
物理インターフェースは、PICベイの位置情報を含む長い名前(フルパス名)で指定することもできます。長い名前では、物理インターフェースの位置を絶対指定するため、PICを着脱しても名前が変化しないという利点があります。
フルパス名では、PICベイを「BAYn」の形式で表します。nはPICベイの番号です。たとえば、本製品のPICベイ0は「bay0」のように表現します。
フルパス名は、PICベイ、インターフェースをピリオドで区切って表現します。たとえば、本製品のPICベイ0に装着したAR020は、次のように表します。
本体内蔵のインターフェース名は、短いインターフェース名と同じです。たとえば、本体内蔵のEthernetインターフェースは、次のように表します。
次に長いインターフェース名についてまとめます。ここでは説明のため、PICベイ0にAR020を装着しているものと仮定します。
表 2:長いインターフェース名の例
| 場所 |
短い名前 |
長い名前 |
| 本製品本体のEthernet 0 |
eth0 |
eth0 |
| 本製品のPICベイ0に装着したPRI |
pri0 |
bay0.pri0 |
システムによって認識されているインターフェースの長い名前と短い名前は、SHOW INTERFACEコマンドで確認できます。
コマンドのパラメーターにインターフェース名を指定するときは、短い名前、長い名前のどちらも同じように使えます。
- インターフェース番号だけを取るパラメーター(例:PRI=0)には、長い名前を指定することもできます(例:PRI=bay0.pri0)。
- インターフェース名を取るパラメーター(例:INT=pri0)には、長い名前を指定することもできます(例:INT=bay0.pri0)。
- マルチホーミングしたIPインターフェースを指定するパラメーター(例:INT=eth1-1)には、長い名前を指定することもできます(例:INT=bay0.eth0-1)。
- インターフェースのインデックス番号(ifIndex)を取るパラメーター(例:INT=1)には、長い名前を指定することもできます(例:INT=bay0.eth0)。
コマンド入力時に短いインターフェース名を指定した場合であっても、CREATE CONFIGコマンドを実行すると、長いインターフェース名で設定が保存されます。
本製品で使用可能な物理インターフェースは以下の5種類です。
- VLANインターフェース(vlan)
- Ethernetインターフェース(eth)
- BRIインターフェース(bri)
- PRIインターフェース(pri)
- 同期シリアルインターフェース(syn)
物理インターフェースは、本製品と各種回線を接続するための接続口(ポート)です。ソフトウェア的には、ポートを制御するドライバーなどを含んでおり、上位の回線制御モジュールやデータリンク層インターフェースにサービスを提供します。
Note
- 本製品は、このほかに非同期シリアルインターフェース(asyn)1ポートを装備していますが、同ポートはコンソール接続専用となっております。モデムなどを接続してのネットワーク接続はサポートしておりません。
以下、インターフェースの種類ごとに設定方法を説明します。
VLAN(LAN側)インターフェースは、本製品をEthernet LAN(100BASE-TX、10BASE-T)に接続するためのインターフェースです。インターフェース名は「vlan1」(固定)です。
VLANインターフェースは4ポートのEthernetスイッチになっており、複数のコンピューターを接続することができます。vlan1インターフェースは、Ethernetと同じように物理層からデータリンク層までが一体となったインターフェースであり、上位層の設定においては、eth0、ppp0、fr0などと同等のデータリンク層インターフェースとして扱うことができます。
Note
- LAN側スイッチポートのグループ構成を変更することはできません。常に全ポートがvlan1所属になります。IPアドレスなど上位層の設定は、個々のスイッチポートではなく、vlan1インターフェースに対して行います。
VLAN(vlan1)インターフェースを使用するにあたって、特に設定しなくてはならない項目はありません。Ethernetインターフェースと同様、直接上位にレイヤー3インターフェース(IP、IPv6、IPX、AppleTalk)を作成することができます。たとえば、vlan1上にIPインターフェースを作成するには、次のようにします。
ADD IP INTERFACE=vlan1 IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0 ↓
Note
- VLANインターフェースは、Ethernetインターフェースとほぼ同等ですが、以下の点は異なります。ご注意ください。 (1) VLANインターフェース上ではPPPoEを使用できません。 (2) VLANインターフェース上ではトリガー機能を使用できません。
■ 内蔵Ethernetスイッチの情報(MACアドレスなど)は、SHOW SWITCHコマンドで確認できます。
■ 内蔵Ethernetスイッチの各種統計カウンターは、SHOW SWITCH COUNTERコマンドで確認できます。
■ LAN側スイッチポートの情報は、SHOW SWITCH PORTコマンドで確認できます。
Ethernetインターフェースは、本製品をEthernet LAN(100BASE-TX、10BASE-T、AUI)に接続するためのインターフェースです。インターフェース名は「ETHn」の形式で表します。
Ethernetインターフェースを使用するにあたって、特に設定しなくてはならない項目はありません。Ethernetは物理層からデータリンク層(MAC副層)までをカバーする規格であるため、直接上位にレイヤー3インターフェース(IP、IPv6、IPX、AppleTalk)を作成することができます。たとえば、eth0上にIPインターフェースを作成するには、次のようにします。
ADD IP INTERFACE=eth0 IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0 ↓
また、Ethernetインターフェースは、LANとの接続に使用するほか、PPPoE(PPP over Ethernet, RFC2516)によるWAN接続にも使用できます。PPPoEはEthernet上でPPP(Point-to-Point Protocol, RFC1661)を使用するためのプロトコルで、xDSLなどのブロードバンドサービスで広く使用されています。
PPPoEインターフェースを作成する場合も、Ethernetインターフェースに対して特別な設定は必要ありません。CREATE PPPコマンドでPPPインターフェースを作成するときに、OVERパラメーターに「Ethernetインターフェース名」+ハイフン(-)+「PPPoEサービス名」を指定してください。ISPからPPPoEサービス名が指定されていない場合は、キーワードANYか任意の文字列を指定できます。たとえば、eth0上にPPPoEインターフェースを作成する場合、サービス名が「fuga」ならば「OVER=eth0-fuga」のように指定します。サービス名の指定がない場合は「OVER=eth0-any」とするか、任意の文字列を指定します。
CREATE PPP=0 OVER=eth0-any ↓
■ Ethernetインターフェース上で動作しているソフトウェアモジュール、プロトコル、フレームタイプ等を確認するには、SHOW ETH CONFIGURATIONコマンドを使います。
SHOW ETH CONFIGURATION ↓
SHOW ETH=0 CONFIGURATION ↓
■ EthernetインターフェースのMACアドレスは、SHOW ETH MACADDRESSコマンドで確認できます。
SHOW ETH MACADDRESS ↓
SHOW ETH=0 MACADDRESS ↓
■ Ethernetインターフェースで受信するよう設定されているMACアドレスの一覧は、SHOW ETH RECEIVEコマンドで確認できます。
SHOW ETH RECEIVE ↓
SHOW ETH=0 RECEIVE ↓
■ Ethernetインターフェースに関する各種統計カウンターは、SHOW ETH COUNTERSコマンドで確認できます。
SHOW ETH COUNTERS ↓
SHOW ETH=0 COUNTERS=COLLISION ↓
■ Ethernetインターフェースの統計カウンターは、RESET ETH COUNTERSコマンドでクリアできます。
RESET ETH COUNTERS ↓
RESET ETH=0 COUNTERS ↓
■ Ethernetインターフェースのリンクステータス、速度、デュプレックスモードは、SHOW ETH STATEコマンドで確認できます。
SHOW ETH STATE ↓
SHOW ETH=0 STATE ↓
■ Ethernetインターフェースをリセットするには、RESET ETHコマンドを使います。
BRI(Basic Rate Interface)インターフェースは、ITU-TがISDNのユーザー・網インターフェースとして定めたIインターフェースのうち、基本インターフェース(I.430)と呼ばれる規格に準拠したインターフェースです。BRIはWAN接続用のインターフェースで、ISDN網(INS64。2B+D)、専用線(64K、128K)、フレームリレー網との接続に使用できます。インターフェース名は「BRIn」の形式で表します。
BRIインターフェースには、ISDNと専用線(TDM)の2つの動作モードがあります。接続する回線に応じて動作モードを切り替えてください。動作モードの切り替えはSET BRIコマンドで行います。
■ 本製品のBRIインターフェースはご購入時の状態でISDNモードに設定されているため、BRIインターフェースをISDN網との接続に使用する場合、特別な設定は必要ありません。「ISDN」の章を参考に、接続先(ISDNコール)の設定に進んでください。
■ BRIインターフェースを専用線(またはフレームリレー網)との接続に使用する場合は、SET BRIコマンドで常時起動のTDM(専用線)モードに切り替える必要があります。BRIインターフェース「0」を専用線モードに切り替えるには次のようにします。
SET BRI=0 MODE=TDM ACTIVATION=ALWAYS TDMSLOTS=1-2 ↓
Note
- BRIインターフェースをTDMモードに切り替えるときは、回線速度に関係なく、すべてのタイムスロットをTDMモードに設定してください。BRIインターフェースの場合は、例のように1〜2の全スロットをTDMモードに切り替えます。一部のスロットだけをTDMモードに変更すると、残りのスロットはISDNモードのままとなりますが、日本国内では同一回線上でISDNの回線交換と専用線接続を行えるサービスがありませんので、誤動作を避けるためにも専用線使用時はすべてのスロットをTDMモードに変更してください。
PRI(Primary Rate Interface)インターフェースは、ITU-TがISDNのユーザー・網インターフェースとして定めたIインターフェースのうち、一次群インターフェース(I.431)と呼ばれる規格に準拠したインターフェースです。PRIはWAN接続用のインターフェースで、ISDN網(INS1500。23B+D)、専用線(192K〜1.5M)、フレームリレー網との接続に使用できます。インターフェース名は「PRIn」の形式で表します。
PRIインターフェースには、ISDNと専用線(TDM)の2つの動作モードがあります。接続する回線に応じて動作モードを切り替えてください。動作モードの切り替えはSET PRIコマンドで行います。
■ 本製品のPRIインターフェースはご購入時の状態でISDNモードに設定されているため、PRIインターフェースをISDN網との接続に使用する場合、特別な設定は必要ありません。「ISDN」の章を参考に、接続先(ISDNコール)の設定に進んでください。
■ PRIインターフェースを専用線(またはフレームリレー網)との接続に使用する場合は、SET PRIコマンドでTDM(専用線)モードに切り替える必要があります。PRIインターフェース「0」を専用線モードに切り替えるには次のようにします。
SET PRI=0 MODE=TDM TDMSLOTS=1-24 ↓
Note
- PRIインターフェースをTDMモードに切り替えるときは、回線速度に関係なく、すべてのタイムスロットをTDMモードに設定してください。PRIインターフェースの場合は、例のように1〜24の全スロットをTDMモードに切り替えます。一部のスロットだけをTDMモードに変更すると、残りのスロットはISDNモードのままとなりますが、日本国内では同一回線上でISDNの回線交換と専用線接続を行えるサービスがありませんので、誤動作を避けるためにも専用線使用時はすべてのスロットをTDMモードに変更してください。
同期シリアルインターフェース(SYN = Synchronous Interface)は、高速な同期通信が可能なシリアルインターフェースです。専用ケーブルでDCE(データ回線終端装置。TAやモデム)と接続することにより、専用線、フレームリレー網との接続に使用できます。インターフェース名は「SYNn」の形式で表します。
Note
- SYNインターフェースはDTE(データ端末装置)としてのみ動作します。
Note
- SYNインターフェースは、専用線やフレームリレーのような常時接続形態でのみ使用できます。回線交換モードのTA等には対応していませんのでご注意ください。
SYNインターフェースは、以下のインターフェースをサポートしています。
- V.35 DTE:ARCBL-V35DTEケーブル(専用)が別途必要です。
- X.21 DTE:ARCBL-X21DTEケーブル(専用)が別途必要です。
- V.24 DTE:ARCBL-V24DTEケーブル(専用)が別途必要です。
SYNインターフェースを使用するにあたって、特別に設定しなくてはならない項目はありません。適切なケーブルを接続するだけで、個々のケーブルを自動判別します。したがって、ケーブルを接続した後は、その上で動作させるデータリンク層インターフェース(PPPやFR)の設定を行うだけです。たとえば、PPPの設定を行う場合は、次のようにします。
■ 同期インターフェースの設定や状態を確認するには、SHOW SYNコマンドを使います。
■ 同期インターフェースの各種統計カウンターを表示するには、SHOW SYN COUNTERSコマンドを使います。
SHOW SYN COUNTERS ↓
SHOW SYN=0 COUNTERS ↓
■ 同期インターフェースの統計カウンターをクリアするにはRESET SYN COUNTERSコマンドを使います。
RESET SYN COUNTERS ↓
RESET SYN=0 COUNTERS ↓
なお、RESET SYN COUNTERSコマンドでクリアされるのは、SHOW SYN COUNTERSコマンドの表示内容だけで、MIBカウンター自体はクリアされません。
■ 同期インターフェースのイネーブル/ディセーブルは次のコマンドで行います。
ENABLE SYN=0 ↓
DISABLE SYN=0 ↓
■ 同期インターフェースをリセットするには、RESET SYNコマンドを使います。本コマンドは、DISABLE SYNコマンド、ENABLE SYNコマンドを続けて実行するのと同じ効果を持ちます。
回線制御モジュールは、物理インターフェースに接続した物理回線の制御(発着信やタイムスロットの処理)を行うソフトウェアモジュールです。BRI、PRIの各インターフェースを使用するときは、データリンク層インターフェースを作成する前に回線制御モジュールの設定を行う必要があります。
回線制御モジュールには次の2種類があります。かっこ内はモジュールを使用する物理インターフェースの種類を示しています。
- ISDNモジュール(BRI、PRI)
- TDMモジュール(BRI、PRI)
以下、それぞれのセットアップ方法について例を挙げながら簡単に説明します。なお、各回線制御モジュールについては、「ISDN」(ISDN)、「専用線」(TDM)の各章で解説していますので、詳細についてはそちらをご参照ください。
ISDNモジュールは、BRI、PRIインターフェースでISDN回線に接続するときに使用するモジュールです。信号チャンネル(Dチャンネル)を通じて発信・着信などの制御を行います。
■ ISDN回線を使用するときは、接続先情報を「ISDNコール」として定義する必要があります。ADD ISDN CALLコマンドで、接続先番号などを指定してください。どの物理インターフェースを使用するかは、INTREQパラメーターで指定します。詳しくは「ISDN」の章をご覧ください。
ADD ISDN CALL=remote NUMBER=0612342222 PRECEDENCE=OUT INTREQ=bri0 ↓
SET ISDN CALL=remote OUTSUB=LOCAL SEARCHSUB=LOCAL ↓
この例では、06-1234-2222との接続をISDNコール「remote」として定義しています。作成したISDNコールは、データリンク層インターフェース(PPP)の作成時に下位インターフェースとして指定することができます。そのときは、ISDNコール名を「ISDN-」+「コール名」の形式で指定します(例:ISDN-remote)。
TDM(Time Division Multiplexing)モジュールは、BRI、PRIインターフェースでデジタル専用回線に接続するときに使用するモジュールです。使用するタイムスロットに応じてデータの組み立てや分解(時分割多重)を行います。
■ 専用線を使用するときは、物理インターフェース上で使用するタイムスロットを「TDMグループ」として定義します。使用するスロットは回線速度に応じて変わります。1スロットは64Kbpsなので、64Kbpsなら1スロットのみ、128Kbpsなら1-2スロットとなります。
64Kbps専用線の場合(BRI)
CREATE TDM GROUP=remote INT=bri0 SLOTS=1 ↓
128Kbps専用線の場合(BRI)
CREATE TDM GROUP=remote INT=bri0 SLOTS=1-2 ↓
512Kbps専用線の場合(PRI)
CREATE TDM GROUP=remote INT=pri0 SLOTS=1-8 ↓
1.5Mbps専用線の場合(PRI)
CREATE TDM GROUP=remote INT=pri0 SLOTS=1-24 ↓
作成したTDMグループは、データリンク層インターフェース(PPP、FR)の作成時に下位インターフェースとして指定することができます。そのときは、TDMグループ名を「TDM-」+「グループ名」の形式で指定します(例:TDM-remote)。
なお、TDMグループを定義するときは、あらかじめBRI、PRIインターフェースの動作モードをTDMモードに変更しておく必要があります。モード変更はSET BRIコマンド、SET PRIコマンドで行います。詳細は「物理インターフェース」をご覧ください。
本製品で使用できるデータリンク層インターフェースは以下の4種類です。
- VLANインターフェース(vlan)
- Ethernetインターフェース(eth)
- PPPインターフェース(ppp)
- フレームリレーインターフェース(fr)
データリンク層インターフェースは、物理インターフェースの上に直接作成する場合と、物理インターフェース上にセットアップした回線制御モジュール上に作成する場合があります。以下、それぞれのセットアップ方法について、例を挙げながら簡単に説明します。各データリンク層インターフェースの詳細な設定方法については、「PPP」、「フレームリレー」の各章をご覧ください(VLANインターフェース、Ethernetインターフェースは特に設定の必要がないため、単独の章はありません)。
VLANインターフェースは、物理層とデータリンク層が一体になっています。VLANインターフェースを使用するにあたって特別な設定は必要ありません。ネットワーク層インターフェースの設定時に、インターフェース名(vlan1で固定)を指定するだけで使用できます。
Note
- LAN側スイッチポートのグループ構成を変更することはできません。常に全ポートがvlan1所属になります。IPアドレスなど上位層の設定は、個々のスイッチポートではなく、vlan1インターフェースに対して行います。
Ethernetインターフェースは、物理層とデータリンク層が一体になっています。Ethernetインターフェースを使用するにあたって特別な設定は必要ありません。ネットワーク層インターフェースの設定時に、インターフェース名(例:eth0)を指定するだけで使用できます。
PPPインターフェースは、2点間のWAN接続に使用するデータリンク層インターフェースです。PPPインターフェースは、以下のインターフェース(物理インターフェースか回線制御モジュール)上に作成することができます。
- ISDNコール(ISDN接続)
- TDMグループ(専用線接続)
- 同期シリアルインターフェース(syn)
- Ethernetインターフェース(eth)
また、トンネリングプロトコルL2TPを使用すると、IPネットワーク上に仮想的な回線(L2TPコール)を構築し、その上にPPPインターフェースを作成することもできます。これについては、「L2TP」の章をご覧ください。
PPPインターフェースはCREATE PPPコマンドで作成します。下位のインターフェースは、OVERパラメーターで指定します。
■ ISDN上でPPPを使用するには、OVERパラメーターにISDNコール名を「ISDN-」+「コール名」の形式で指定します。ISDN回線では、通常「IDLE=ON」を指定してダイヤルオンデマンドを有効にします。
CREATE PPP=0 OVER=ISDN-remote IDLE=ON ↓
■ BRI、PRIインターフェースによる専用線接続でPPPを使用するには、OVERパラメーターにTDMグループ名を「TDM-」+「グループ名」の形式で指定します。
CREATE PPP=0 OVER=TDM-remote ↓
■ 同期インターフェースによる専用線接続でPPPを使用するには、OVERパラメーターにインターフェース名(SYNn)を指定します(nは番号)。
■ Ethernet上でPPP(PPPoE)を使用するには、OVERパラメーターに「Ethernetインターフェース名」+ハイフン(-)+「PPPoEサービス名」を指定します。ISPからPPPoEサービス名が指定されていない場合は、すべてのサービスを意味するキーワード「any」か任意の文字列を指定します。
CREATE PPP=0 OVER=eth0-any ↓
必要なときだけ接続するようにするには、「IDLE=ON」を指定してダイヤルオンデマンドを有効にします。
CREATE PPP=0 OVER=eth0-any IDLE=ON ↓
Note
- VLANインターフェース上ではPPPoEを使用できません。
フレームリレー(FR)インターフェースは、フレームリレー網と接続するときに使うデータリンク層インターフェースです。FRインターフェースは、以下のインターフェース(物理インターフェースか回線制御モジュール)上に作成することができます。
- TDMグループ(専用線接続)
- 同期シリアルインターフェース(syn)
FRインターフェースはCREATE FRAMERELAYコマンドで作成します。下位のインターフェースは、OVERパラメーターで指定します。
■ BRI、PRIインターフェースでフレームリレー網に接続するときは、CREATE FRAMERELAYコマンドのOVERパラメーターに、TDMグループ名を「TDM-」+「グループ名」の形式で指定します。また、使用するPVC状態確認手順(LMI)をLMISCHEMEパラメーターで指定してください。「RESET FR=0」はLMIの設定を有効にするためのコマンドです。
CREATE FR=0 OVER=TDM-remote LMISCHEME=ANNEXD ↓
RESET FR=0 ↓
■ 同期インターフェースでフレームリレー網に接続するには、OVERパラメーターにインターフェース名(SYNn)を指定します(nは番号)。また、使用するPVC状態確認手順(LMI)をLMISCHEMEパラメーターで指定してください。「RESET FR=0」はLMIの設定を有効にするためのコマンドです。
CREATE FR=0 OVER=syn0 LMISCHEME=ANNEXD ↓
RESET FR=0 ↓
Note
- 「RESET FR=0」は、コマンドラインからフレームリレーインターフェースの設定を行った場合にのみ必要なものです。テキストエディター等で設定ファイルを直接編集する場合、「RESET FR=0」は不要です。
本製品で使用できるネットワーク層インターフェースは以下の4種類です。かっこ内は設定コマンドにおける呼称です。
- IPインターフェース
- IPv6インターフェース
- IPXインターフェース(IPXサーキット)
- AppleTalkインターフェース(AppleTalkポート)
ネットワーク層インターフェースは、ルーターの基本機能であるルーティングのためのインターフェースです。本製品をルーターとして機能させるためには、使用するルーティングモジュール(IP、IPv6、IPX、AppleTalk)を有効にし、ネットワーク層インターフェースを2つ以上作成する必要があります。
ネットワーク層インターフェースは、データリンク層インターフェースの上に作成します。以下、プロトコルごとにセットアップ方法を簡単に説明します。各プロトコルの詳細な設定方法については、「IP」、「IPv6」、「IPX」、「AppleTalk」の各章をご覧ください。
IPインターフェースは、IPパケットの送受信を行うためのインターフェースです。IPモジュールを有効にし、IPインターフェースを複数作成した時点でIPパケットの転送(ルーティング)が行われるようになります。
IPインターフェースは、ADD IP INTERFACEコマンドでデータリンク層インターフェースにIPアドレス(とネットマスク)を割り当てることによって作成します。詳細は「IP」の章をご覧ください。
作成したIPインターフェースは、データリンク層インターフェースと同じ名前で参照できます。たとえば、Ethernetインターフェース「0」上に作成したIPインターフェースを他のIP関連コマンドで指定するときは「eth0」とします。
■ IPモジュールを有効化するには、ENABLE IPコマンドを実行します。
■ VLANインターフェースにIPアドレスを設定するには次のようにします。
ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.1.1 MASK=255.255.255.0 ↓
■ EthernetインターフェースにIPアドレスを設定するには次のようにします。
ADD IP INT=eth0 IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0 ↓
■ PPPインターフェースにIPアドレスを設定するには次のようにします。
ADD IP INT=ppp0 IP=192.168.100.1 MASK=255.255.255.0 ↓
■ フレームリレーインターフェースにIPアドレスを設定するには次のようにします。
ADD IP INT=fr0 IP=192.168.200.1 MASK=255.255.255.0 ↓
IPv6インターフェースは、IPv6パケットの送受信を行うためのインターフェースです。IPv6モジュールを有効にし、IPv6インターフェースを複数作成した時点でIPv6パケットの転送(ルーティング)が行われるようになります。
IPv6インターフェースは、ADD IPV6 INTERFACEコマンドでデータリンク層インターフェースにIPv6アドレスとプレフィックス長を割り当てることによって作成します。詳細は「IPv6」の章をご覧ください。
作成したIPv6インターフェースは、データリンク層インターフェースと同じ名前で参照できます。たとえば、Ethernetインターフェース「0」上に作成したIPv6インターフェースを他のIPv6関連コマンドで指定するときは「eth0」とします。
Note
- フレームリレー上でのIPv6はサポートしていません。
■ IPv6モジュールを有効化するには、ENABLE IPV6コマンドを実行します。
■ VLANインターフェースにIPv6アドレスを設定するには次のようにします。
ADD IPV6 INT=vlan1 IP=3ffe:1:2:3::1/64 ↓
■ EthernetインターフェースにIPv6アドレスを設定するには次のようにします。
ADD IPV6 INT=eth0 IP=2001:1:2:10::1/64 ↓
■ インターフェース上でプレフィックス通知を行う場合は、次のように「PUBLISH=YES」を付け、さらにENABLE IPV6 ADVERTISEコマンドを実行します。
ADD IPV6 INT=eth0 IP=2001:1:2:10::1/64 PUBLISH=YES ↓
ENABLE IPV6 ADVERTISE ↓
■ PPPインターフェースにIPV6アドレスを設定するには次のようにします。
ADD IPV6 INT=ppp0 IP=2001:1:2:100::1/128 ↓
■ リンクローカルアドレスのみを自動設定で割り当てる場合は、CREATE IPV6 INTERFACEコマンドを使います。
IPXインターフェースは、IPXパケットの送受信を行うためのインターフェースです。IPXモジュールを有効にし、IPXインターフェースを複数作成した時点でIPXパケットの転送(ルーティング)が行われるようになります。
IPXインターフェース(IPXサーキット)は、ADD IPX CIRCUITコマンドでデータリンク層インターフェースを指定し、該当データリンク上で使用するIPXネットワーク番号を割り当てることによって作成します。詳細は「IPX」の章をご覧ください。
作成したIPXインターフェースは、ADD IPX CIRCUITコマンドのCIRCUITパラメーターで指定したインターフェース番号で参照します。
■ IPXモジュールを有効化するには、ENABLE IPXコマンドを実行します。
■ VLANインターフェース上にIPXインターフェースを作成するには次のようにします。VLANの場合はフレームタイプも指定してください。
ADD IPX CIRCUIT=1 INT=vlan1 NETWORK=1 ENCAPSULATION=802.2 ↓
■ Ethernetインターフェース上にIPXインターフェースを作成するには次のようにします。Ethernetの場合はフレームタイプも指定してください。
ADD IPX CIRCUIT=1 INT=eth0 NETWORK=10 ENCAPSULATION=802.2 ↓
■ PPPインターフェース上にIPXインターフェースを作成するには次のようにします。
ADD IPX CIRCUIT=2 INT=ppp0 NETWORK=100 ↓
PPPのダイヤルオンデマンド機能が有効なとき(IDLE=ON)は「DEMAND=ON」を指定します。これにより、経路情報の定期交換が抑制され、IPXの代理応答が有効になります。
ADD IPX CIRCUIT=2 INT=ppp0 NETWORK=100 DEMAND=ON ↓
■ フレームリレーインターフェース上にIPXインターフェースを作成するには次のようにします。フレームリレーの場合はDLCI(論理パス番号)も指定してください。
ADD IPX CIRCUIT=3 INT=fr0 NETWORK=200 DLCI=16 ↓
フレームリレーサービスの契約が従量制の場合は、「DEMAND=ON」を指定することによって、経路情報の定期交換を抑制し、IPXの代理応答を有効化できます。
ADD IPX CIRCUIT=3 INT=fr0 NETWORK=200 DLCI=16 DEMAND=ON ↓
AppleTalkインターフェースは、AppleTalkパケットの送受信を行うためのインターフェースです。AppleTalkモジュールを有効にし、AppleTalkインターフェースを複数作成した時点でAppleTalkパケットの転送(ルーティング)が行われるようになります。
AppleTalkインターフェース(AppleTalkポート)は、ADD APPLETALK PORTコマンドでデータリンク層インターフェースを指定することによって作成します。Ethernet上でシードルーター(AppleTalkノードにネットワークアドレスを通知するルーター)として機能させる場合は、該当データリンク上で使用するネットワーク番号(の範囲)も指定します。詳細は「AppleTalk」の章をご覧ください。
作成したAppleTalkインターフェースは、ADD APPLETALK PORTコマンドの実行順に1から順番に割り当てられるインターフェース番号で参照します。番号はSHOW APPLETALK PORTコマンドで確認できます。インターフェースの作成時に番号を指定することはできません。
■ AppleTalkモジュールを有効化するには、ENABLE APPLETALKコマンドを実行します。
■ VLANインターフェース上にAppleTalkインターフェースを作成するには次のようにします。シードルーターとして機能させる場合は、SEEDパラメーターでネットワーク番号の範囲(ネットワークレンジ)も指定してください。
ADD APPLETALK PORT INT=vlan1 SEED=1-1 ↓
■ Ethernetインターフェース上にAppleTalkインターフェースを作成するには次のようにします。シードルーターとして機能させる場合は、SEEDパラメーターでネットワーク番号の範囲(ネットワークレンジ)も指定してください。
ADD APPLETALK PORT INT=eth0 SEED=10-10 ↓
同一Ethernetセグメントにシードルーターがすでに存在しているときは、ネットワーク番号を指定しないでください。
ADD APPLETALK PORT INT=eth0 ↓
■ PPPインターフェース上にAppleTalkインターフェースを作成するには次のようにします。AppleTalkでは、通常WANポートにはアドレスを割り当てません。
ADD APPLETALK PORT INT=ppp0 ↓
PPPのダイヤルオンデマンド機能が有効なとき(IDLE=ON)は、「DEMAND=ON」を指定して経路情報の定期交換が行われないようにします。
ADD APPLETALK PORT INT=ppp0 DEMAND=ON ↓
■ フレームリレーインターフェース上にAppleTalkインターフェースを作成するには次のようにします。フレームリレーの場合は、ADD APPLETALK PORTコマンドでインターフェースを作成した後、ADD APPLETALK DLCIコマンドでインターフェースに所属するDLCI(論理パス番号)を明示的に指定する必要があります。
ADD APPLETALK PORT INT=fr0 ↓
ADD APPLETALK DLCI=16 PORT=1 ↓
Note
- AppleTalkのポート番号は作成順(ADD APPLETALK PORTコマンドの実行順)に1番、2番...と付けられます。番号はSHOW APPLETALK PORTコマンドで確認できます。
フレームリレーサービスの契約が従量制の場合は、「DEMAND=ON」を指定することで経路情報の定期交換を行わないよう設定できます。
ADD APPLETALK PORT INT=fr0 DEMAND=ON ↓
ADD APPLETALK DLCI=16 PORT=1 ↓
(C) 2002 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社
PN: J613-M3048-01 Rev.M