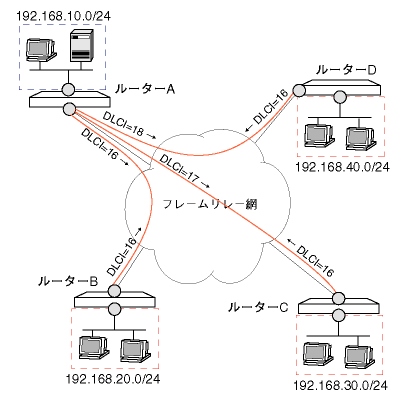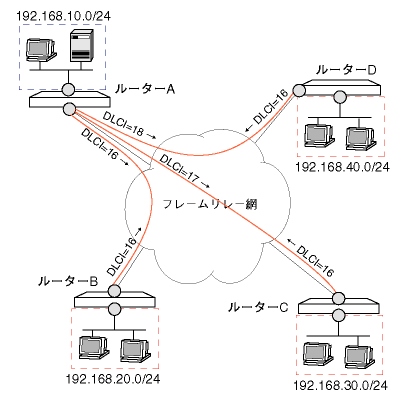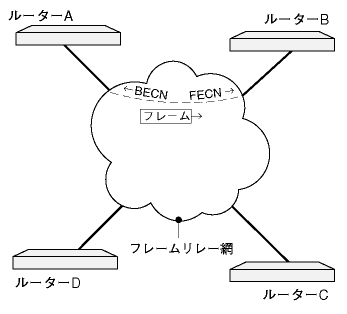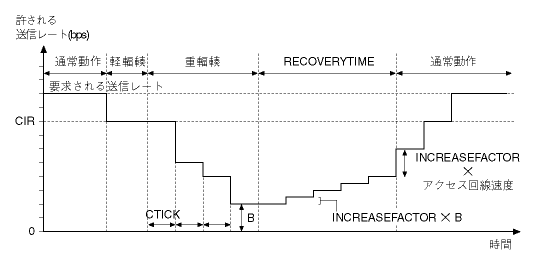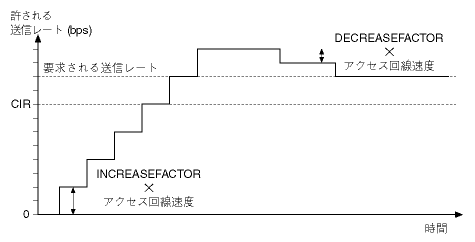[index]
CentreCOM AR410 V2 コマンドリファレンス 2.6
フレームリレー/概要・基本設定
- 基本設定
- 物理層のセットアップ
- フレームリレーインターフェースの作成
- 上位層とのインターフェース
- フレームリレー論理インターフェース
- 輻輳制御
- 輻輳通知
- 輻輳検出時の動作
- スロースタートメカニズム
- 暗号・圧縮機能(FRF.9)
フレームリレー(Frame Relay)は、通信事業者が提供する広域データ通信網サービスです。契約時にDLC(Data Link Connection)と呼ぶ論理パスを設定し、一本の物理回線で複数拠点との固定接続が可能な点が特徴です。
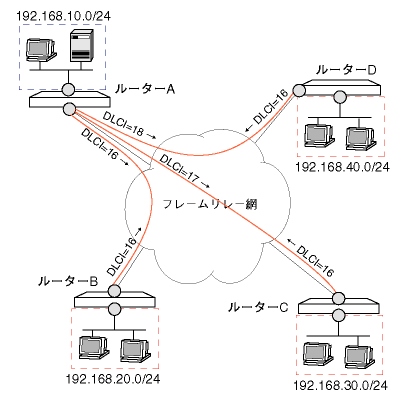
フレームリレー網への接続には、BRI、PRI、SYNの各インターフェースを使用することができます。ここでは、これらのインターフェースを使って、本製品をフレームリレー網に接続するための概要について説明します。
フレームリレー網に接続するための基本設定を示します。
物理インターフェースとして使用できるのは、BRI、PRI、SYNの3種類です。いずれの場合も、物理層の設定は専用線接続と同じです。
■ BRIインターフェースを使う場合は、インターフェースの動作モードを常時起動のTDM(専用線)モードに切り替え、TDMグループを作成します。TDMグループ作成時には、回線速度に応じてスロット数を割り当てます。
SET BRI=0 MODE=TDM ACTIVATION=ALWAYS TDMSLOTS=1-2 ↓
CREATE TDM GROUP=access INT=bri0 SLOTS=1-2 ↓
■ PRIインターフェースを使う場合は、インターフェースの動作モードをTDM(専用線)モードに切り替え、TDMグループを作成します。TDMグループ作成時には、回線速度に応じてスロット数を割り当てます。
SET PRI=0 MODE=TDM TDMSLOTS=1-24 ↓
CREATE TDM GROUP=access INT=pri0 SLOTS=1-24 ↓
■ SYNインターフェースを使う場合は、接続するDCE(TA等)に応じて専用ケーブルを選択してください。特別な設定は必要ありません。
フレームリレーインターフェースはCREATE FRAMERELAYコマンドで作成します。このとき必要なのは、インターフェース番号(0〜63)、物理インターフェース、PVC状態確認手順(LMI)の3つです。
LMIについてはサービス事業者にご確認ください。本製品は以下のLMIをサポートしています(「キーワード」はLMISCHEMEパラメーターに指定する値です)。デフォルトはLMIREV1です。
表 1
| キーワード |
PVC状態確認手順(LMI) |
| LMIREV1 |
フレームリレーベンダー標準LMI Rev.1 |
| ANNEXAまたはQ933A |
ITU-T Q933a(Annex A) |
| ANNEXBまたはT1617B |
ANSI T1617B(Annex B) |
| ANNEXDまたはT1617D |
ANSI T1617D(Annex D) |
■ TDMグループ「access」上にフレームリレーインターフェース「0」を作成します。ここではLMIとしてAnnex Aを指定しています。RESET FR=0はLMIの設定を有効にするためのものです
CREATE FR=0 OVER=TDM-access LMISCHEME=ANNEXA ↓
RESET FR=0 ↓
■ 同期インターフェース「syn0」上にフレームリレーインターフェース「0」を作成します。LMIにはAnnex Dを指定しています。
CREATE FR=0 OVER=syn0 LMISCHEME=ANNEXD ↓
RESET FR=0 ↓
Note
- 例中の「RESET FR=0」はフレームリレーインターフェースをリセットするコマンドです。コマンドラインからLMIを設定したときは、フレームリレーインターフェースをいったんリセットしてください。このコマンドは、コマンドラインから設定を行っているときだけ必要なものです。設定ファイル(*.cfg)をテキストエディター等で直接編集する場合、「RESET FR=0」は不要です。
作成したフレームリレーインターフェースは、第2層(データリンク層)インターフェースとして扱われ、上位にIPやIPX等の第3層(ネットワーク層)インターフェースを作成できます。このとき、フレームリレーインターフェースは「FRn」の形式で指定します。nはインターフェース番号です。
■ フレームリレーインターフェース「0」上にIPインターフェースを作成するには、ADD IP INTERFACEコマンドを使います。
ADD IP INT=fr0 IP=192.168.100.1 MASK=255.255.255.0 ↓
フレームリレー上でIPを使用する場合、通常はInverse ARPよって各DLC上の対向ルーターのIPアドレスを取得します。しかし、対向ルーターがサポートしていないなどの理由でInverse ARPを使用しない場合は、ADD IP ARPコマンドで対向ルーターのIPアドレスをスタティックに登録してください。たとえば、fr0において、DLC 16上の対向ルーターのIPアドレスが192.168.100.2ならば、次のようにします。
ADD IP ARP=192.168.100.2 INT=fr0 DLCI=16 ↓
■ 同一インターフェース上に複数のIPアドレスを設定するときは、後述するフレームリレー論理インターフェース(FRLI)を使います。FRLIを使うと、DLCを任意のグループに分け、それぞれを個別のIPインターフェースとして扱うことができます。
ADD FR=0 LI=1 ↓
SET FR=0 DLC=18 LI=1 ↓
SET FR=0 DLC=19 LI=1 ↓
ADD IP INT=fr0.0 IP=192.168.100.1 MASK=255.255.255.0 ↓
ADD IP INT=fr0.1 IP=192.168.110.1 MASK=255.255.255.0 ↓
■ フレームリレーインターフェース「0」上にIPXインターフェース(IPXサーキット)を作成するには、ADD IPX CIRCUITコマンドを使います。IPXインターフェースはDLC単位で作成するため、DLCIも指定してください。
ADD IPX CIRCUIT=1 INT=fr0 NETWORK=100 DLCI=16 ↓
■ フレームリレーインターフェース「0」上にAppleTalkインターフェース(AppleTalkポート)を作成するには、ADD APPLETALK PORTコマンドを使います。さらに、AppleTalkポートを作成したら、ADD APPLETALK DLCIコマンドで使用するDLCを指定します。AppleTalkでは、WAN側インターフェースは通常Unnumberedとなります。
ADD APPLETALK PORT INT=fr0 ↓
ADD APPLETALK DLCI=16 PORT=1 ↓
Note
- AppleTalkポート番号は、1から順に自動的に割り当てられます。ADD APPLETALK DLCIコマンドのPORTパラメーターに指定する番号は、SHOW APPLETALK PORTコマンドで確認してください。
フレームリレー論理インターフェース(FRLI)は、同一インターフェース上に設定されたDLCを任意のグループに分割して、それぞれを個別の論理インターフェースとして扱う機能です。個々の論理インターフェースには、それぞれ別のIPアドレスを割り当てることができます。
■ CREATE FRAMERELAYコマンドでフレームリレーインターフェースを作成すると、自動的にデフォルトの論理インターフェース「0」が作成されます。特に設定を行わない限り、同インターフェース上のDLCはすべて論理インターフェース「0」の所属となります。
CREATE FR=0 OVER=TDM-access ↓
■ 論理インターフェースを新規作成するには、ADD FRAMERELAY LIコマンドを使います。フレームリレーインターフェース「0」上に論理インターフェース「1」を作成するには、次のようにします。
■ デフォルトでは、フレームリレーインターフェース上のDLCはすべてデフォルトの論理インターフェース「0」に所属しています。DLCを他の論理インターフェースに所属させるには、SET FRAMERELAY DLCコマンドのLIパラメーターを使います。たとえば、DLC「110」と「111」をフレームリレーインターフェース「0」上の論理インターフェース「1」に所属させるには次のようにします。
SET FR=0 DLC=110 LI=1 ↓
SET FR=0 DLC=111 LI=1 ↓
■ フレームリレー論理インターフェースは「frA.B」の形式で表します。「A」はフレームリレーインターフェースの番号、「B」は論理インターフェース番号です。フレームリレーインターフェース「0」上の論理インターフェース「fr0.0」と「fr0.1」にIPアドレスを割り当てるには次のようにします。
ADD IP INT=fr0.0 IP=192.168.100.1 MASK=255.255.255.0 ↓
ADD IP INT=fr0.1 IP=192.168.110.1 MASK=255.255.255.0 ↓
Note
- 単に「fr0」と指定した場合は、フレームリレーインターフェース全体に対してIPアドレスを割り当てることになります。論理インターフェースを使うときは、デフォルトの「0」番に対しても「fr0.0」のように指定してください。
Note
- 論理インターフェースはIPだけを対象としています。IPX、AppleTalkでは、もともとインターフェース作成時にDLCIを指定するようになっているため、論理インターフェースの必要がありません(使えません)。
■ 論理インターフェースの情報は、SHOW FRAMERELAY LIコマンドで確認できます。
本製品は、輻輳(網が混んでいること)が検出された場合に送信するトラフィック量を制限し、輻輳を可能な限り迅速に解決する機能を備えています(輻輳制御は、単位時間内にルーターが網に対して送信するトラフィック量を制御するもの、すなわち網とルーター間に関するものであり、通信相手のルーターにこの機能が設定されている必要はありません)。
フレームリレー網には、輻輳状態を通知する機能があります。どの種類の機能がサポートされているかは、通信事業者によって異なります。本製品は、「BECN(Backward Explicit Congestion Notification)」と「CLLM(Consolidated Link Layer Management)」に対応しており、デフォルトでは両方で輻輳を検出します。たいていの事業者はBECNをサポートしており、一部の事業者はBECNとCLLMの両方をサポートしています。
■ BECNビット
フレームリレー網が輻輳しているとき、網は輻輳が発生している個所を通過するフレームのうち、輻輳の原因となっているトラフィックとは逆方向に流れるフレームのBECNビットを立てます。これにより、輻輳の原因となっているトラフィックの発生元に対して輻輳発生を通知します。本製品は、網から受信した各フレームのBECNビットを調査し、DLCごとにBECNビットが立っている受信フレームの数をカウントします。本製品は、BECNビットが立っている最初のフレームを受信した時点で、網が軽輻輳状態にあるとみなします。BECNビットの立ったフレームを限界値(CREATE FRAMERELAYコマンド/SET FRAMERELAYコマンドのBECNLIMITパラメーター)以上連続して受信した場合、本製品は網が重輻輳状態にあると判断します。
輻輳時(軽度と重度の両方)には、BECNビットが立っていないフレームを「BECNLIMIT/2」(個)連続して受信した場合、または最初にBECNビットが立っていないフレームを受信してからBECNビットが立っていないフレームの受信がBECNTIMEOUT(秒)持続したときに、本製品は網が輻輳から回復したと判断します。
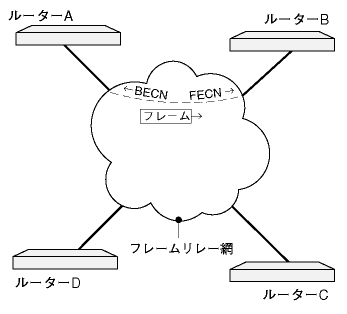
■ CLLM
CLLMは、フレームリレー網が輻輳状態になったときなどに、網から10秒間隔で送られるメッセージです。CLLMメッセージは、輻輳の原因や度合の情報を含んでおり、本製品はその情報に合わせて輻輳の制御を行います。輻輳状態でないときには、輻輳の情報を含むCLLMメッセージは送られません。11秒以上経過しても、CLLMメッセージが受信されない場合、本製品は網が輻輳から回復したと解釈します。
BECNビットまたはCLLMメッセージのどちらかによって軽輻輳を検出すると、本製品は該当するDLCの送信レートをDLCのCommitted Information Rate(CIR)まで落とします。CIRのデフォルト値は、リンクの帯域幅の1/2です。
重輻輳が検出された場合は、CTICKで定義された時間の経過の後、送信レートを「0.675×CIR」まで落とします。さらに、もう一度CTICKの時間が経過した後も重輻輳状態が継続した場合、送信レートは「0.5×CIR」にまで落とされ、次のCTICKの経過後も同様であれば、最終的に「0.25×CIR」にまで落とされます。
CLLMを通じて故障通知または全フレーム破棄通知を受信した場合は、上位層からフレームリレーモジュールに渡されるすべてのパケットはまず待ち行列に入れられ、待ち行列が制限に到達すると破棄されます。
DLCが輻輳から回復したとき、スロースタートメカニズムが有効に設定されていれば、送信レートはスロースタートメカニズムによって制御されたレートで増加します。もし、スロースタートメカニズムが有効でなければ、送信レートはただちに輻輳がないときにおける制限のない状態となります。輻輳が検出されたとき、輻輳制御とスロースタートメカニズムの両方を有効にした場合の送信レートの変化を次の図に示します。図では、輻輳制御関連のパラメーターと送信レートの変化がどのように関係するかも示しています。
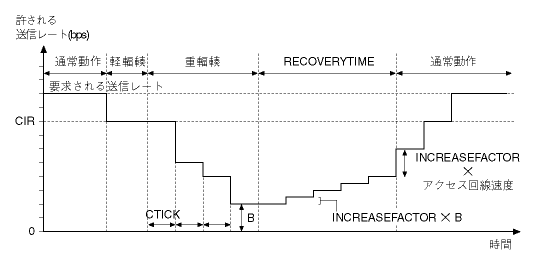
■ 輻輳制御を有効化または無効化するには、次のコマンドを使用します。デフォルトは無効です。
ENABLE FR=0 CONGESTIONCONTROL ↓
DISABLE FR=0 CONGESTIONCONTROL ↓
■ DLCのCIRを設定するには、SET FRAMERELAY DLCコマンドのCIRパラメーターを使います。単位はbpsです。省略時はリンク帯域幅の1/2に設定されます。次の例ではfr0上のDLCI=16のCIRを32Kbpsに設定しています。
SET FRAMERELAY=fr0 DLC=16 CIR=32000 ↓
■ 輻輳に関する情報を入手するには、SHOW LOGコマンドのMODULEパラメーターにFRを指定します。このコマンドを実行すると、網が輻輳しているかどうか、輻輳がいつから始まりいつ終わったか(=いつからフレームが破棄されていたか)、輻輳状態だった期間、といった輻輳に関するログが表示されます。
■ BECN受信状況の表示
BECNフレームを受信したかどうかを調べるには、SHOW FRAMERELAYコマンドのCOUNTERSオプションを使います。該当するDLCIの「BECN」欄に表示された数が、BECNビットがオンのフレーム数を示します。
SHOW FRAMERELAY COUNTERS ↓
Note
- 輻輳発生を通知する方法には、「FECN(Forward Explicit Congestion Notification」という方法もあります。FECNとは、輻輳の原因となるトラフィックと同じ方向に流れるフレームのFECNビットをオンにすることで、フレームの受信側に対して網が輻輳状態であることを通知する方法です。SHOW FRAMERELAYコマンドのCOUNTERSパラメーターで表示される項目の中にも「FECN」欄があります。この欄で、FECNビットがオンのフレーム数を知ることができますが、本製品はFECNに基づく輻輳制御は行いません。
ルーターがフレームリレー網に対してデータの送信を開始するとき、急激にトラフィック量を増加させると輻輳の原因となります。トラフィック増加による影響を最小限におさえ、深刻な輻輳を避けるため、本製品にはスロースタートメカニズムが実装されています。
スロースタートメカニズムは、データの送信レートを制限し、トラフィック量の急激な変化を防ぐものです。最初にDLCがアクティブになったとき、そのDLCでの送信レートは非常に小さな値をとります。この送信レートは、上位層からフレームリレーモジュールへのデータ転送レートに等しくなるか、または物理インターフェースの帯域幅に到達するか、または輻輳が発生するまで徐々に増加していきます。
次の図は、送信レートが「INCREASEFACTOR×アクセス回線速度」の幅で段階的に増加してゆき、次いで、要求される送信レートに落ち着くまで「DECREASEFACTOR×アクセス回線速度」の幅で段階的に低下していくようすを示しています。許される送信レートが要求される送信レートを上回って増加している点に注目してください。これは、送信レートが希望の送信レートを下回っていたときに待ち行列に入れられたパケットをクリアするためです。
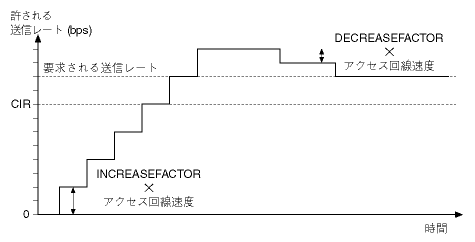
■ スロースタートメカニズムを有効化または無効化するには、次のコマンドを使用します。デフォルトは無効です。
ENABLE FRAMERELAY=0 SLOWSTART ↓
DISABLE FRAMERELAY=0 SLOWSTART ↓
本製品では、フレームリレーフォーラム標準FRF.9方式によるデータリンク圧縮が可能です。また、同方式を拡張した暗号機能も使用できます。暗号・圧縮はDLC単位で設定できます。
FRF.9を使用する場合は、対向ルーターも同じ方式に設定されている必要があります。暗号・圧縮使用時の対向ルーターとのネゴシエーションは、DLCの初期設定時にPPPの制御用サブプロトコルであるCCP(Compression Control Protocol, RFC1962)とECP(Encryption Control Protocol, RFC1968)によって行われます。対向ルーターが暗号をサポートしていなかった場合は、該当DLCは使用できなくなります。
暗号機能を使用するには、暗号・圧縮ボード(AR011 V2)が必要です。一方、圧縮機能は本体のみでも使用できます。
フレームリレーの暗号化・圧縮の詳細については、「暗号・圧縮」の章をご覧ください。
(C) 2002 - 2008 アライドテレシスホールディングス株式会社
PN: J613-M3048-01 Rev.M