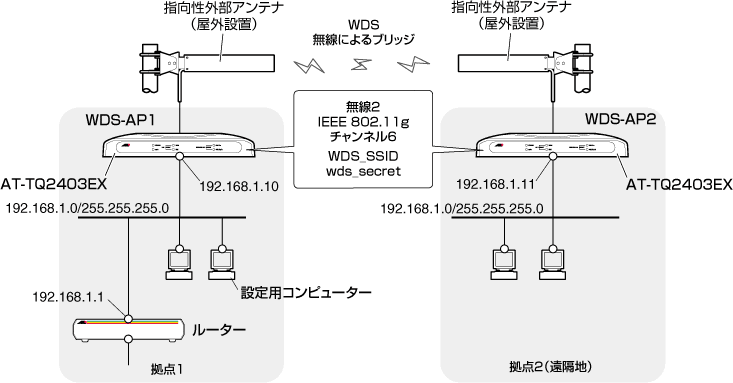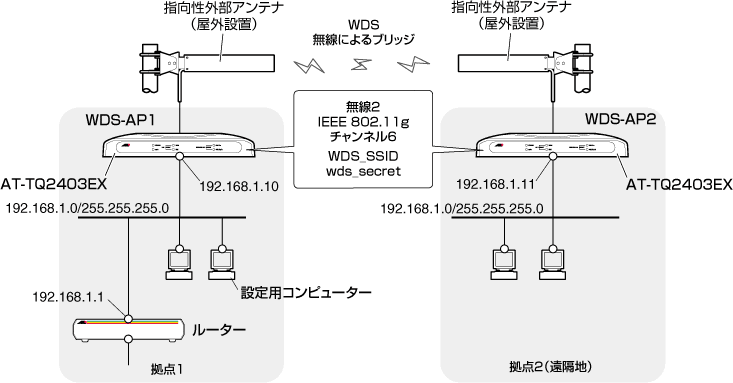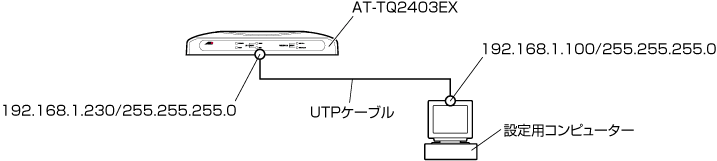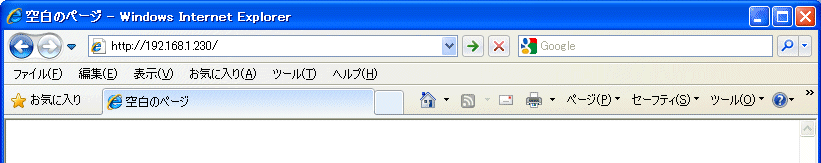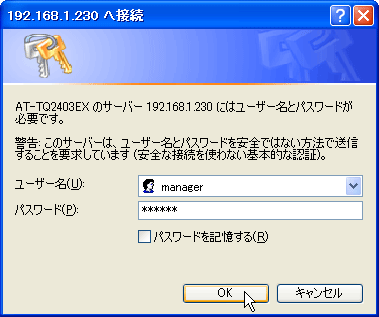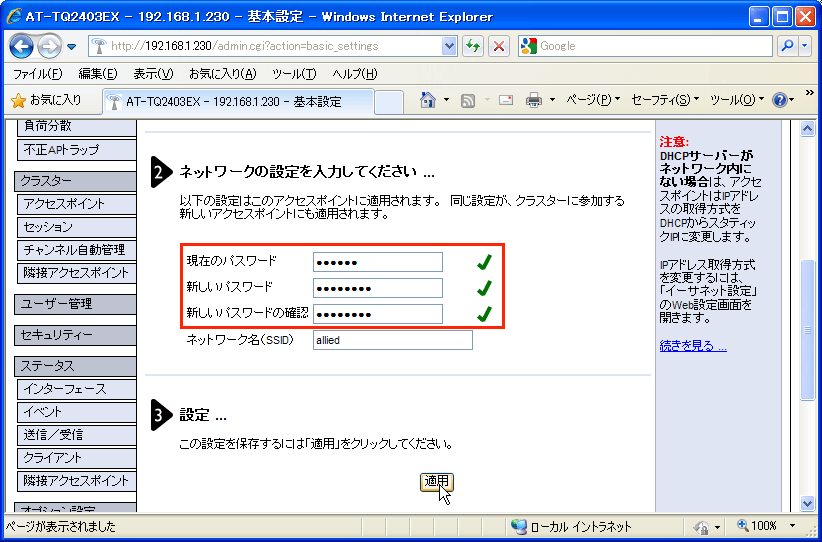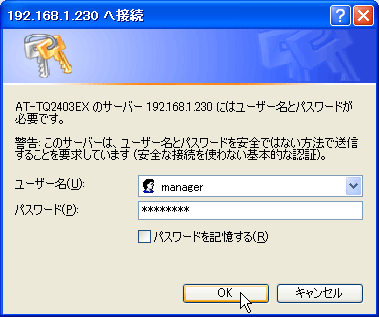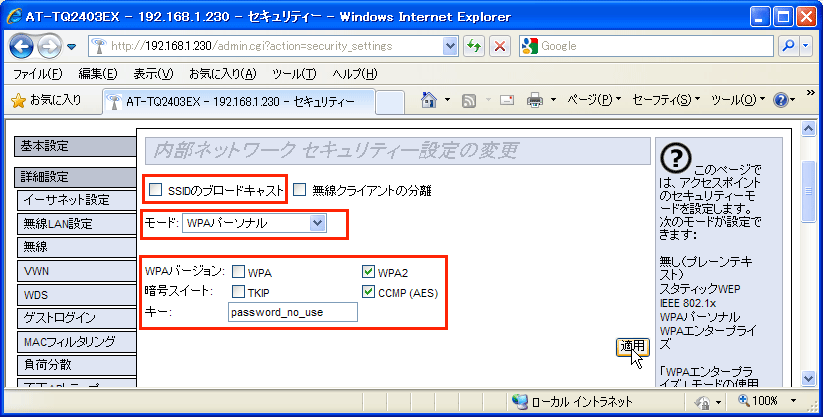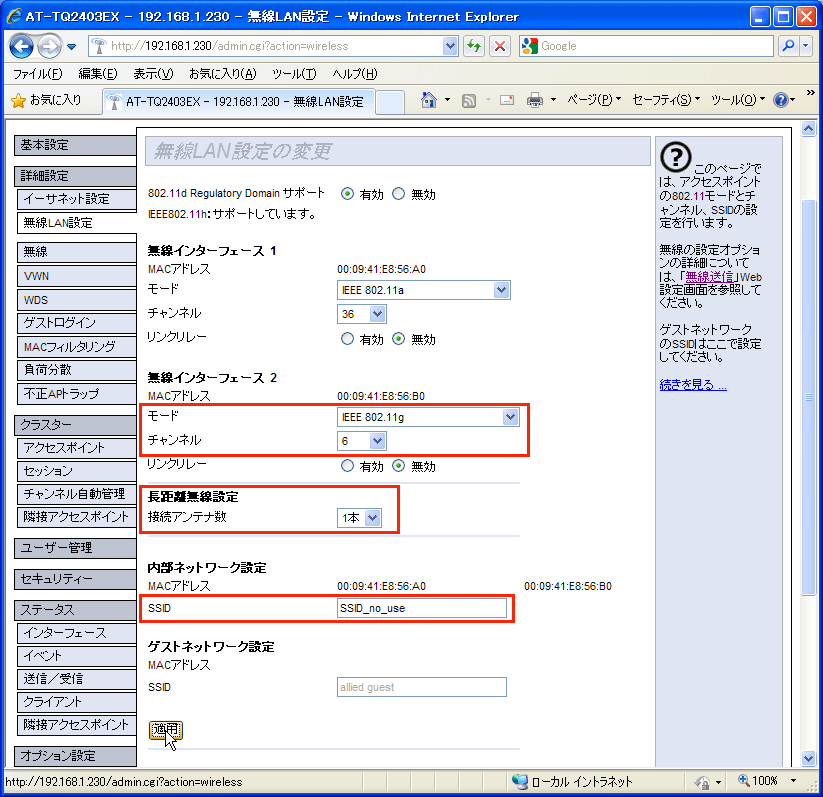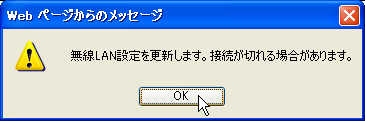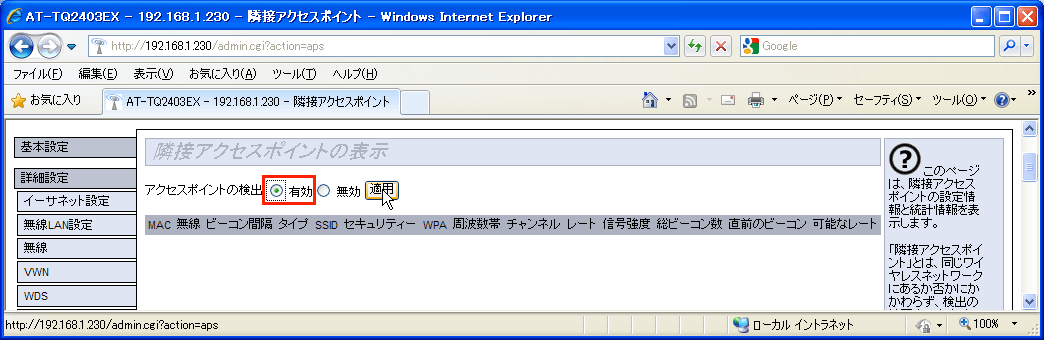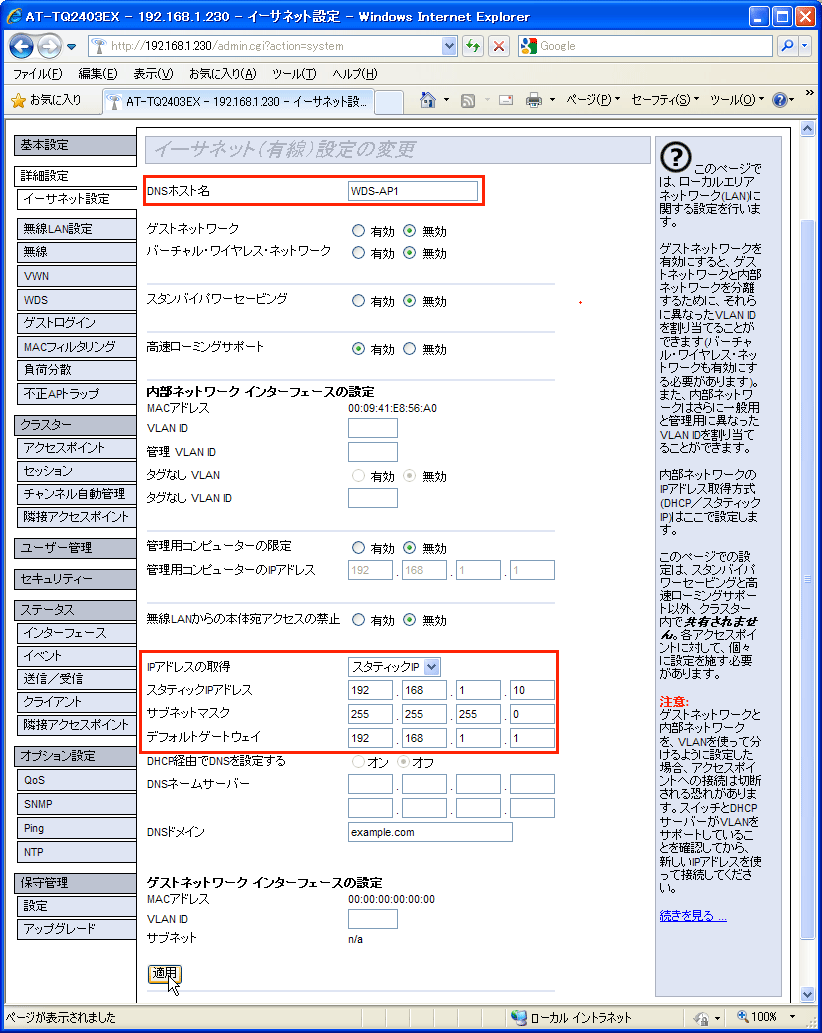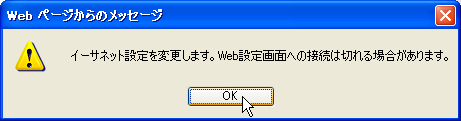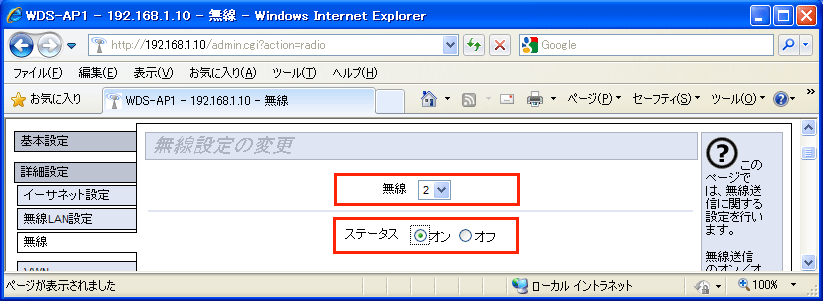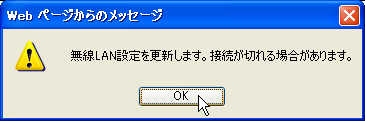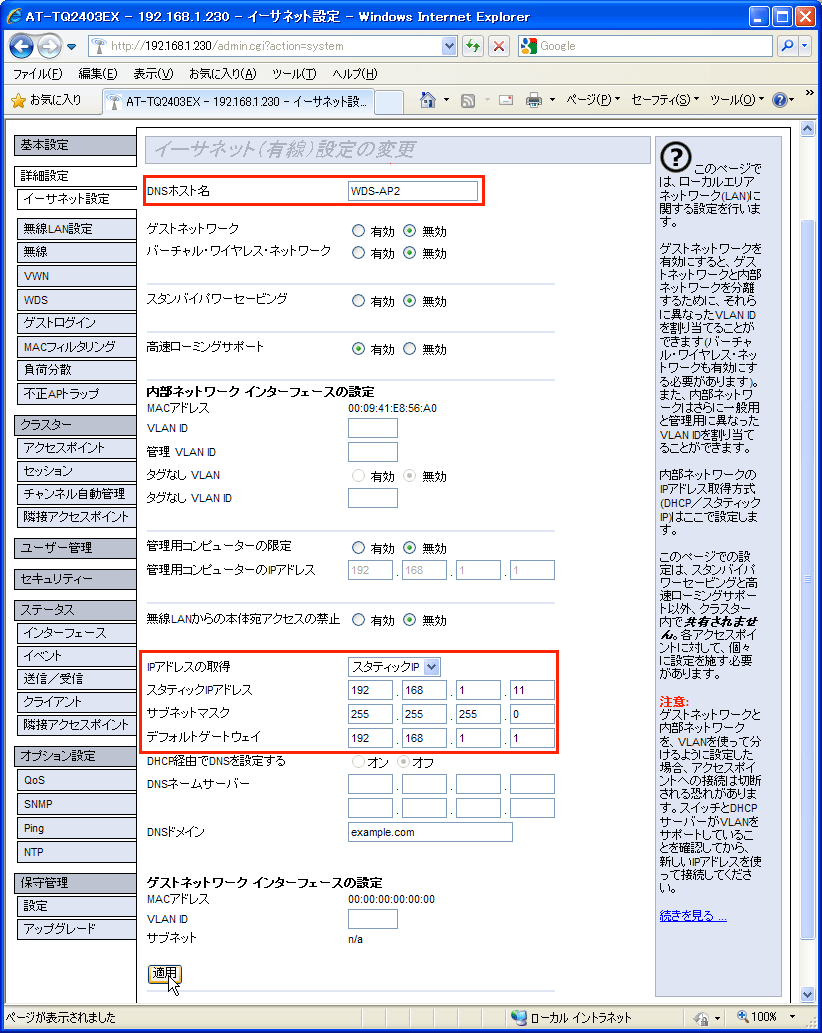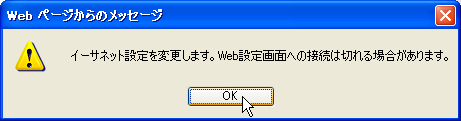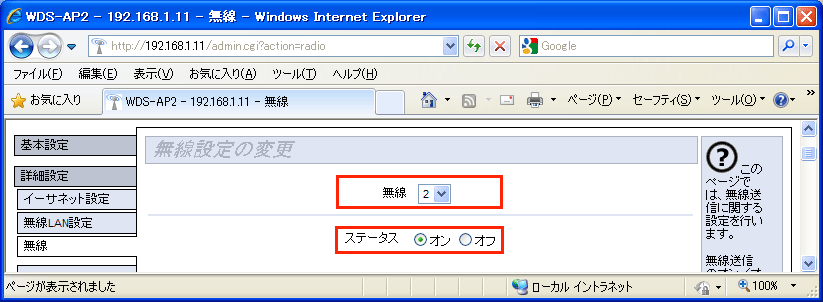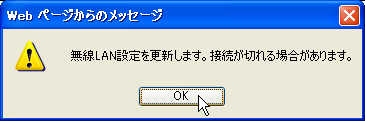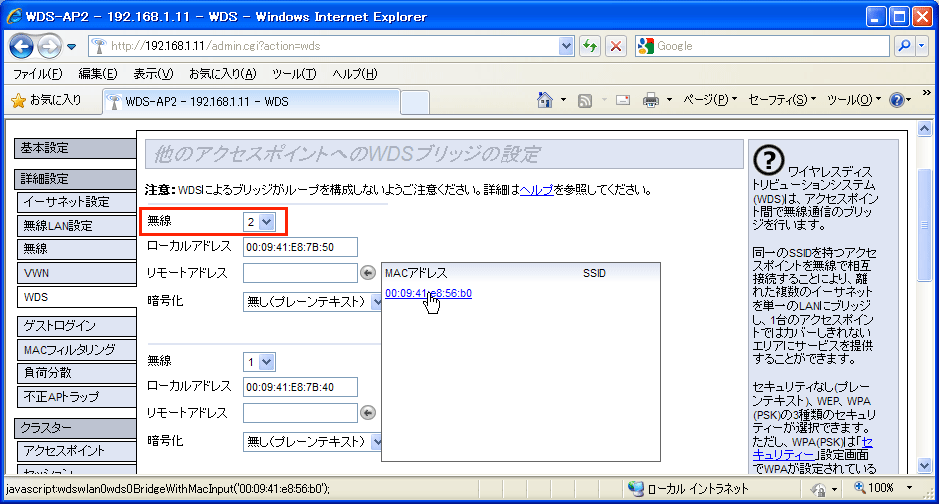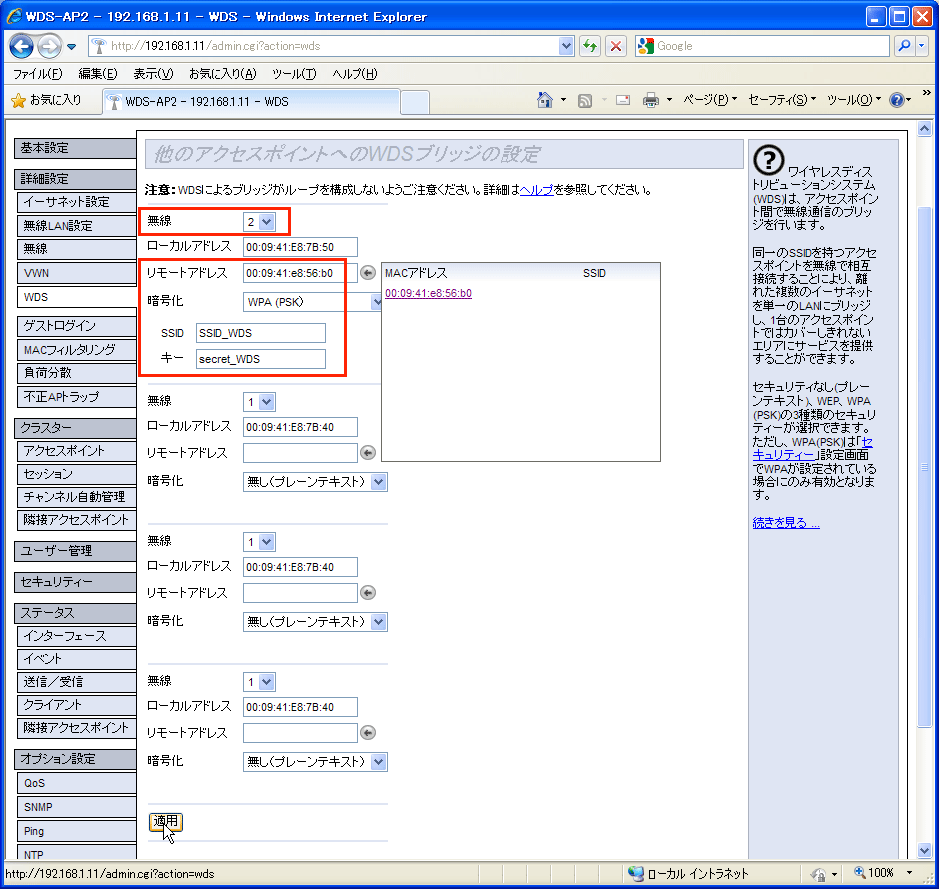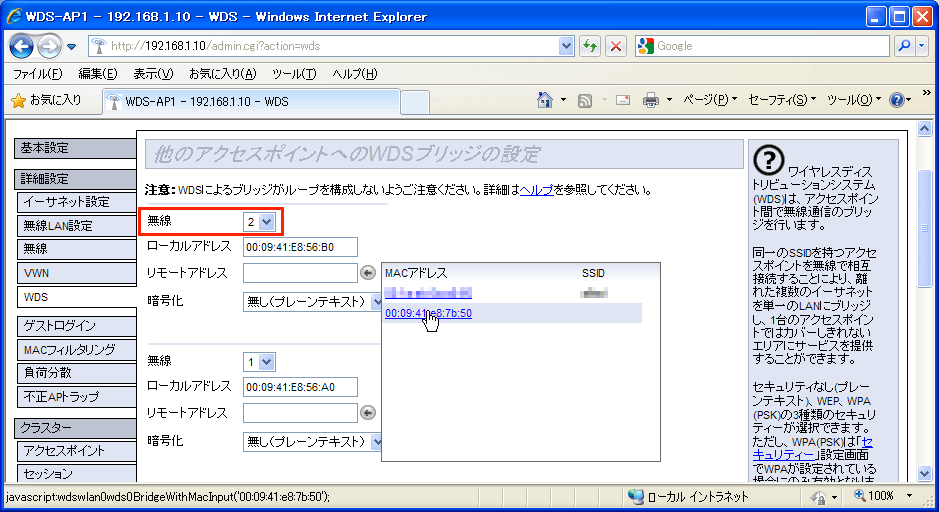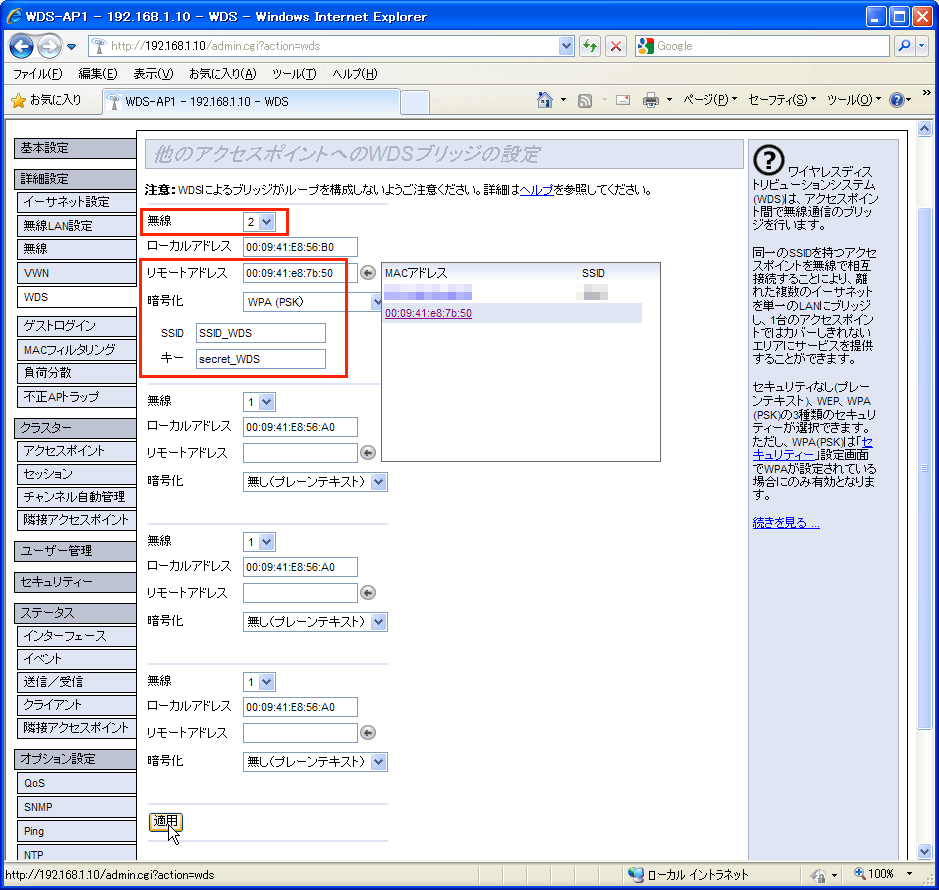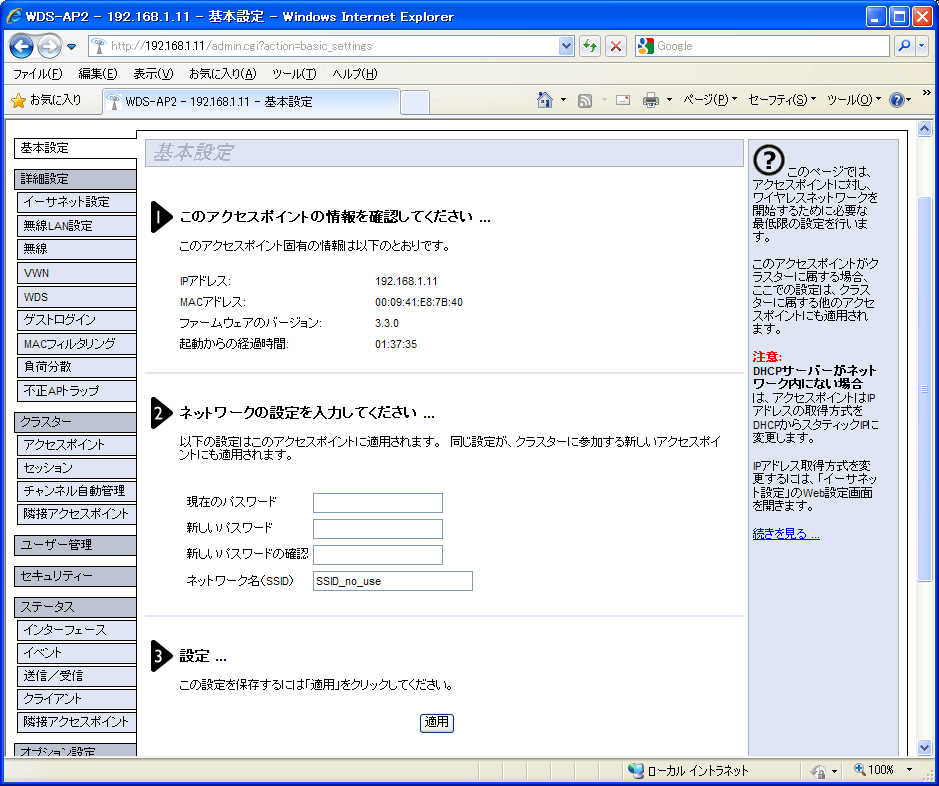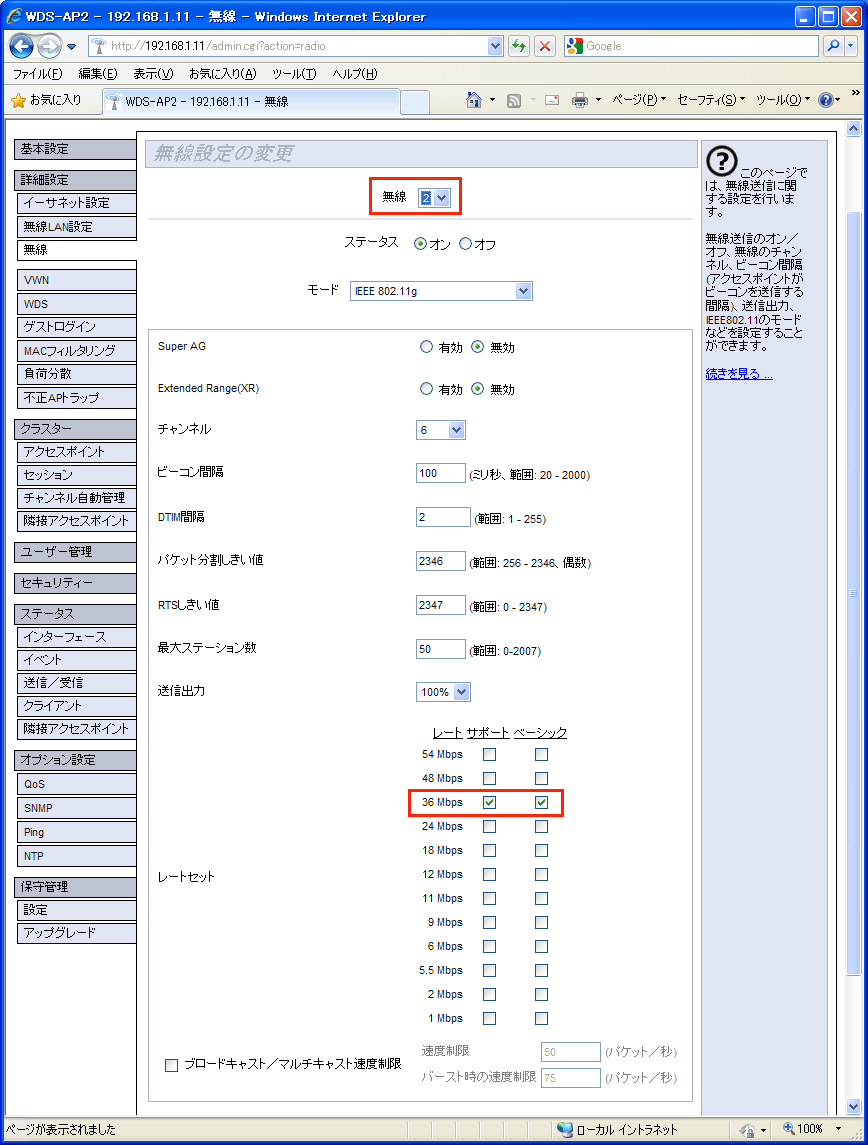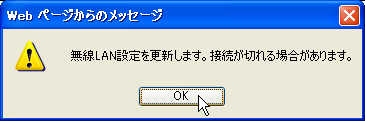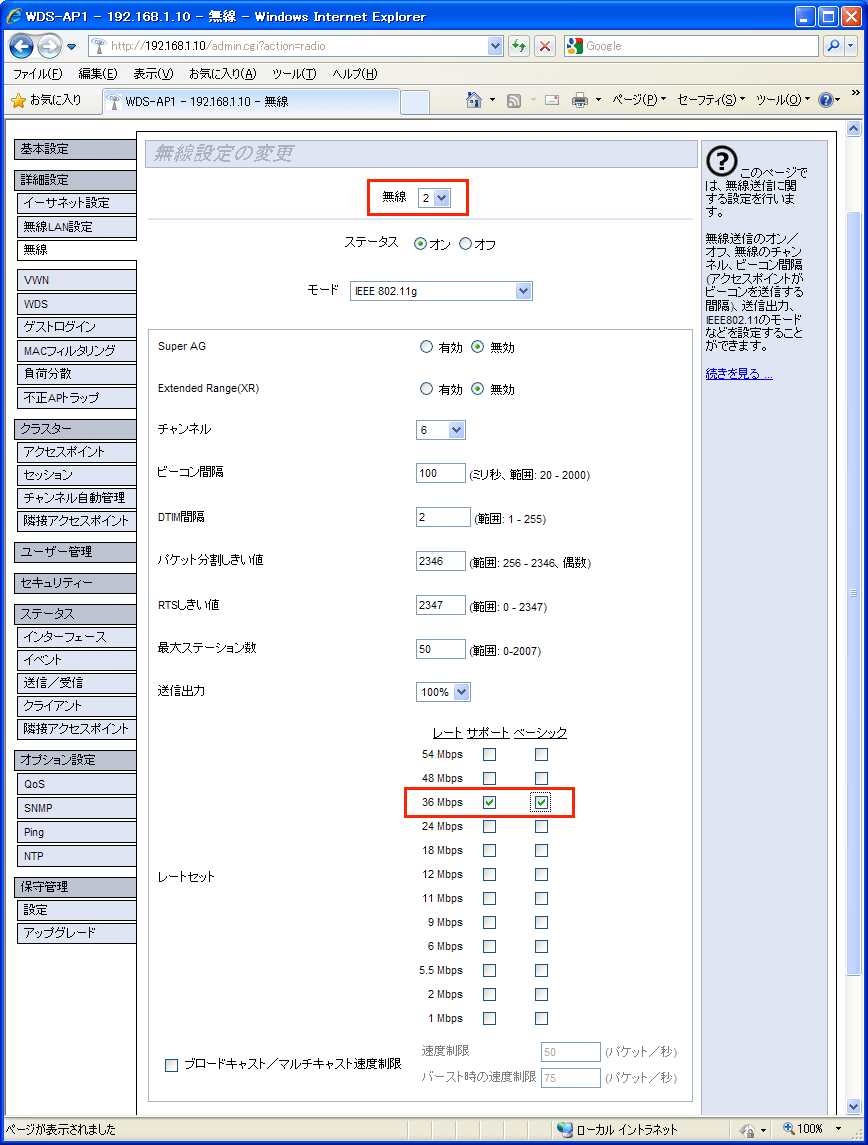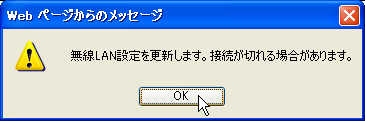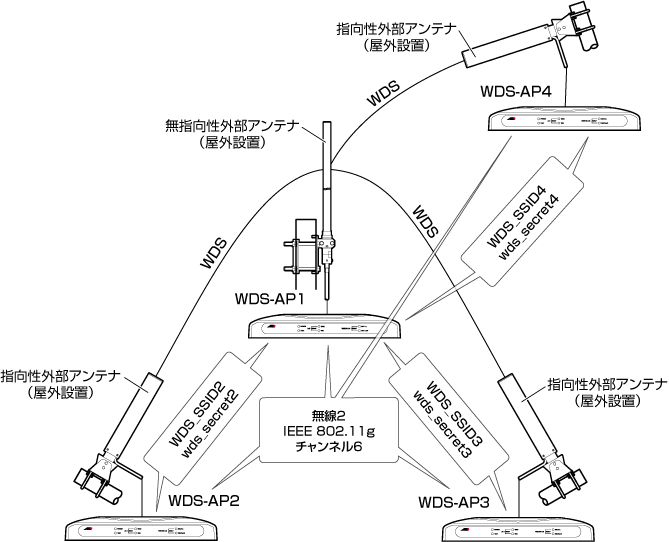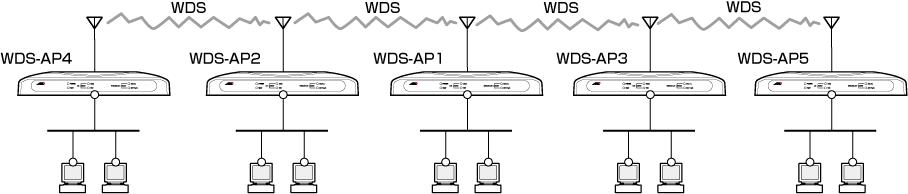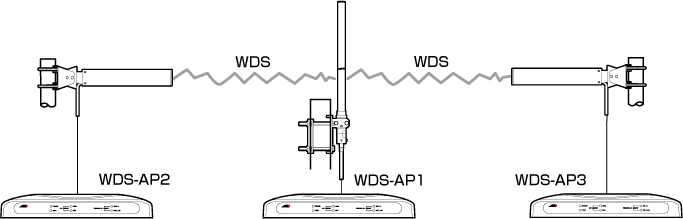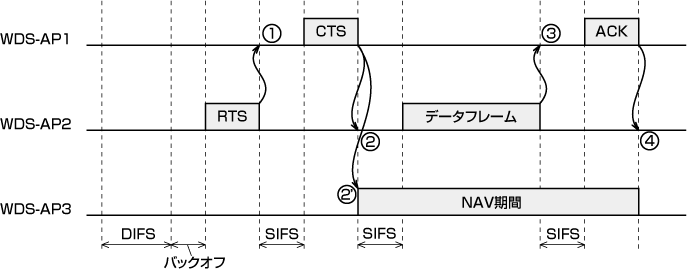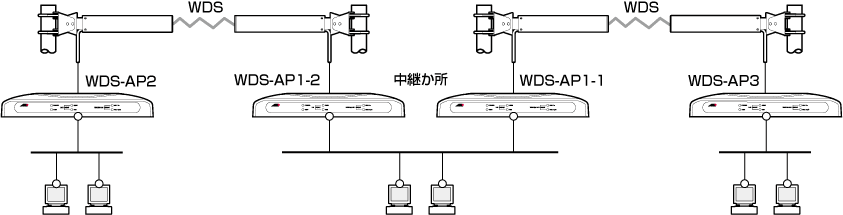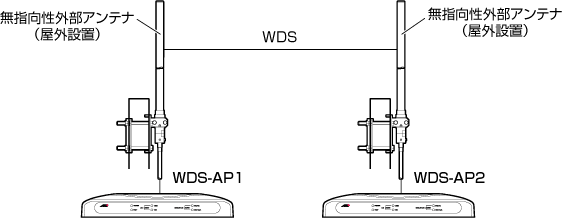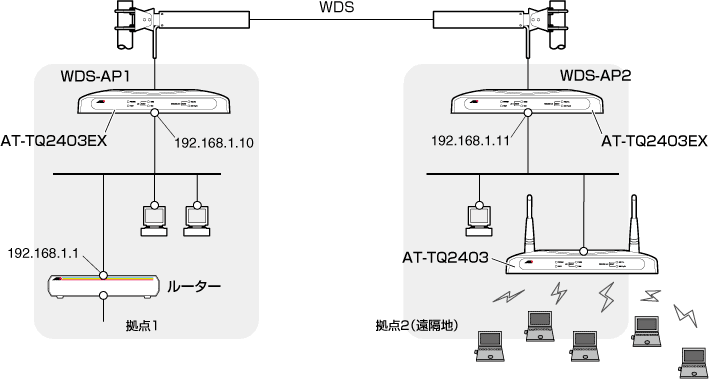[index]
AT-TQ2403EX リファレンスマニュアル 3.4
設定例/WDSでLAN間をブリッジする
- 準備
- 無線リンク設計ツール
- 拠点1の設定
- 本製品の設定画面を開く(拠点1・2共通)
- 管理者パスワードを変更する(拠点1・2共通)
- セキュリティーを設定する(拠点1・2共通)
- モード・チャンネル・接続アンテナ数・SSIDを設定する(拠点1・2共通)
- アクセスポイントの検出を有効にする(拠点1・2共通)
- DNSホスト名とIPアドレスを設定する
- 無線電波の送受信を開始する
- 拠点2の設定
- DNSホスト名とIPアドレスを設定する
- 無線電波の送受信を開始する
- 拠点2のWDSを設定する
- 拠点1のWDSを設定する
- 備考
- ループを作らない
- レートを固定する
- 3拠点以上のWDS接続
- スター型
- 多段接続(数珠繋ぎ)
- 隠れ端末
- 多段接続のパフォーマンスの改善
- 無指向性屋外アンテナによる拠点間の接続
- WDS接続を行っている拠点における無線接続サービスの提供
WDS(Wireless Distribution System)を使用すれば、無線通信でLAN間(アクセスポイント間)を接続(ブリッジ)することができます。有線でLAN間を接続できないような場合に便利です。
ここでは、下記の構成を仮定します。
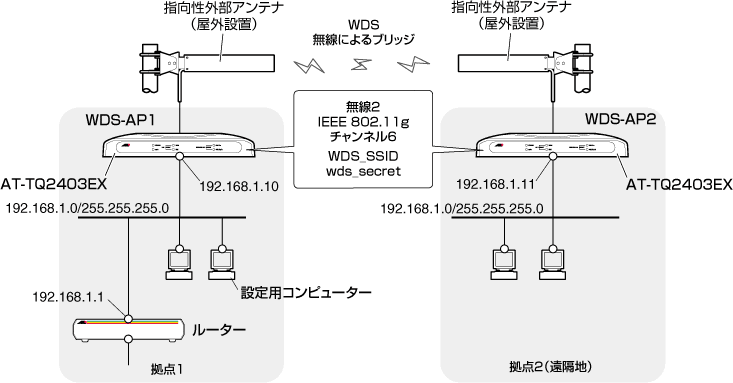
WDSは、下記の制限があります。
- VWN(バーチャル・ワイヤレス・ネットワーク)、ゲストネットワークとの併用はできません。
WDSと下記の機能の併用はお勧めいたしません。
- 無線クライアントに対する接続サービスの提供
- クラスター機能
本製品で屋外の通信を行うためには、下記の制限があります。
- 無線1(IEEE 802.11a、W52/W53)は使用できません。IEEE 802.11a(W52/W53)は屋外での使用が法律により禁止されています。
- 無線2のチャンネル14(IEEE 802.11b)は使用できません。チャンネル14は外部アンテナでの使用が法律により禁止されています。
無線リンク設計ツールは、2拠点間の無線リンクをシミュレートするツールです。「伝送距離」「データレート」「アンテナ種類」、「延長用同軸」の本数を入力することにより、無線リンクが可能か否か、またその余裕度などを知ることができます。各アンテナの指向特性(半値角)については、「ユーザーマニュアル」/「A.2 仕様」/「アンテナ仕様」を参照してください。
本章「備考」「レートを固定する」に関連情報があります。
Note
- 「延長用同軸」の「変換ケーブル」は「アンテナコネクター変換ケーブル」を指します。使用本数は常に1となります。
Note
- AT-TQ0207J(27素子八木)には、AT-TQ0062(10m同軸)が付属しています。付属のAT-TQ0062の損失はあらかじめAT-TQ0207Jのアンテナ利得に含まれておりますので、「延長用同軸」として加算しないでください。

拠点1から設定を始めます。
- 本製品に電源を入れ、設定用コンピューターとUTPケーブルで接続します。
Note
- 設定の間はアンテナをつながなくても構いません。拠点1、2の本製品を近接して置くことによりWDSの設定が可能です。
Note
- 本製品の10BASE-T/100BASE-TXポートは、MDI/MDI-X自動認識機能を持つため、スイッチを介さず直接コンピューターを接続できます。
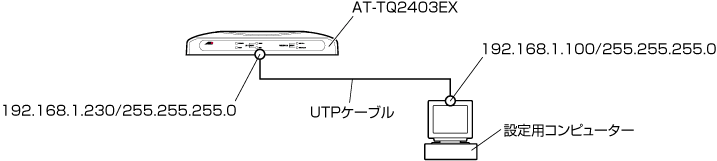
- Internet Explorerを使用して「192.168.1.230」にアクセスします。
Note
- コンピューターのIPアドレスは192.168.1.100/255.255.255.0など、本製品と同じネットワークに設定しておく必要があります。詳しくは、「設定画面へのアクセス」/「設定の準備」を参照してください。
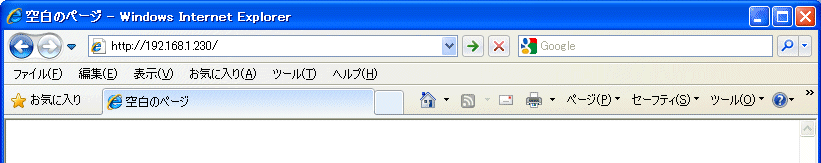
- ユーザー名「manager」、パスワード「friend」でログインします。
Note
- 本製品のご購入時(デフォルト)におけるパスワードは「friend」です。
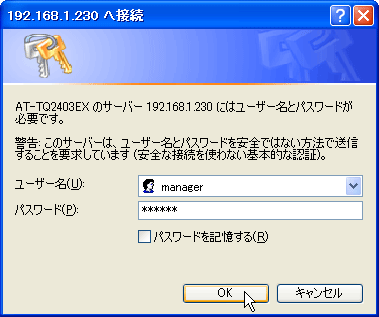
- 「基本設定」画面が開きます。
Note
- 表示の初期設定は、「ナビゲーション: ドロップダウンメニュー」となっています。表示の設定変更については「設定画面へのアクセス」/「ナビゲーション」を参照してください。以下の説明では「垂直タブ」を使用します。
Note
- 「基本設定」画面が開けないときはコンピューターのIPアドレスやプロキシーの設定などのネットワーク設定を確認してください。
- 「基本設定」画面を開きます。
- 「現在のパスワード」に「friend」と入力します。
- 「新しいパスワード」「新しいパスワードの確認」に新たな管理者パスワードを設定します。
- 「適用」ボタンをクリックします。
Note
- 本製品の設定画面にアクセスするためのパスワードを設定し、悪意のあるユーザーが本製品に対して不正にアクセスすることを防ぎます。パスワードは、8文字以内の「スペース " $ : < > ' & *」を除く半角英数記号が使用できます。不正に変更されることを防ぐために、管理者以外には類推しにくい管理者名、パスワードを設定しましょう。
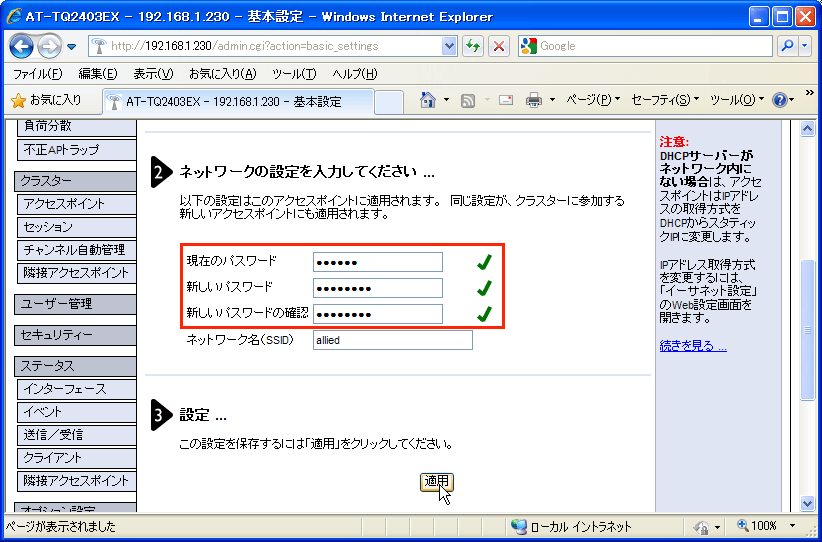
WDSの暗号として「WPA(PSK)」を使用するために、「セキュリティー」画面で「WPAパーソナル」を選択します。本製品はWDS専用として動作させ、無線クライアントに接続サービスを提供しません(「キー」をユーザーに公開しません)。
Note
- WDSの「暗号化」で「WPA(PSK)」を使用する場合、「セキュリティー」画面の「WPAパーソナル」または「WPAエンタープライズ」の「暗号スイート」のチェックボックスの設定(チェックの組み合わせ)は、WDSで接続するもの同士、完全に同一となるようにしてください。設定が異なっていると、WDS接続ができません。
- 「セキュリティー」をクリックします。
- パスワード入力を求める画面が表示されます。変更後の管理者パスワードを入力して、「OK」ボタンをクリックしてください。
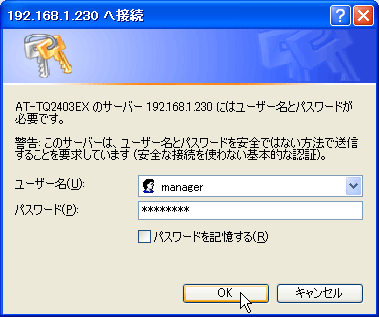
- 「SSIDのブロードキャスト」はチェックを入れません(デフォルト)。
- 「モード」を「WPAパーソナル」にします。
- 「WPAバージョン」は、「WPA2」のみにチェックをつけます(「WPA」のチェックを外します)。
- 「暗号スイート」は、「TKIP」のチェックを外し、「CCMP(AES)」にチェックをつけます。
- 「適用」ボタンをクリックし、設定を保存します。
Note
- 「詳細設定」/「MACフィルタリング」画面により、デフォルトでは無線クライアントのすべての接続が禁止されています。
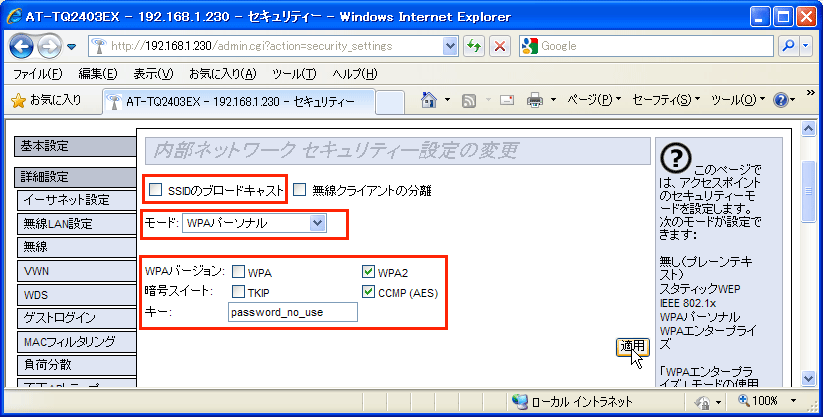
| モード・チャンネル・接続アンテナ数・SSIDを設定する(拠点1・2共通) |
- 「詳細設定」/「無線LAN設定」画面を開きます。
- 「無線インターフェース2」の「モード」「チャンネル」を「IEEE 802.11g」「6」に設定します(デフォルト)。
Note
- チャンネルで「Auto」を選択しないでください。WDSで接続するアクセスポイントのチャンネルは固定されている必要があります。
Note
- 無線2のチャンネル14(無線2、IEEE 802.11b)は外部アンテナでの使用が禁止されています。外部アンテナを使用する場合は、「14」以外のチャンネルに設定してください。
- 「長距離無線設定」の「接続アンテナ数」で「1本」を選択します(デフォルト)。
Note
- 「1本」のみが選択可能です。アンテナは「ANT1」端子に接続します。
Note
- 「長距離無線設定」はAT-TQ2403EXのみが持つ設定項目です。AT-TQ2403にはありません。
- 「内部ネットワーク設定」の「SSID」を設定します。ここでは「SSID_no_use」と入力しています。
- 「無線インターフェース2」の「MACアドレス」を記録しておきます。この情報をWDSの設定で使用します。
- 「適用」ボタンをクリックしてください。
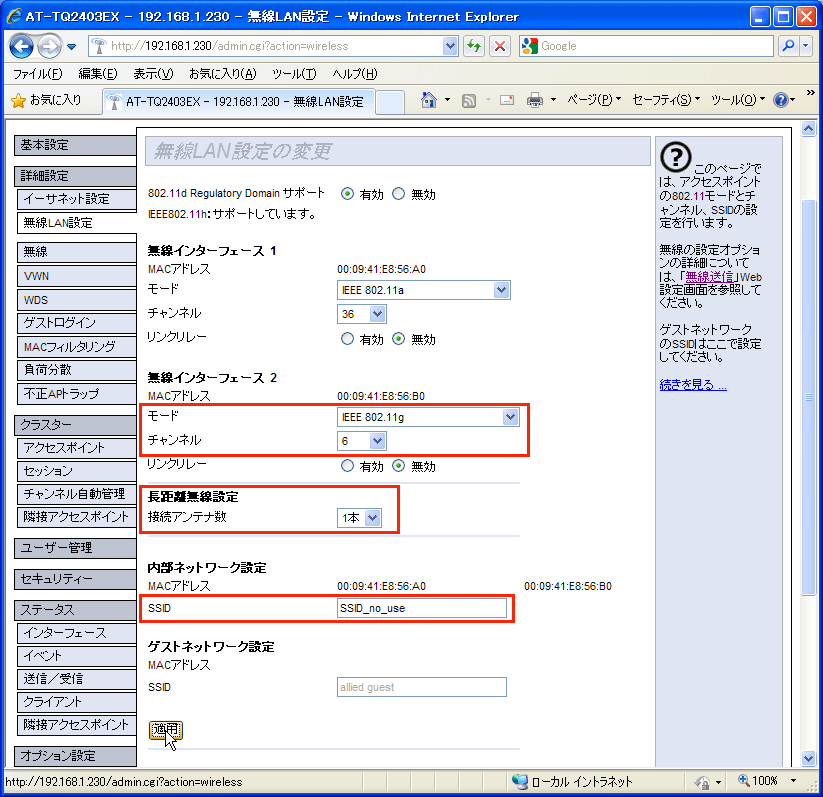
- 「OK」ボタンをクリックします。
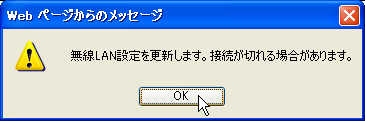
| アクセスポイントの検出を有効にする(拠点1・2共通) |
- 「ステータス」/「隣接アクセスポイント」画面を開きます。
- 「アクセスポイントの検出」の「有効」を選択します。
Note
- これを有効にしておくと、WDSの接続相手の設定が容易になります。
- 「適用」ボタンをクリックしてください。
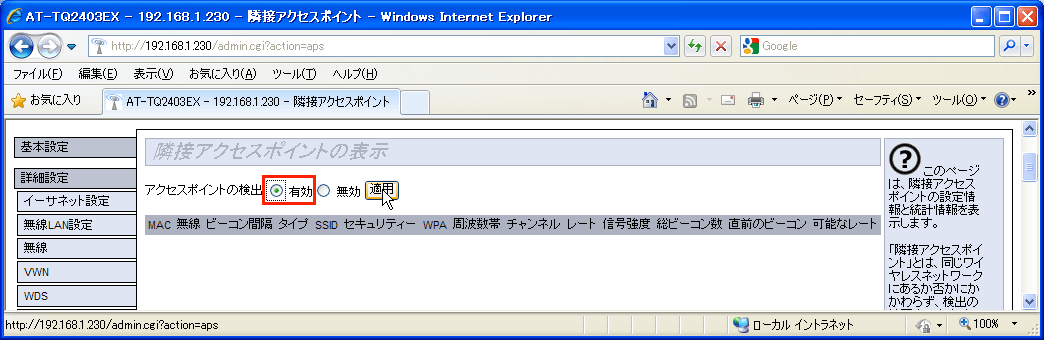
- 「詳細設定」/「イーサネット設定」画面を開きます。
- 管理をしやすくするために「DNSホスト名」に「WDS-AP1」を入力します。この名前はWebブラウザーのタイトルバーに表示されます。
- 「IPアドレスの取得」を「スタティックIP」にします。
「スタティックIPアドレス」「サブネットマスク」「デフォルトゲートウェイ」を設定します。
ここでは、それぞれ「192.168.1.10」「255.255.255.0」「192.168.1.1」を設定しています。
- 「適用」ボタンをクリックし、設定を保存します。
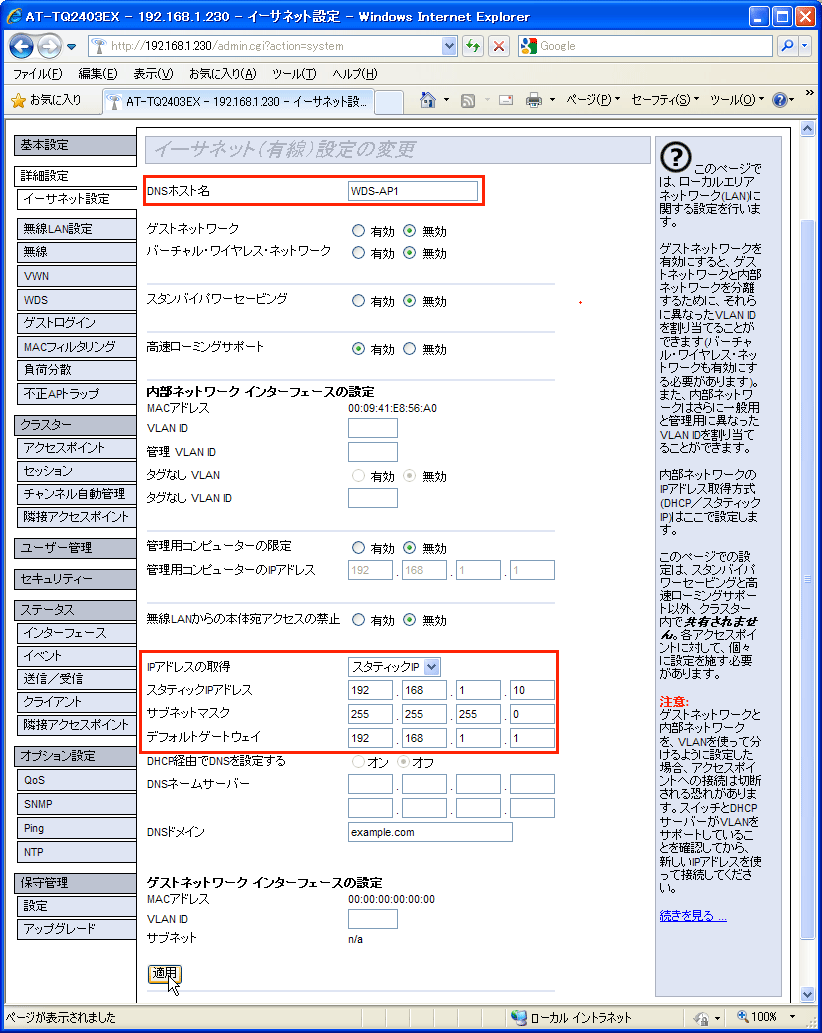
- 「OK」ボタンをクリックしてください。Webブラウザーとの接続が切断されます。
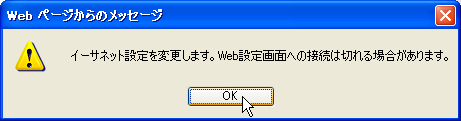
Note
- IPアドレスを変更すると、ナビゲーションが「ドロップダウンメニュー」に戻ります。変更後のIPアドレスでナビゲーションを再設定してください。詳しくは、「設定画面へのアクセス」/「ナビゲーション」を参照してください。
- IPアドレスの変更後、30秒くらい待って、変更後のIPアドレス「192.168.1.10」にアクセスし、設定画面にログインします。
- 「詳細設定」/「無線」画面を開きます。
- 「無線」で「2」を選択し、「ステータス」をオンにします。これにより、無線2の無線電波の送受信が開始されます。
Note
- 無線1(IEEE 802.11a、W52/W53)は屋外での使用が禁止されています。外部アンテナを使用する場合は、「無線1」の「ステータス」を「オフ」に設定してください。
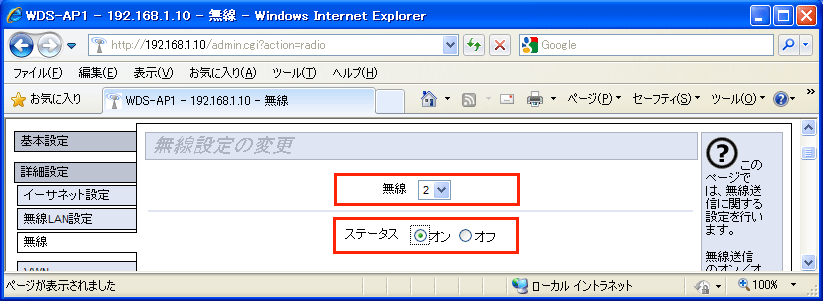
- 「適用」ボタンをクリックします。

- 「OK」ボタンをクリックします。
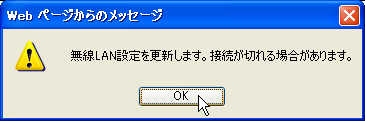
続いて、設定用コンピューターを拠点2用の本製品につなぎ替え、拠点1の以下の項と同じように設定します。
- 本製品の設定画面を開く
- 管理者パスワードを変更する
- セキュリティーを設定する
- モード・チャンネル・接続アンテナ数・SSIDを設定する
- アクセスポイントの検出を有効にする
Note
- 拠点2の本製品につなぎ替えたたとき、Web設定画面にアクセスできない場合は、設定用コンピューターでコマンドプロンプトを開き「arp -d 192.168.1.230」を入力してARPキャッシュをクリアしてください。

- 「詳細設定」/「イーサネット設定」画面を開きます。
- 管理をしやすくするために「DNSホスト名」に「WDS-AP2」を入力します。この名前はWebブラウザーのタイトルバーに表示されます。
- 「IPアドレスの取得」を「スタティックIP」にします。
「スタティックIPアドレス」「サブネットマスク」「デフォルトゲートウェイ」を設定します。
ここでは、それぞれ「192.168.1.11」「255.255.255.0」「192.168.1.1」を設定しています。
- 「適用」ボタンをクリックし、設定を保存します。
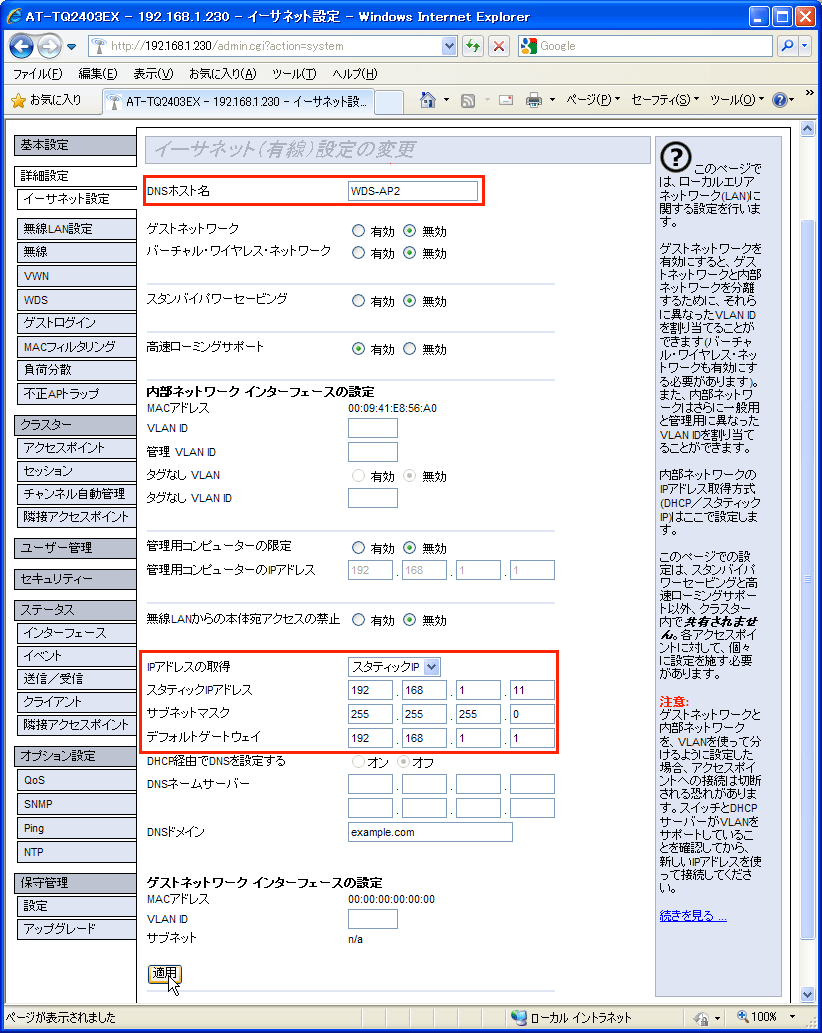
- 「OK」ボタンをクリックしてください。Webブラウザーとの接続が切断されます。
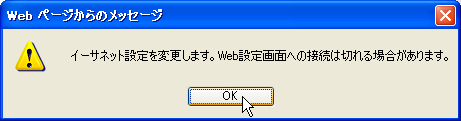
Note
- IPアドレスを変更すると、ナビゲーションが「ドロップダウンメニュー」に戻ります。変更後のIPアドレスでナビゲーションを再設定してください。詳しくは、「設定画面へのアクセス」/「ナビゲーション」を参照してください。
- IPアドレスの変更後、30秒くらい待って、変更後のIPアドレス「192.168.1.11」にアクセスし、設定画面にログインします。
- 「詳細設定」/「無線」画面を開きます。
- 「無線」で「2」を選択し、「ステータス」をオンにします。これにより、無線2の無線電波の送受信が開始されます。
Note
- 無線1(IEEE 802.11a、W52/W53)は屋外での使用が禁止されています。外部アンテナを使用する場合は、「無線1」の「ステータス」を「オフ」に設定してください。
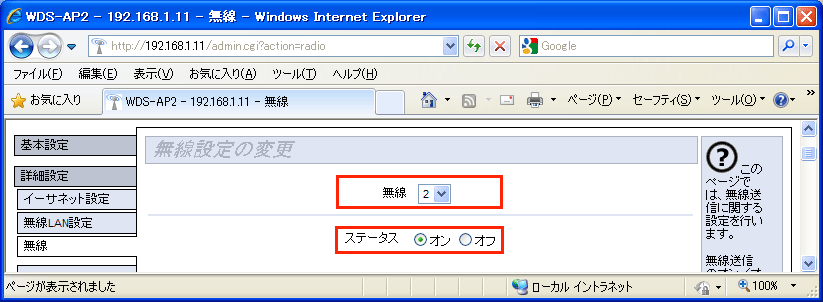
- 「適用」ボタンをクリックします。

- 「OK」ボタンをクリックします。
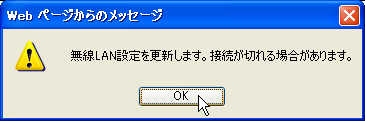
- 引き続き、拠点2のWDSを設定します。

- 「詳細設定」/「WDS」画面を開きます。
- 「無線」で「2」を選択します。
- 「リモートアドレス」の右の「←」をクリックするとプルダウンメニューが現れます。メニューからWDSの接続相手となる拠点1の本製品のMACアドレスをクリックします。クリックしたMACアドレスが「リモートアドレス」に入力されます。
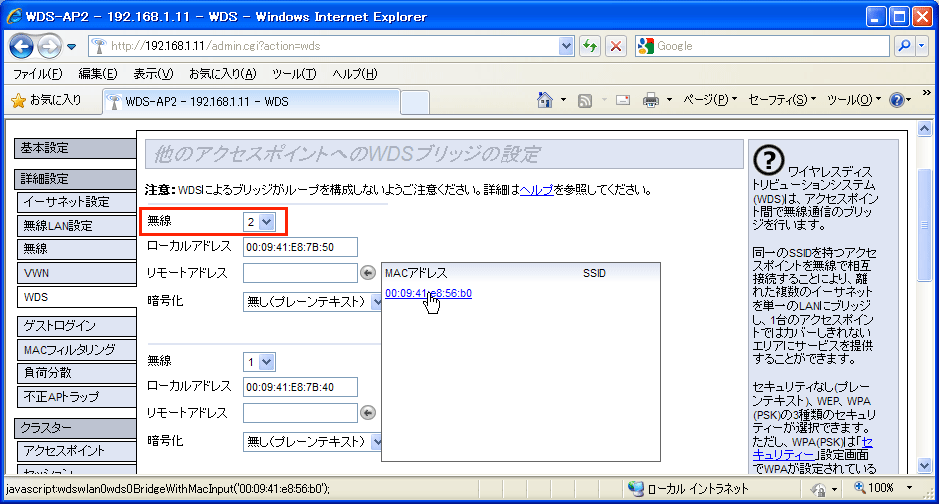
- 「暗号化」で「WPA(PSK)」を選択します。
- 「SSID」「キー」を設定します。ここではそれぞれ「SSID_WDS」「secret_WDS」を入力しています。
Note
- WDSで接続するもの同士は同一の「SSID」「キー」を設定します。
- 「適用」ボタンをクリックします。
Note
- WDS接続の解除は、「リモートアドレス」を削除し、「適用」ボタンをクリックします。接続相手に施した設定に対しても、同様にして削除します。
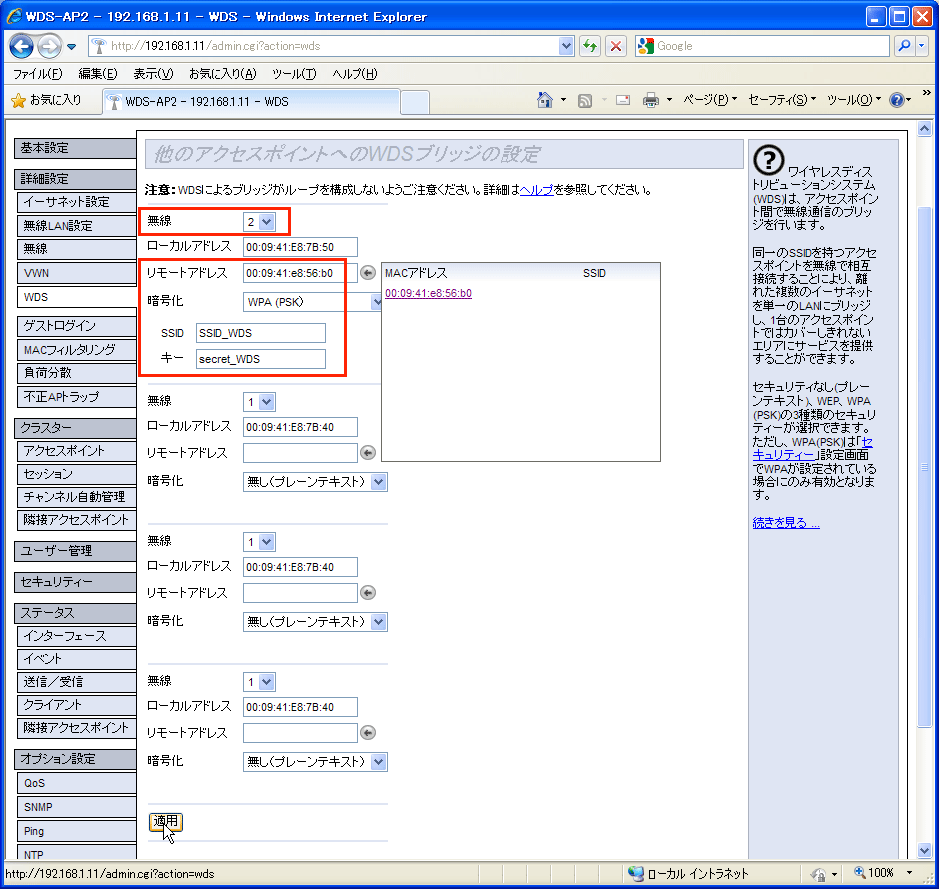
- 拠点1のWDSを設定します。設定用コンピューターを拠点1の本製品につなぎ替えます。

- 192.168.1.10 にアクセスし、「詳細設定」/「WDS」画面を開きます。
- 「無線」で「2」を選択します。
- 「リモートアドレス」の右の「←」をクリックするとプルダウンメニューが現れます。メニューからWDSの接続相手となる拠点2の本製品のMACアドレスをクリックします。クリックしたMACアドレスが「リモートアドレス」に入力されます。
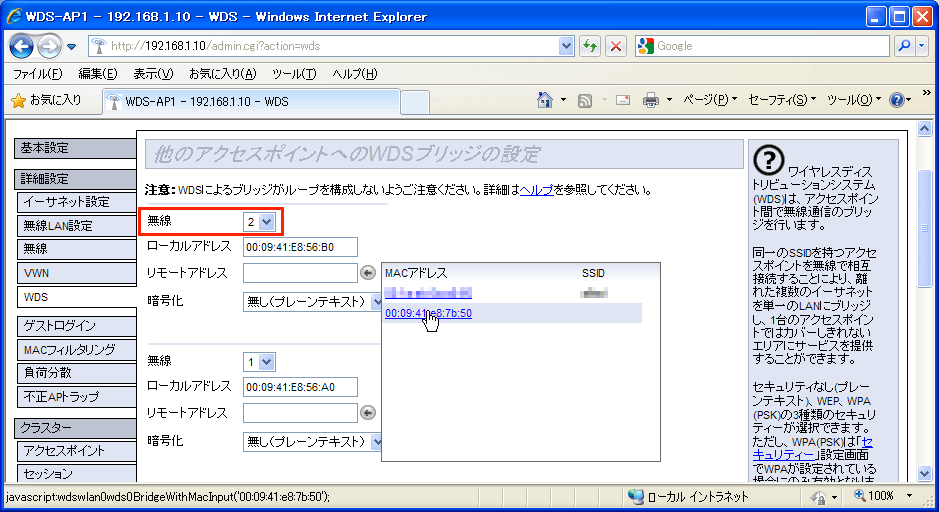
- 「暗号化」で「WPA(PSK)」を選択します。
- 「SSID」「キー」を設定します。ここではそれぞれ「SSID_WDS」「secret_WDS」を入力しています。
Note
- WDSで接続するもの同士は同一の「SSID」「キー」を設定します。
- 「適用」ボタンをクリックします。
Note
- WDS接続の解除は、「リモートアドレス」を削除し、「適用」ボタンをクリックします。接続相手に施した設定に対しても、同様にして削除します。
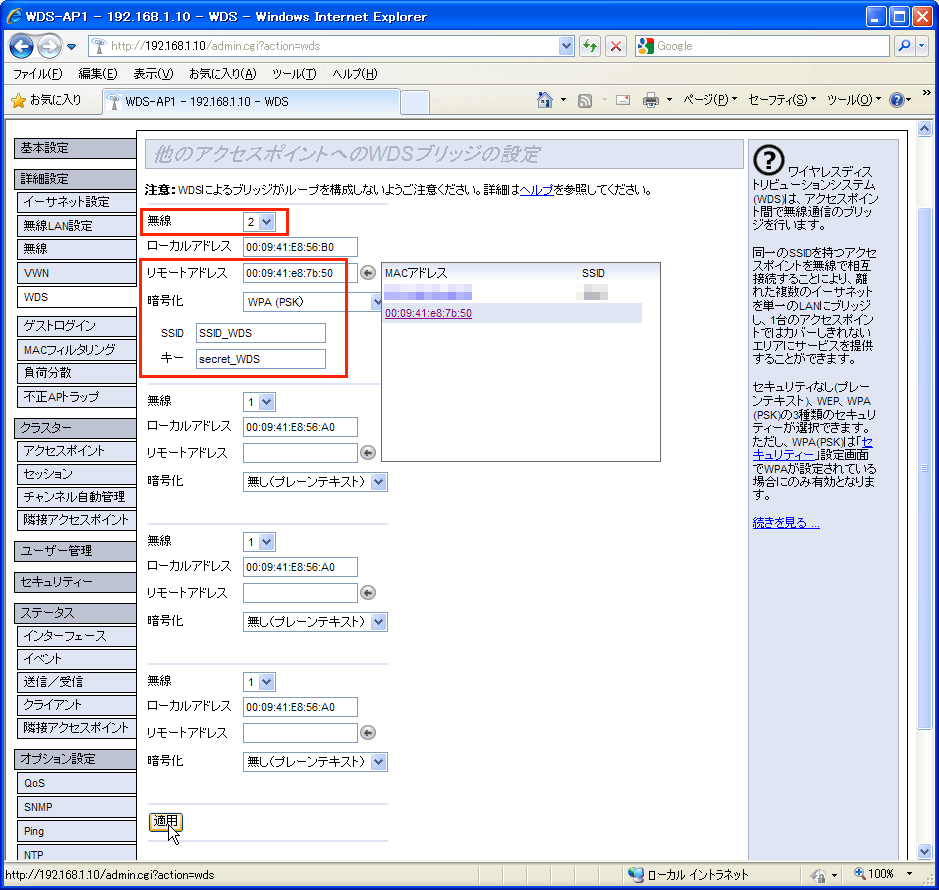
- 192.168.1.11 の設定画面にアクセスしてみます。表示されれば、WDS接続は成功しています。

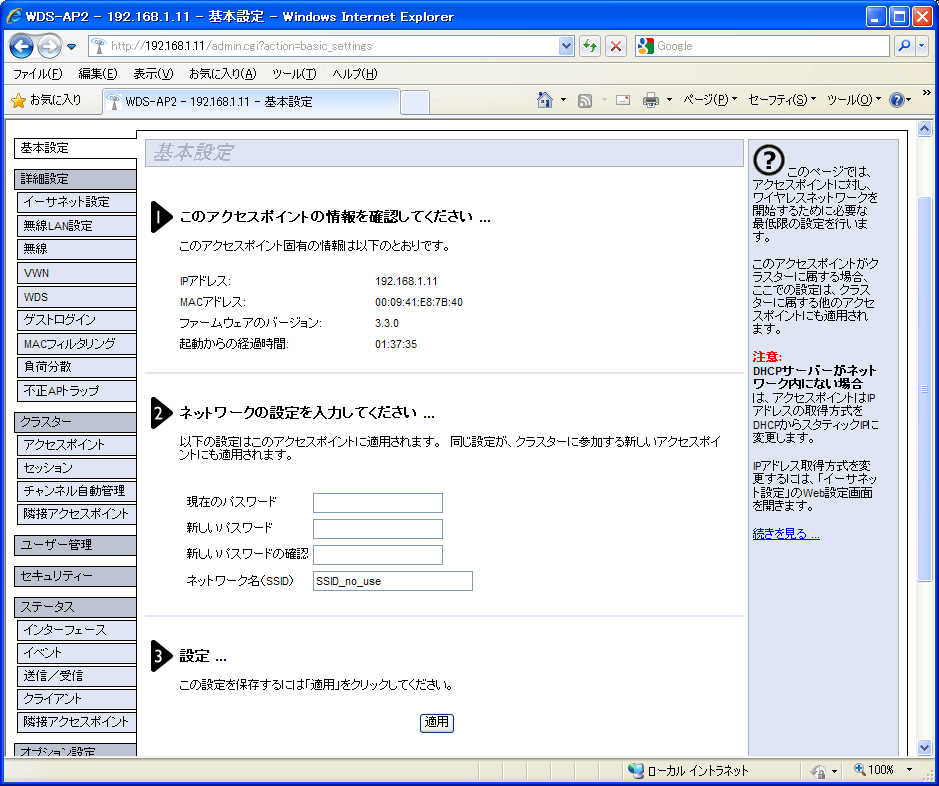
- 本製品を拠点1、2に設置し、ケーブル類を接続します。
Note
- 「ステータス」/「WDS」画面でWDSの接続状態を確認できます。
スイッチを使えば、設定の際に拠点1と2の本製品をいちいちつなぎ替えなくてもすむので便利ですが、最後のWDSの設定手順を実行するときは、本製品を1台ずつスイッチにつないで行ってください。

2拠点の両方の本製品をスイッチに接続した状態でWDSの設定が有効になると、WDSとイーサネットポートの間でループとなり、過大なトラフィックが発生します。

ご購入時において、レートは自動的に決定されるため、伝送距離によってはWDS経由の通信が不安定になることがあります。この場合、レートを固定することをお勧めします。固定するレートは、前述の「無線リンク設計ツール」を使用して決定してください。
例えば、レートを36Mbpsに固定する場合、サポート・レートセット、ベーシック・レートセットとも36Mbpsのみをチェックします。拠点1、拠点2の両方にこの設定を行います。
手順は下記のとおりです。
- 拠点2の本製品にログインし、「詳細設定」/「無線」画面を開きます。
- 「無線」で「2」を選択し、「レートセット」の「サポート」「ベーシック」とも「36Mbps」のみにチェックを入れます。
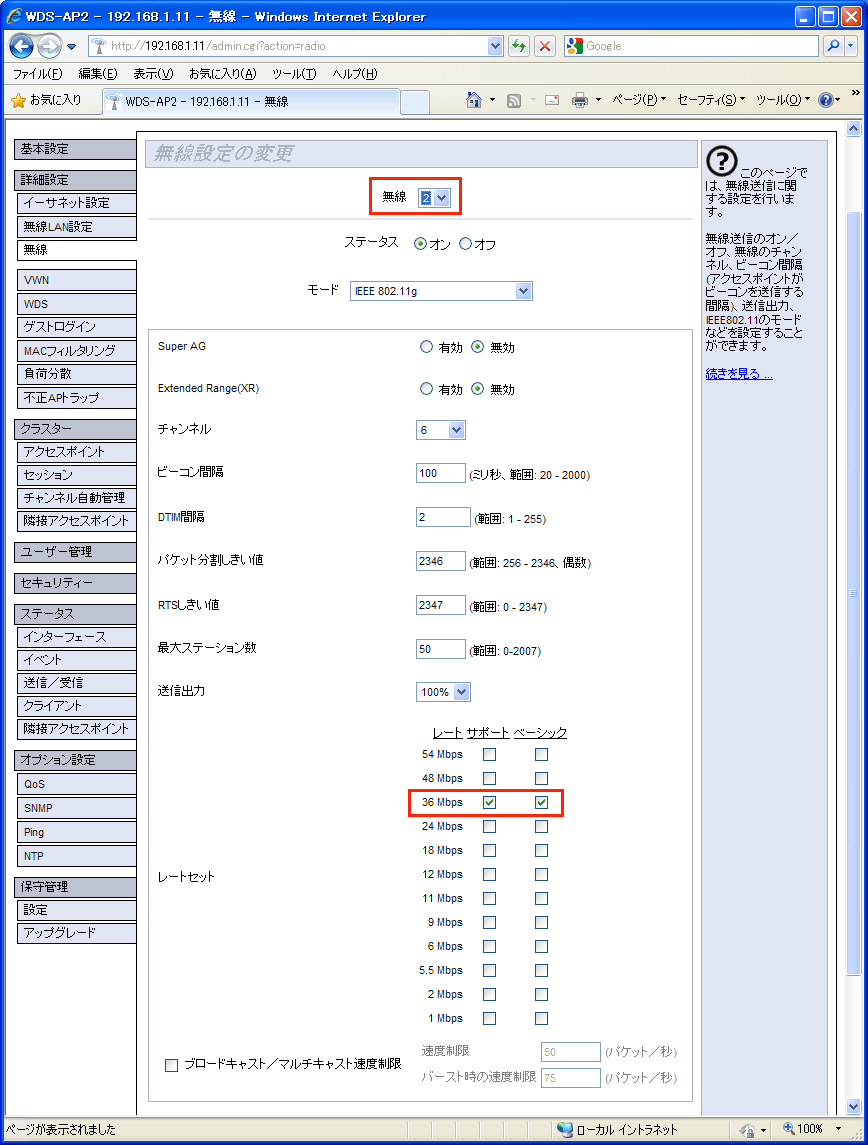
- 「適用」ボタンをクリックします。

- 「OK」ボタンをクリックします。
Note
- 拠点2のサポート・レートセットが拠点1のベーシック・レートセットを満たさなくなるのでWDS接続が切断します。拠点1、2両方のサポート・レートセット、ベーシック・レートセットを一致させたとき、WDS接続が戻ります。
Note
- WDS経由でこの設定を変更する場合、拠点2(遠隔地側)から行います。最初に拠点1側を変更してしまうと、WDS接続を再確立するためには拠点2のLANポートを使用して行わなければなりません。
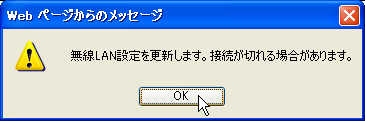
- 拠点1の本製品にログインし、「詳細設定」/「無線」画面を開きます。
- 「無線」で「2」を選択し、「レートセット」の「サポート」「ベーシック」とも「36Mbps」のみにチェックを入れます。
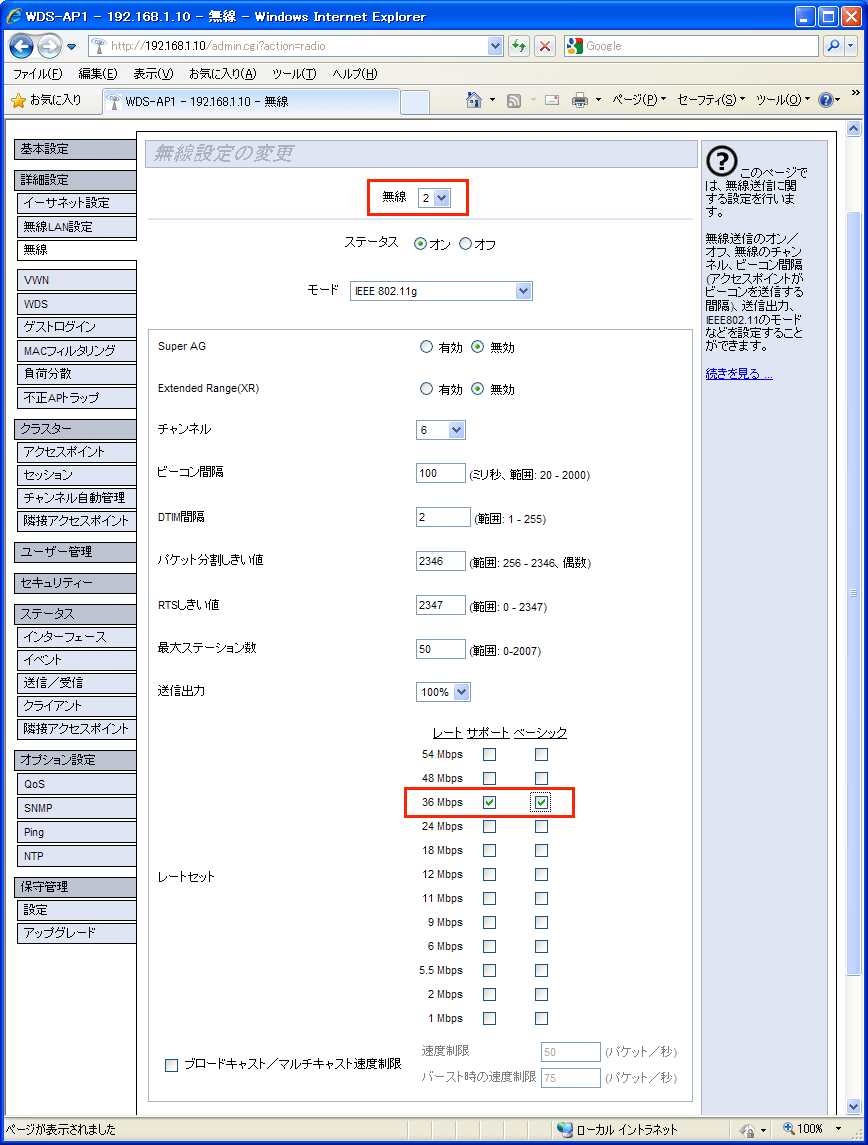
- 「適用」ボタンをクリックします。

- 「OK」ボタンをクリックします。
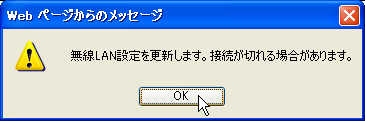
- WDS接続が再度確立します。WDS経由で拠点2の本製品にアクセスできるか確認します。
Note
- 何らかの理由でWDS接続が確立しない場合、拠点2の本製品にアクセスするためには、拠点2の本製品のLANポートを使用して行う必要があります。
3拠点以上のWDS接続における注意点を挙げます。
スター型
- 複数の接続を受ける拠点(例ではWDS-AP1)は、無指向性のアンテナを推奨します。接続拠点を増設する可能性がある場合は、あらかじめ考慮しておく必要があります。また、指向性アンテナを使用する場合は半値角に注意し配置してください。
Note
- 「ユーザーマニュアル」/「A.2 仕様」/「アンテナ仕様」を参照してください。
- モード、チャンネルは、すべての本製品で同一にします。
- WDSの「暗号化」「SSID」「キー」は、WDSで接続する本製品同士で同一にします。
- 「RTSしきい値」を調整してください。下記の例では、WDS-AP2、WDS-AP3、WDS-AP4でその調整が必要です。詳しくは、後述の「隠れ端末」を参照してください。
- 本製品は4台までWDS接続の設定ができます。しかしながら、WDS接続数は3台程度にすることをお勧めいたします。
下記に構成例を挙げます。
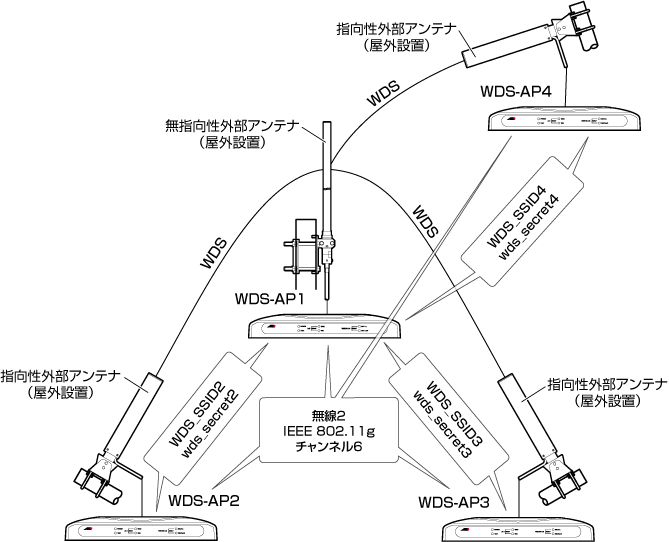
多段接続(数珠繋ぎ)
WDS接続は、次のように多段接続が可能です。
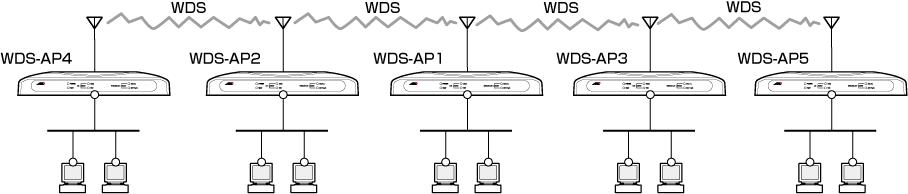
しかしながら、次のように2段までにすることをお勧めいたします。この構成は、前述のスター型のWDS-AP4が存在しない構成と同じです。
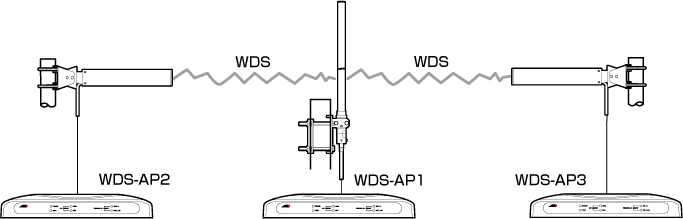
WDS-AP2からWDS-AP3へパケットを送ると2回転送が行われるためスループットは、対向の場合と比較して理論上50%以下になります。実際にはアプリケーションによって差がありますがFTPを使用した実測では30〜40%となります。
注意点は、スター型と同様です。
- WDS-AP1は、無指向性のアンテナを使用してください。
- モード、チャンネルは、すべての本製品で同一にします。
- WDSの「暗号化」「SSID」「キー」は、WDSで接続する本製品同士で同一にします。
- WDS-AP2、WDS-AP3で「RTSしきい値」を調整してください。詳しくは、次の「隠れ端末」を参照してください。
- 多段接続は2段(中継1回)までにすることをお勧めします。
隠れ端末
上記の2段接続の構成を例に説明します。
WDS-AP2の電波はWDS-AP3に届きません。同様に、WDS-AP3の電波もWDS-AP2に届きません。そのため、例えばWDS-AP2はWDS-AP3が送信したことを知ることができません。WDS-AP3が送信したことを知らずにWDS-AP2が送信するとWDS-AP1で衝突し、WDS-AP2やWDS-AP3はデータの再送が必要となります。
Note
- 端末同士が互いの電波の到達範囲外にあることを「互いに隠れている」と言います。そのような端末のことを「隠れ端末」と言います。
この問題の改善のためにRTS/CTSが使用されます。
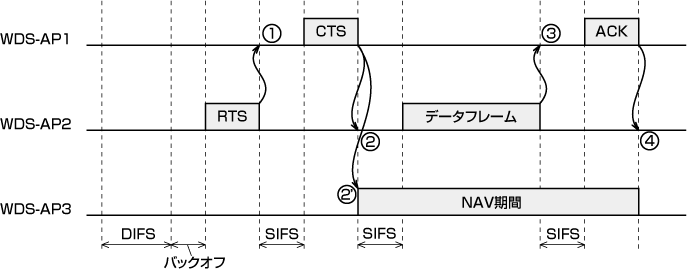
- WDS-AP2は、DIFSとバックオフの時間をキャリアセンスして、誰も送信していないことが確認できたらRTSをWDS-AP1に送信します。
Note
- RTS(Request to Send、送信要求)は、データ送信を事前に相手に知らせるメッセージです。
- WDS-AP1は、SIFSの時間を空けてCTSをWDS-AP2に返します。CTSは、無線回線を使用する予定期間の情報を持っています。CTSは、WDS-AP3も受信することができます。WDS-AP3は、これを参照し予定期間の間送信しません(NAV期間)。
Note
- CTS(Clear to Send、受信準備完了)は、RTSを受け取った側でデータ受信が可能であることを知らせるメッセージです。
Note
- SIFS<DIFSなので、RTSが正常に受信されると、待ち時間の短いSIFSによって、その後の送信は優先されます。
- WDS-AP2は、SIFSの時間を空けてデータフレームをWDS-AP1に送信します。
- データフレームが受信できたら、WDS-AP1はACKをWDS-AP2に返します。
WDS-AP2とWDS-AP3の送信がWDS-AP1で衝突する確率はフレームサイズが大きくなるに従って高くなるので、あるサイズを超える場合だけRTSを送信することによってこの状況を改善します。
これは、「詳細設定」/「無線」画面の「RTSしきい値」で設定できます。
「RTSしきい値」は、0〜2347の数値が設定できます。ご購入時には「2347」となっており、これはRTSを送信しません。RTSを送信する場合は、2347よりも小さな値を設定します。数値が大きすぎると効果が期待できません。数値が小さすぎると通信のスループットが下がります。
多段接続のパフォーマンスの改善
WDS接続の多段接続でスループットをあまり低下させたくない場合は、次のように中継か所に2台の本製品を設置し、イーサネットで接続してください。干渉を回避するため、各ペアの無線チャンネルはできるだけ離して設定してください。「RTSしきい値」の調整は不要です。
スループットの低下はアプリケーションによって差がありますが、遅延が増加するために中継1回につきFTPなどでは70〜80%程度になります。
この場合でも段数を増やすと干渉が増えたりパフォーマンスが低下するので推奨は3段(2回中継)までです。
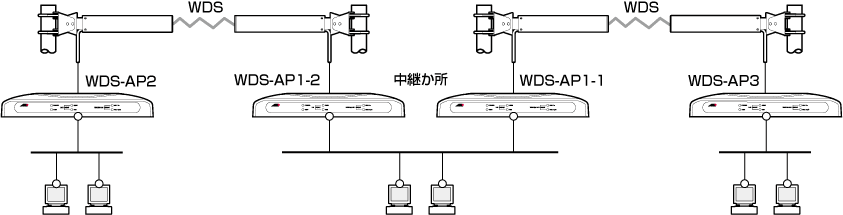
指向性外部アンテナを使用すれば、より長距離のLAN間接続が可能ですが、無線電波が充分に到達可能であれば(充分な無線通信速度が得られるのであれば)、無指向性外部アンテナを使用することができます。
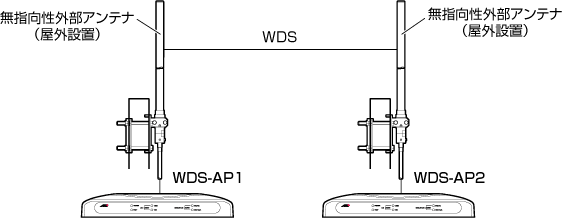
| WDS接続を行っている拠点における無線接続サービスの提供 |
WDS接続を行っている拠点で無線クライアントに対する接続サービスを提供する必要がある場合は、接続サービスのためのアクセスポイントを別途用意することをお勧めいたします。WDS接続を行っているアクセスポイントと無線接続サービスを提供しているアクセスポイントは異なったチャンネルを設定してください。
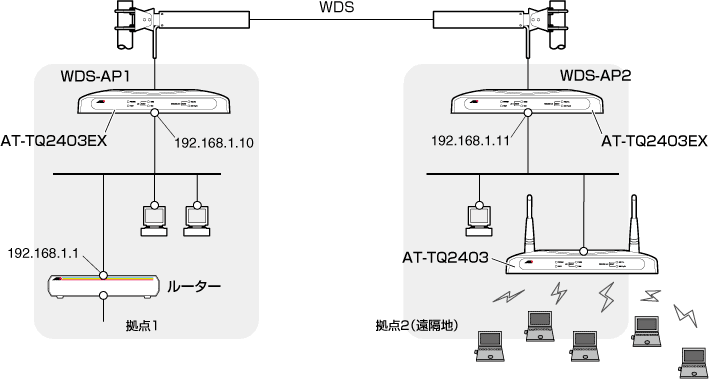
Copyright (C) 2011,2012 アライドテレシスホールディングス株式会社
PN: 613-001582 Rev.B