現在、国は自治体DXを推進するために、自治体が使用する情報システムの標準化を進めています。しかし、自治体の情報システム標準化が必要とされている背景や課題について、よくわからないという方もいるのではないでしょうか。この記事では、国が進めている自治体のシステム標準化の背景と目的、メリット、移行にあたっての課題を整理し解説します。
自治体システム標準化──国が推し進める自治体DX
自治体システム標準化とは、どのような取り組みなのでしょうか。
まずは、自治体システム標準化の概要や必要となった背景、目的について解説していきます。
自治体システム標準化とは
自治体システム標準化とは、自治体が使用する情報システムを、国が定める統一の基準や規格に準拠したシステムに移行する取り組みのことです。主に、デジタル庁や総務省が中心となって進められている国の政策の一つであり、自治体が重点的に取り組むべき事項とされています。標準化の対象は、住民記録や税、福祉など、住民の生活に直結する20業務が中心となっています。
システム標準化が必要となった背景
これまで自治体は、利便性の向上のために、独自に情報システムを構築・管理・カスタマイズして活用していました。
そのため、制度改正などで改修が必要となったとき、自治体が都度個別で対応しなければならず、人的にも財政的にも負担が大きくなっています。
住民サービスを向上させるための施策を政府が迅速に全国に普及させたくても、自治体ごとで情報システムに差異があることから、地域で施策の反映に差が生じてしまっている点も問題視されています。
特に、新型コロナウイルス感染症対策では、各自治体システムの連携が取れず、特別定額支給金の給付遅れなど様々な課題が発生しました。
また、政府は自治体が共有で利用できるクラウドサービスである「ガバメントクラウド」の使用を推し進めていますが、自治体への普及が進んでいません。これも、地域ごとに情報システムが異なっていることが原因の一つとして挙げられています。
国が掲げる自治体システム標準化の目的
こうした課題を解決するために、国は自治体システム標準化の目的として、各業務の効率化やコスト低減、セキュリティ強化、地域格差の是正を行い、住民サービスを向上させることを掲げています。
同時に、全国的に統一したデジタル基盤を整えることで、マイナンバー制度やデジタル活用を推進したいという狙いもあります。
こうした目的を達成するために、国は2021年に「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」を成立させました。
この法律では、自治体に対象となった20業務のシステム標準化を原則義務付け、移行目標期限を2025年度末までと定めています。また、ガバメントクラウドの利用についても、努力義務としました。
法律の施行に伴って、政府は2023年4月から2026年3月までを「移行支援期間」とし、自治体が円滑にシステム標準化できるよう様々な支援も行っています。
自治体のシステム標準化によって期待できるメリットとは?
システムが標準化されることによって、自治体は業務上で多数のメリットを得られることが期待されています。
具体的にどのようなメリットがあるか、詳しく見ていきましょう。
業務の軽減・効率化
自治体システム標準化を行うにあたり、これまでの業務が見直されることになります。
中にはテクノロジーによる自動化が図られたり、業務の簡略化が行われたりすることもあり、業務量が軽減・効率化する可能性が大きいと考えられています。
また、標準化基準の策定・変更は、国が行うことになります。そのため、制度の改正や突発的な行政需要への緊急対応に伴う自治体の個別対応も、これまでより削減されるでしょう。
こうした業務の軽減と効率化は、ICT業務の人材不足の解消につながることも期待できます。
コストが削減され、ベンダーも選びやすくなる
情報システムが全ての自治体で統一されると、個別のカスタマイズが不要となるため、カスタマイズにかかっていたコストも削減されると見込まれています。
ガバメントクラウドを利用した情報管理を行えば、印刷物や資料の保存場所に必要な費用も軽減されます。情報入手の時間や手間も短縮されるため、人件費の低減も期待できるでしょう。
さらに、個別カスタマイズが不要になることから、特定のベンダーに依存せざるを得ない状況も解消されるとされています。そのため、システムを更新する際に、より良い条件のシステム開発や革新的な技術を持つベンダーなど、選択肢が広がると考えられています。
他自治体情報システムとの円滑な連携
統一・標準化された情報システム間では、データ連携やシステム連携が容易となります。そのため、自治体をまたいだ連携や、税務や福祉などの部門間連携が円滑になるでしょう。
国と自治体間のデータ連携も円滑となるので、災害時における緊急対応もこれまで以上に迅速となるほか、全国ベースのデータ比較・分析も容易となることが考えられます。
住民サービスと利便性の向上
システム標準化によって業務の効率化やコストの削減が行われることで、結果的に浮いた人的リソースを住民サービスの充足に回すことが可能となります。
また、役所で直接提出が必要な書類や手続き、制度の交付・通知・決定までの日数も減少させる方向で改革が進んでいるので、自治体・住民ともに様々な負担が軽減されるでしょう。
オンライン申請の連携も拡充されるため、住民の利便性の向上も期待されています。
システム標準化で自治体が抱えている課題
システム標準化を行うことで様々なメリットが期待できる一方、自治体は移行にあたって多くの課題を抱えています。目標期限までの移行完了が困難だと考えられている自治体も少なくありません。
システム標準化を行う過程で自治体が抱えている課題について、詳しく見ていきましょう。
移行期限が迫っている
目標期限である2025年度末が迫る一方、移行が難航している自治体も少なくありません。
総務省やデジタル庁が発表した2025年8月時点 の全体進捗状況を見ると、約3割の自治体がシステムの標準化が作業中、あるいは未着手であることがわかります。このため、2025年度末までの移行達成は、困難であることが予想されています。
期限までに作業完了が困難である原因の一つには、こども・子育て政策やマイナンバー関連施策など、優先度が高い国策に関わるシステム改修も追加で発生しており、開発スケジュールを圧迫していることが挙げられています。
ベンダーが不足している
移行期限が迫っているために、各自治体で開発ベンダーの取り合いが発生している点も見逃せません。
自治体が開発ベンダーを確保できなかった場合、標準化が遅延する可能性があります。
また、現行ベンダーが撤退して代替の見込みがない、あるいは事業者のリソースがひっ迫して開発・移行作業が遅延している自治体もあります。
標準化移行への負担が大きい
システム標準化は、業務自体の見直しが必要となるため、人的にも財政的にも負担が大きい作業です。加えて、通常のデータ移動と新システム稼働においても、大きなコストがかかることが考えられます。
さらに、標準化対象事務の標準仕様書は何度も改訂されており、そのたびに業務の見直しの負担が増加しています。
こうした点も、2025年度までのシステム移行が困難である原因と言えるでしょう。
標準仕様書が自治体の規模や特性に合っていない部分がある
システム標準化を実現するために国が定めた標準仕様書は、自治体の規模や特性にマッチしていない部分もあります。
特に、規模が大きい政令指定都市は、特有の業務フローや条例について、標準仕様書に十分考慮されていないことが多いです。そのため、ほとんどの政令指定都市が期限までのシステム標準化が困難であると指摘されています。
なお、移行期限までにシステム標準化が難しいと判断されたシステムは、「特定移行支援システム」として移行期限の延長が認められています。特定移行支援システムを有する可能性がある自治体は、全団体の約3割である554団体であることが公表されています。
自治体システム標準化を進めるためのポイント4つ
移行期限である2025年度末までに、作業がまだ完了していない自治体は、どのようにシステムの標準化を進めればよいのでしょうか。
最後に、自治体システム標準化を円滑に行うためのポイントを4つご紹介します。
業務への影響度が高いシステムから標準化を行う
全てのシステムを一斉に移行しようとすると、業務負担やシステム障害のリスクが大きくなります。
まずは、業務への影響度やシステム間の連携関係を考慮して作業に優先順位を付け、段階的に標準化を進めていくと良いでしょう。
標準化を優先すべきシステムを考える際の指標には、以下の3つが挙げられます。
- 自治体経営に欠かせない基幹業務や基盤となるシステム:国の指針でも基幹業務優先で進めることが示されている
- 契約更新時期のタイミングが近いシステム:二重契約やコストの無駄を防ぐため
- 比較的シンプルなシステム:単純なシステムから着手することで、ノウハウや体制を整えられる
ベンダーと密接に協力を行う
システムの標準化とその後の運用には、ベンダーとの密接な協力が不可欠です。
特に、各業務の影響範囲を適切に把握するためには、ベンダーと粘り強い確認を行うことが大切になります。
ただし、標準化担当者だけでベンダーと調整すると、所管課でないと想定できない観点が抜けて、手戻りが発生する可能性もあります。ベンダーとの調整でテストデータなどが必要となった際は、所管課にもチェックと事前調整を行いましょう。
ICT系に知見がある人材が少ない自治体は、アフターサポートや保守サービスが手厚いベンダーに協力してもらうことがおすすめです。標準化後にトラブルが起こっても、素早い対応が期待できます。
自治体間で連携を取りながら進める
システム標準化に割けるリソースは、どの自治体でも限られています。効率よく進めるためには、他の自治体と連携を取りながら進めることが重要です。
自治体間で、こまめな情報交換や課題・ノウハウの共有、ベンダーとの調整を行うことが、成功への鍵となるでしょう。
自治体ごとに運用方法が異なるため、連携をとるときは自治体ごとの状況も考慮して行うことが大切になります。
国の支援を活用する
自治体システム標準化は国が推し進めている政策であるため、支援も多岐にわたって行われています。
特に、特定移行支援システムがある自治体は、最大2030年度末まで移行経費などを含めた支援を延長することになっているため、活用していきましょう。
財政的支援だけでなく、実務支援機能としてPMOツール(進捗管理等支援ツール)も提供しています。このツールでは、進捗管理の支援を行うほか、最新情報の提供や課題の共有、問い合わせ、質問回答にも対応しています。
技術面や運用面の支援では、デジタル庁から各都道府県にシステム標準化の専門職員である「標準化リエゾン」が派遣されています。標準化リエゾンに相談を行えば、適切な解決策や外部リソースの紹介を受けることができるでしょう。
こうした国の支援も積極的に活用することも、円滑なシステム標準化を行うためには大切になります。
まとめ
国は、自治体の業務の効率化・軽減や、地域格差を埋めて住民サービスの利便性を向上させることを目指し、現在も自治体の情報システムの標準化を進めています。
しかしながら、移行の目標期限までに作業完了が難しい自治体も少なくありません。こうした、特定移行支援システムがある自治体に対しては、国は2030年度まで支援の延長を決めています。
システム標準化には多くのメリットがある一方で、導入作業の負担は大きいです。残り少ない期限の中で効率よく進めるためには、他自治体と連携し、時には国の支援も積極的に活用していくことが大切となるでしょう。
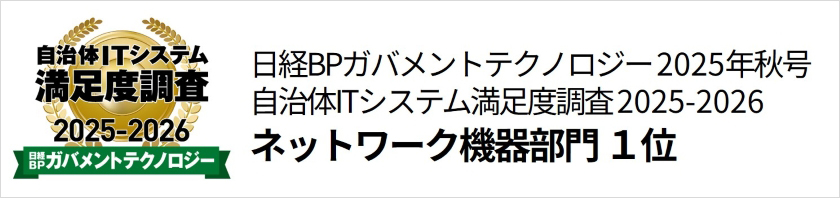
ITシステムの標準化と運用についてお悩みの方もご安心ください。
アライドテレシスは、日経BPガバメントテクノロジー 2025年秋号 自治体ITシステム満足度調査 2025-2026 ネットワーク機器部門において1位を獲得しました。地域密着型のサポート体制と製品で、自治体ITシステムのお悩み・お困りごとの解決を支援します。ぜひお気軽にご相談ください。
- 本記事の内容は公開日時点の情報です。
- 記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。
\注目情報をメールマガジンでいち早くお届け/
あなたの業種に合わせた旬な情報が満載!
- 旬な話題に対応したイベント・セミナー開催のご案内
- アライドテレシスのサービスや製品に関する最新情報や、事例もご紹介!
あなたの業種に合わせた旬な情報をお届け!
旬な話題を取り上げたイベント・セミナー情報や、アライドテレシスの最新事例・サービス・製品情報をご案内します!














 とは?
とは?