昨今は、デジタル技術の発展にともない、医療現場でもAIの導入による業務の効率化が進められています。しかし、AI医療の活用には医療現場のネットワーク環境やセキュリティの確保など、様々な課題が残されています。
本記事では、医療現場におけるAIの活用事例に注目しながら、AI医療の導入に向けた課題を解説していきます。
AI医療とは?活用事例4選も紹介!
AI医療とは、AI(人工知能)技術を医療分野に応用し、病気の予防・診断・治療や病院の運営などを支援して、様々な医療プロセスを高度化する取り組みです。昨今では、高性能ハードウェアの普及によってAIの処理速度や自己学習の精度が向上したため、医療現場でのAI活用が可能になりました。
それにともない、厚生労働省や経済産業省が方針を定めながら、AI医療の導入が国策として進められています。
AI医療の活用事例には、以下のようなものがあります。
画像診断支援
レントゲン、内視鏡、CT、MRIなどの画像をAIが解析して、医師に病変の有無やリスクを提示します。AIはCTに映った1~2mmの初期ガンの兆候などを発見できるため、医師の熟練度の差や疲労による見落としを減らし、診断精度の向上につながります。
問診/治療支援
患者がタブレットなどに症状を入力すると、AIが自動で質問を作成して問診を行います。AI問診はすでに「Ubie(ユビー)」などの活用事例があり、AIが作成した問診票を診察に使用する病院も増加しています。また、診察の内容からAIが疑われる疾患の候補や治療方針を提示することで、医師の判断を補強することも可能です。
病院運営/事務業務支援 /医療文書作成支援
AIが診察時の会話を聞き取って電子カルテを作成したり、患者の診察日程を調整したりといった業務を支援します。また、AIは他病院への紹介状や保険会社に提出する診断書の作成、診療報酬請求などの業務支援も行えるため、記入漏れや入力ミスを予防するとともに、医療従事者の業務負担の軽減につながります。
新薬開発支援
AIが数百万以上の化合物の中から疾患に有効な成分の候補を絞り込み、薬効や副作用の可能性を予測します。これにより臨床試験の成功率の向上が期待されており、新薬開発にかかる時間やコスト削減にもつながります。
このように、医療現場では診療画像を解析するAIや、医師と患者の会話から文章を作成する生成AIなど、様々なAIの活用が広がっているのです。これらの取り組みによって、医療現場の人手不足や労働環境の改善にも期待されています。
AI医療の課題は「ネットワーク環境」と「セキュリティ」
先述しているAI医療の活用事例は、全てオンライン環境を前提に成立しています。そのため、医療AIを導入するには大量のデータを高速かつ正確に処理できるネットワークを構築した上で、患者の個人情報を扱えるだけの十分なセキュリティを確保する必要があるのです。
以下では、AI医療の導入における課題を3つの視点に分けて解説します。
干渉が起きないネットワーク環境の課題
ネットワーク干渉とは、通信に使用している回線が他の回線や電波の影響を受けて不安定になる現象のことです。身近な例では、人混みの中でスマートフォンの通信速度が遅くなる現象が挙げられます。
無線LANでは、広範囲をカバーできる一方で干渉が起こりやすい「2.4GHz帯」と、通信範囲は狭いが干渉が少ない「5GHz帯」「6GHz帯」の3つが主に利用されています。
病院は、CTやMRIなどの大型医療機器が強力な電磁波を発しているほか、電子カルテを閲覧するスタッフやスマートフォンを利用する患者などによって回線が混雑しやすく、ネットワーク干渉が起こりやすい環境です。ネットワーク干渉によって通信やAIの回答生成に遅延が発生すると、診療や治療の遅れにつながる可能性があります。
そのため、AI医療の導入には「干渉が起きないネットワーク環境」の整備が不可欠なのです。
セキュリティ確保の課題
AI医療の導入において最も大きな課題の1つがセキュリティの確保です。特に、患者の既往歴や診断結果などの情報はプライバシーに関わる「要配慮個人情報」に該当するため、万が一でも流出すれば病院の信頼に関わる深刻な問題になりかねません。
また、昨今では病院をターゲットにしたランサムウェア攻撃も発生しています。ランサムウェアとは、ウイルスを送りつけてパソコンやサーバーのデータを暗号化して使えなくすることで、その解除と引き換えに身代金などを要求する攻撃です。これにより電子カルテなどのシステムが使用できなくなると、診療が停止して患者の命に関わる重大な問題が発生するリスクがあります。
こうした背景から、国もAI医療の導入を推進するにあたり「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を定めて、医療機関に高度なセキュリティ対策を求めています。医療機関では、「セキュリティ=患者の命を守る基盤」であるため、利便性よりも情報保護が優先されているのです。
物理的セキュリティの課題
物理的セキュリティとは、人災や災害などからITインフラを物理的に守ることです。物理的セキュリティの確保には、以下のような対策が挙げられます。
サーバールームへの入室制限
カードキーや暗証番号により入室を制限して、入退室のログを記録する。
ネットワーク機器の物理的保護
サーバーやルーターを施錠可能なラックに収納して、無断でのケーブルの抜き差しやUSBの接続を防止する。また、火災時に水を使わず消火できるガス消火設備の導入や、水害時の浸水対策にサーバールームを上階に配置するなどの工夫も重要。
予備電源の確保
停電に備えて非常用電源や無停電電源装置を導入して、システムが停止しない仕組みを整える。
論理的セキュリティの課題
論理的セキュリティとは、データ通信やシステム利用の仕組みそのものを守ることです。病院での論理的セキュリティの確保には、以下のような取り組みが挙げられます。
通信の暗号化
VPN(仮想の専用回線)を用いて電子カルテなどを暗号化して送受信することで、盗聴されても内容を読み取れないようにする。
多要素認証
システムへのログイン時に、パスワードに加えて生体認証やワンタイムパスワードを取り入れることで、アカウント情報が漏えいしても不正ログインができないようにする。
アクセス権限の分離
医師、看護師、事務スタッフなどの役職に応じてアクセスできる権限を制限して、誤操作や内部不正を予防する。
AI医療を安全に活用する3つの対策
以下では、AI医療を安全に活用するための3つの対策を解説します。
AIの学習データの取り扱いに注意する
AIの回答生成の精度は、AI学習に用いられるデータの質と量に依存しています。そのため、診断補助や電子カルテの自動生成などの用途で医療AIを活用する場合は、大量の症例や患者データをAIに読み込ませる必要があります。
この際に重要なのが、AI学習に使用するデータを個人の特定につながらない形に加工することです。例えば、氏名や生年月日などのデータを匿名化しておくことで、万が一情報が漏えいしても被害を最小限に抑えられます。また、AIとの学習データの送受信を閉域ネットワークで行うことで、外部からの不正アクセスを防止できます。
AI医療を活用するには、「データを外に出さない」を徹底した上で、情報漏えいが発生しても被害を最小限に抑えられる体制を整えることが重要です。
チェックや最終判断は人が行う
AIは高い解析力を持つ一方で、誤った情報や存在しない事実を作り出す「ハルシネーション(幻覚)」という現象が発生する可能性があります。AIの一般利用であれば多少の誤答は問題になりませんが、医療現場では誤情報が診断や治療に影響すれば患者の命に関わる重大なリスクとなります。
そのため、AIの回答に対する責任の所在を明確にして、ダブルチェックの体制を整えることが大切です。AIはあくまでも補助ツールであるため、最終的な判断や治療方針の決定は必ず人が行うという原則を徹底することが、AI医療を安全に活用する基盤となるのです。
患者への情報提供を行う
AI医療の導入に対して、患者は以下のような不安を抱えることがあります。
- AIの診断は正確なのか?
- 自分の個人情報はAIに提供されているのか?
- 個人情報が流出するリスクはないのか?
こうした不安を解消するためには、医療機関がAIをどのような体制で運用しているかについて、患者にわかりやすく説明することが重要です。AI医療の有効性や安全性を発信することは、患者との信頼関係を築くために欠かせない取り組みです。
まとめ
AI医療は画像診断や問診、事務業務などで幅広く活用されており、医療現場の負担軽減や業務効率化に貢献しています。一方で、安定したネットワークやセキュリティ、個人情報の保護などの課題も残されています。
また、AI医療を安全に活用するには、AIの回答に対するチェックや運用体制を明確にして、AI医療の有効性や安全性を患者に発信することも大切です。
AI医療を支える安定したネットワーク構築とサイバーセキュリティ対策は、多くの医療機関様のITインフラ構築を支援してきたアライドテレシスにお任せください。
より詳しくご覧になりたい方は以下よりご覧ください。
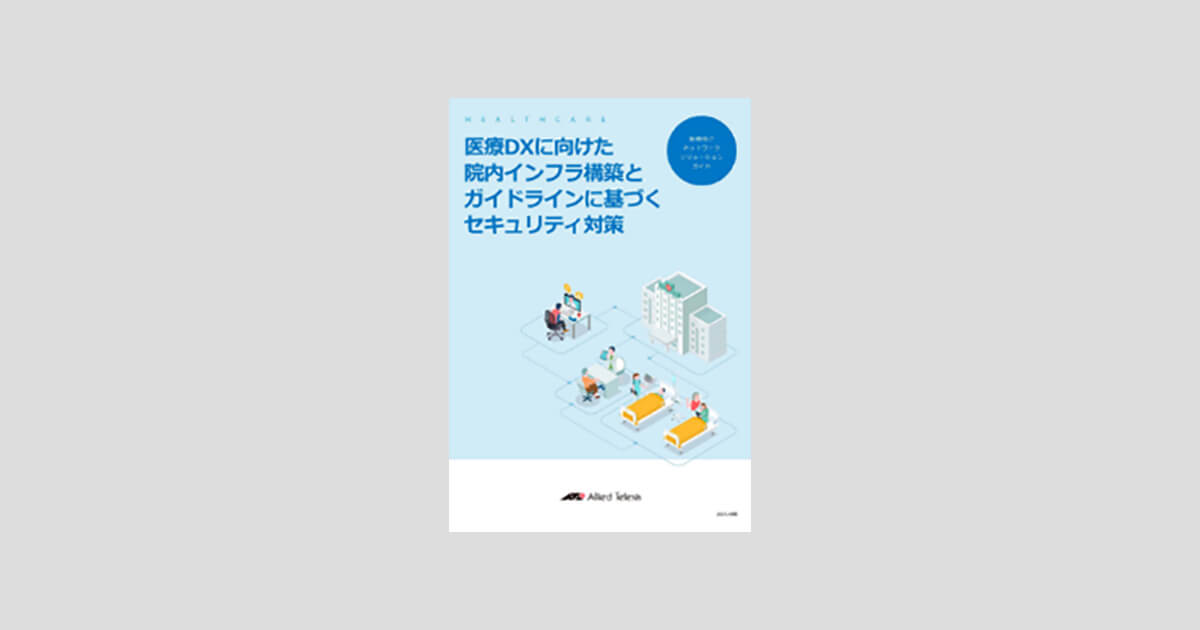
- 本記事の内容は公開日時点の情報です。
- 記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。
ネットワークのお困りごと、まずは相談してみませんか?
現状の把握から課題の解決まで 一緒に考え抜きます!
- どうしたいいかわからないから、とにかく相談に乗ってほしい!
- サービスやソリューションについて、もうすこし聞いてみたい。
- 新しいツールを取り入れたけど、通信が遅くて使えない…。
- 他ベンダーを使っているけど、アセスメントや保守をお願いしたい。
ネットワークのお困りごと
まずは相談してみませんか?
何から始めればいいのか分からずに悩んでいる方、サービスやソリューションについてもう少し詳しく聞きたい方、まずはお気軽にご相談ください!
現状の把握から課題の解決まで、私たちが一緒に考え抜き、最適なサポートをご提案いたします。








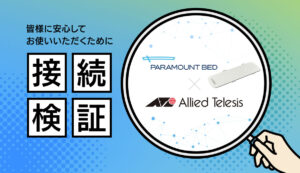





 とは?
とは?