スマートフォンやタブレットが普及した現代では、外出先でも快適にWi-Fi接続ができる環境が求められるようになりました。さらに、国際化や海外観光客の増加などにより、世界中で共通して利用できるWi-Fi環境の需要は急速に高まりつつあります。
本記事では、これらの課題を解決するために開発されたOpenRoamingの基礎知識と導入支援の事例について解説します。
OpenRoamingの概要
OpenRoaming(オープンローミング)とは、Wireless Broadband Alliance(WBA)とその参加企業が共同で開発した、国際的な無線LANローミングの仕組みです。
ローミングとは、本来契約している通信事業者の回線が圏外になった場合に、他社のWi-Fiに自動で接続して通信を継続する仕組みを指します。OpenRoamingはこの考え方を拡張して、世界中の対応スポットで安全かつスムーズにWi-Fi接続ができる環境の実現を目指しています。
従来の公共用Wi-Fiでは、利用するたびにIDやパスワードの入力が必要であり、施設ごとにSSID(Wi-Fiネットワークの名前)や認証方式が異なるため、接続には煩雑な手間が発生していました。また、海外でWi-Fiを利用する際も、専用のSIMカードを購入したりポケットWi-Fiをレンタルしたりといった手間が必要でした。OpenRoamingでは、こうした課題を解決するために、一度端末で利用登録をするだけで世界中の対応Wi-Fiに自動接続できる仕組みを採用しています。また、WBAの認証を受けた通信事業者のWi-Fiにのみ接続されるため、従来の公共用Wi-Fiよりも盗聴やマルウェア感染のリスクが大幅に軽減されており、セキュリティが高いというメリットがあります。
これらのメリットから、国内でもOpenRoamingの導入に注目が集まっているのです。
OpenRoamingの導入事例とメリット
以下では、3つのOpenRoamingの導入事例とそのメリットを解説します。
教育機関での導入事例
OpenRoamingは、特に大学で導入するメリットが大きい仕組みです。多くの大学では、既に学内の学生や研究者を対象としたeduroam(エデュローム)というWi-Fi環境が整備されています。しかし、大学では海外からの留学生や研究者、学外の一般利用者が多いため、eduroamだけでWi-Fi環境をカバーするには限界があります。
そのため、大学がOpenRoamingを導入することで、国内外を問わず来訪者がスムーズにWi-Fiを利用できるようになります。また、OpenRoamingはWBAが策定している国際的なセキュリティポリシーに準拠しているため、世界標準の安全性が担保されている点にも大きなメリットがあるのです。
一方で、小中学校などの教育機関ではWi-Fi利用者が在校生と教職員に限定されるため、OpenRoamingを導入するメリットや必要性はそれほど大きくありません。現在の小中学校では、「GIGAスクール構想」に基づき校内のWi-Fi環境やオンライン学習環境の整備が優先的に進められています。
医療機関での導入事例
医療機関でのOpenRoamingの導入は、患者の利便性の向上に大きなメリットがあります。
これまで、病院内の公共用Wi-FiはSSIDやパスワードの入力が必要であり、高齢の患者やデジタル機器の扱いに不慣れな人にとっては利用が難しいという問題がありました。また、昨今では病院が在留外国人や訪日外国人の患者を受け入れるケースが増加しており、翻訳サービスや多言語案内設備の利用のためにWi-Fiの需要が高まりつつあります。
OpenRoamingはこれらの問題を解決するために注目されています。特に、長期入院の患者にとっては動画視聴や家族とのオンライン通話など、入院生活の快適性を高めるツールとして役立ちます。医療スタッフが患者一人ひとりに対してWi-Fi接続の案内をする手間を省ける点も、副次的なメリットがあると言えるでしょう。
実際の導入事例としては、2024年より東京都立病院機構がアライドテレシス株式会社と連携してOpenRoaming対応のWi-Fiを提供しており、医療機関の新しい通信サービスのモデルケースとなっています。
観光地での導入事例
観光地やイベント会場において、来訪者がストレスなくWi-Fiを利用できる環境を整えることは、観光の質を高める重要な要素です。その中でも、2025年に開催された大阪・関西万博でのOpenRoamingの導入事例は非常に印象的です。
現在では、アジア・ヨーロッパ・欧米などの観光地や都市部では公共Wi-Fiが生活インフラとして浸透しているエリアが多くあります。そのため、海外からの観光客は「公共の場では安全なWi-Fiが無料で使えるのが当たり前」という認識を持つ人が多く、セキュリティに懸念を持ちがちな日本人の感覚とは異なる場合があります。
OpenRoamingには、こうした国内外での公共Wi-Fiのサービス格差をなくす役割があるため、日本でも観光地や空港などの施設を中心に段階的に導入が進められているのです。
OpenRoamingの導入支援3つの取り組み
以下では、国内で行われているOpenRoamingの導入支援について解説します。
地方公共団体による導入支援
OpenRoamingは、「地域DXの推進」「公共サービスの質の向上」「観光振興」などの観点から、地方公共団体による導入支援が行われています。導入支援は設備の設置や運用に関する技術的サポート、導入費用の補助が中心であり、地域ごとのデジタル格差の是正に期待されているのです。
例えば、東京都は「つながる東京」というプロジェクトを掲げており、2023年時点では約600箇所に設置されていた「TOKYO FREE Wi-Fi」を、2025年に1300箇所にまで拡大してOpenRoamingの対応を進めています。
また、地方の観光地や公共施設でもデジタル案内板やキャッシュレス決済との連携において、OpenRoamingが活用されるケースが増加しており、地域DXの推進が進められています。
さらに、沖縄や北海道などでは自治体と通信事業者が協力してOpenRoamingの試験的な導入が行われており、検証結果を基に地域ごとの需要に合わせた公共Wi-Fiの最適化も模索されています。
通信事業者による導入支援
OpenRoamingの根幹を支えるWBAは、以下のような世界共通の運営基準を策定しています。
- 国際的な認証局の運営(信頼できるIDを持つ端末のみを接続させる)
- セキュリティ基準の策定(通信にWPA3などの最新の暗号化方式の利用を推奨)
- 相互接続のルール作成(国や事業者を問わず共通のサービスを利用できる仕組み)
こうした基準を踏まえ、大手通信キャリアは、スマートフォンの回線(4G/5G)とOpenRoamingを連携させたハイブリッド運用を進めています。これにより、圏外エリアの補完やデータ通信コストの削減に期待されます。
また、大手通信キャリアが医療機関や教育機関に対して、OpenRoaming導入のコンサルティングやシステム構築を支援するケースも増加しています。
ネットワーク機器ベンダーによる導入支援
OpenRoamingの導入や普及には、ネットワーク機器ベンダーの役割も欠かせません。ベンダーは直接的に補助金や制度支援などの政策を担うわけではありませんが、OpenRoaming対応機器の開発・提供によって通信インフラの整備を技術的に支えています。
代表的な事例として、アライドテレシス株式会社は札幌学院大学と共同でOpenRoamingの実証実験を行っており、国内ベンダーで初めてWBAの認証を受けたアクセスポイント(Wi-Fiの電波を飛ばす機器)を提供するに至りました。
こうしたベンダーの取り組みがあるからこそ、安全性と利便性を両立したWi-Fi環境が実現しているのです。
まとめ
OpenRoamingは、世界中のどこでも共通のIDで公共用のWi-Fiを利用できる環境を整備する取り組みです。OpenRoamingの導入は、海外からの観光客や留学生の利便性を高めるだけでなく、医療機関や公共施設におけるサービス向上にもつながります。
そのため、地方公共団体、通信事業者、ネットワーク機器ベンダーが中心となり、OpenRoamingの導入支援が進められているのです。
アライドテレシスも、ネットワーク機器ベンダーとしてOpenRoamingの利用に必要な機能を搭載したWi-Fi 6/6E/7対応無線LANアクセスポイントを多数リリースし、OpenRoamingの導入を支援しています。
OpenRoamingについての詳しい内容はこちらもご覧ください。
- 本記事の内容は公開日時点の情報です。
- 記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。
\注目情報をメールマガジンでいち早くお届け/
あなたの業種に合わせた旬な情報が満載!
- 旬な話題に対応したイベント・セミナー開催のご案内
- アライドテレシスのサービスや製品に関する最新情報や、事例もご紹介!
あなたの業種に合わせた旬な情報をお届け!
旬な話題を取り上げたイベント・セミナー情報や、アライドテレシスの最新事例・サービス・製品情報をご案内します!



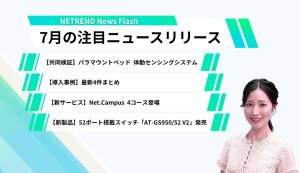





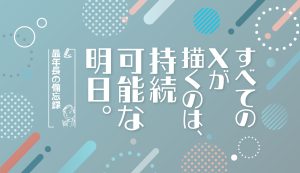




 とは?
とは?